職場でいつも 冷静・真面目・控えめ…
なんだか目立てない自分にモヤモヤしていませんか?
そんなあなたに朗報です。
この記事では、“職場でユーモアのある人”がどんな言動をしているか、そしてなぜそれが信頼を生み、チームを動かす力になるのかを、心理学的研究と実体験を交えて丁寧に解説します。
この記事を読むことで、あなたも「ユーモアはセンスではなく習慣である」と実感し、職場でユーモアを発揮する足がかりが得られるでしょう。

私自身、真面目な性格ゆえに「冗談を言って空気を壊したらどうしよう」と毎日考えていました。
でもある時、小さな“和ませる一言”でチームの雰囲気が変わった経験があります。
この記事では、そのリアルな体験をもとに、同じように悩むあなたに“安心して一歩踏み出せる”情報をお届けします。
- ユーモアは“笑わせる”技術ではなく、“安心させる”力
- 観察力と距離感が、ユーモアを支える土台
- 小さな習慣がユーモア感覚を育てる
- ユーモアは“信頼を生むビジネススキル”
職場でユーモアのある人の特徴5選
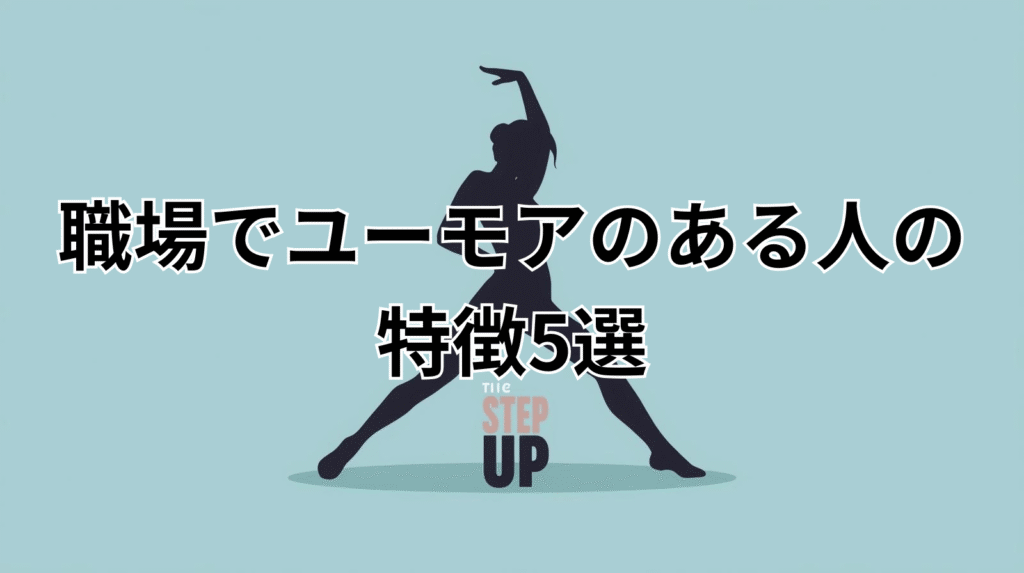
職場で「話しやすい」「雰囲気を明るくしてくれる」と言われる人には、共通した特徴があります。
ユーモアは“おもしろさ”ではなく、“人との距離をやわらげる力”です。
ここでは、職場でユーモアのある人に共通する5つの特徴を紹介します。
- 場の空気を読む観察力がある
- 人を笑わせるのではなく“和ませる”
- 言葉選びが丁寧で攻撃的でない
- タイミングと距離感を大切にしている
- 自分の失敗を笑いに変える余裕がある
場の空気を読む観察力がある
職場でユーモアのある人は、まず「今、相手がどんな気分か」をよく見ています。
笑わせるよりも、空気を読む力が先にあるのです。
私のかつての同僚に、会議の張り詰めた空気を一瞬でやわらげる人がいました。
彼女はいつも発言の前に周囲の表情を見て、一呼吸おいてから言葉を選んでいました。
その一言に笑いが起こり、緊張していた上司も自然と笑顔になる。
これが観察力の力です。
- 空気を読むことがユーモアの第一歩
- 相手の反応を見てから発言する
- “場を明るくする意識”が根底にある

私自身も以前、無理に冗談を言って空気を凍らせた経験があります。
そこから「話す前に一拍おく」だけで、会話が驚くほどスムーズになりました。
人を笑わせるのではなく“和ませる”
ユーモアのある人は、相手を笑わせるより「緊張をとく」ことを意識しています。
たとえば、ちょっとした失敗を自分からネタにして「私もやったことありますよ」と共感を示すと、相手の安心感が生まれるでしょう。
日本笑い学会の研究でも、相手と共感を共有する“共感的ユーモア”が信頼構築に寄与することが報告されています。
- 「笑わせる」より「安心させる」
- 共感をベースにした笑いが信頼を深める
- ユーモアは相手への思いやりの形

ウケなかったときを考えると、ためらってしまいますよね。
でも“笑わせる”目的を“和ませる”に変えると、緊張が不思議と消えます。
言葉選びが丁寧で攻撃的でない
ユーモアのある人は、決して相手を傷つける言葉を使いません。
冗談や軽口のつもりが、受け取る側には「からかい」と感じられることがあります。
「いじり」と「ユーモア」は紙一重です。相手の立場を想像し、ネガティブな言葉をポジティブに変える姿勢が信頼につながります。
- 言葉にトゲを含ませない
- 相手が笑顔でいられる範囲を見極める
- “思いやりのフィルター”を通して話す

誰かに冗談を言う時に、誰かを傷つけてしまわないかをいつも考えています。
「優しいユーモアを選ぶ」ことで、周囲の人が不快にならずに済むでしょう。
タイミングと距離感を大切にしている
タイミングを誤ったユーモアは、かえって場を白けさせます。
成功する人は“今は笑いの時間か、それとも真剣な場か”を感覚的に見極めています。
これは場数を踏むほど身につくスキルで、会話の流れや相手の集中度を観察することで鍛えられるでしょう。
- タイミングを間違えると逆効果
- 空気を読む力は経験で磨かれる
- 会話全体のリズムを意識する

真面目な会議の中でも、適切な間に笑いが入ると場の集中力が上がります。
ユーモアはリズムの潤滑油だといえるでしょう。
自分の失敗を笑いに変える余裕がある
最後に、ユーモアのある人は“完璧でいよう”としません。
むしろ自分のミスや失敗を軽く笑いに変えることで、周囲の緊張をほぐします。
会議で緊張しているとき、同僚が「緊張して震えると思ったらスマートフォンでした」と笑いに変えた瞬間、場の空気が一気に和んだのを覚えています。
そのとき感じたのは、ユーモアは“完璧さ”より“余裕”から生まれるということです。
- 失敗を恐れず、自分を笑える余裕を持つ
- “笑いの共有”が人間関係を温める
- 真面目さの中に遊び心を持つことが信頼につながる

完璧であろうとするより、“人間らしさ”を見せる方が信頼される。ユーモアは「弱さを見せる勇気」でもあります。
職場でユーモアのある人の役割とは?
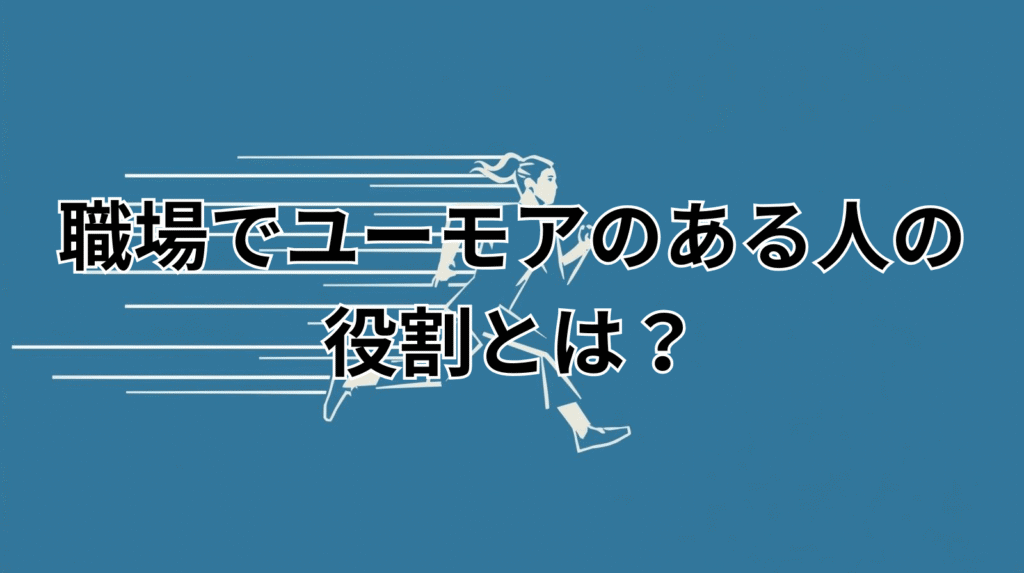
「ユーモアのある人って、結局どういう役割があるんだろう?」
そう感じる人は少なくありません。
笑いを取るタイプではなく、むしろ“安心して話せる人”こそが職場でのユーモアのある人です。
ここでは、ユーモアの意味と背景、そして職場で好かれる人の特徴を心理的観点から解説します。
- ユーモアの定義とビジネスシーンでの意味
- ユーモアのある人が職場で好かれる理由
- 心理的安全性とユーモアの関係
- 真面目な人でもユーモアを身につけられる理由
ユーモアの定義とビジネスシーンでの意味
一般的に「ユーモア=笑いのセンス」と思われがちですが、ビジネスでは少し異なります。
心理学では、ユーモアとは「相手の緊張を和らげる言動」や「共感を生む言葉の工夫」を指します。
つまり、職場のユーモアとは「場の温度を整えるコミュニケーション技術」なのです。
ユーモアのある人は、冗談を言うタイミングだけでなく、“相手を尊重した言葉選び”を心がけています。
笑いの目的は相手を楽しませることであり、けっして優位に立つことではありません。
- 職場でのユーモアは「空気を整える力」
- 相手を笑わせるより「安心させる」意識が大切
- 尊重・観察・共感の3要素がユーモアの基盤

私も以前は「ユーモア=面白くなければいけない」と思っていました。
でも実際は、言葉の温度を少し上げるだけで、場の雰囲気は驚くほど変わります。
ユーモアのある人が職場で好かれる理由
ユーモアのある人が好かれるのは、単に「面白いから」ではありません。
本質は「一緒にいて安心できる」「失敗しても受け止めてくれそう」と感じさせる空気にあります。
職場では緊張や気遣いが絶えません。その中で、少し笑わせてくれる人は“呼吸を戻してくれる存在”なのです。
たとえば、同僚が仕事でミスをしたときに「なかなかの大物だな」とやわらかく言える人。
そんな一言が、全員の肩の力を抜いてくれます。
- ユーモアの根底には「安心感」がある
- 緊張を解く人ほど、信頼されやすい
- 冗談より「包容力」が職場での魅力になる

私も以前、冗談を言えない自分を気にしていました。
でも、同僚から「あなたが笑うだけで場が和む」と言われた時、無理して面白くなる必要はないと気づきました。
心理的安全性とユーモアの関係
丸山淳市・藤桂(2022)の研究では、ユーモアが「心理的安全性」を通じてチームの創造性を高める可能性があることが報告されています。
心理的安全性とは、メンバーが「自分の意見を安心して言える」と感じる状態のこと。
その雰囲気を作る鍵の一つが、相手の緊張をほどく“共感的ユーモア”です。
つまり、ユーモアのある人は単に空気を明るくするだけでなく、「安心して意見を出せる場」を作り出しています。
これはチームリーダーだけでなく、すべての社員にとって重要なスキルといえるでしょう。
- ユーモアが心理的安全性を高める
- 安心できる場がチームの創造性を生む
- 笑いは“関係の潤滑油”ではなく“信頼の架け橋”

私の前職でも、会議がピリついた時に上司が「これ、きっとAIなら即却下ですね」と言って笑いを取った瞬間、全員が話しやすくなったのを覚えています。
真面目な人でもユーモアを身につけられる理由
「自分は真面目だから、ユーモアなんて無理」と思う人も多いでしょう。
しかし、ユーモアはセンスではなく“考え方の柔軟さ”です。
誠実な人ほど、相手の立場を思いやる力が強いため、ちょっとした言葉の工夫で十分にユーモアを発揮できます。
たとえば、報告メールに「早く提出しすぎて自分でも驚きました」と添えるだけでも、受け取る側は和やかな気持ちになります。
大切なのは「完璧を目指すより、余白を持つこと」。その余白にユーモアが宿ります。
- 真面目な人ほどユーモアを活かせる
- ユーモアは“余白”から生まれる
- 完璧主義を少し手放すと柔らかい印象になる

私も昔は「きちんとしなきゃ」と思い詰めていました。
でも、力を抜くことでユーモアを持てると、今は思います。
職場でユーモアのある人が生み出す3つの効果
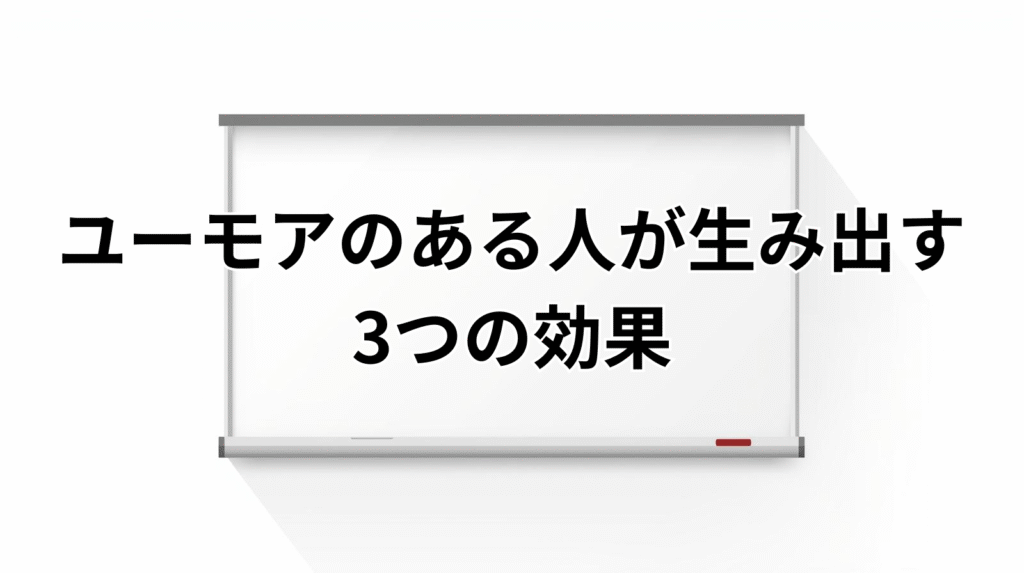
ユーモアは「楽しい雰囲気を作る」だけではありません。
実は、組織心理学の観点から見ても、ユーモアにはチームの成果や人間関係に影響を与える重要な役割があるのです。
ここでは、ユーモアのある人が職場にもたらす3つの効果を紹介します。
- 心理的安全性を高める効果
- チームの創造性・生産性向上
- ストレス緩和と人間関係の改善
心理的安全性が高まり発言しやすくなる
ユーモアがある職場は、意見を言いやすい空気が生まれます。
「笑っても大丈夫」「少しの失敗なら許される」という雰囲気が、心理的安全性を育てるのです。
丸山淳市・藤桂(2022)の研究によると、共感的ユーモアを交わすチームほど、創造的な発言が増え、ミスを共有しやすくなる傾向があると示されています。
私自身、以前の職場で上司が「今日はスライドが脱走したね」と笑いながらミスを受け止めた瞬間、場が和みました。
誰も責めることなく、むしろ次の改善案が自然に出てきたのです。
- ユーモアが「発言しやすさ」を生む
- 笑いは安心と信頼のサイン
- チームの心理的安全性が高まるほど意見交換が活発になる

真面目な場でこそ、ユーモアが必要です。
緊張をやわらげる一言が、次の建設的な対話を引き出します。
チームの創造性・生産性が上がる
ユーモアのある環境は、発想を柔らかくし、チームの創造性を引き出すのです。
冗談を交わすとき、私たちの脳は一時的に“緊張モード”から“発想モード”に切り替わります。
この瞬間、既存の枠を超えたアイデアが出やすくなるのです。
また、ユーモアは「上下関係の圧力」をやわらげる効果もあります。
リーダーが少し笑いを交えるだけで、部下は安心して意見を出しやすくなり、結果として業務の効率も上がります。
日常の小さな会話が、組織全体の創造力を底上げしているのです。
- 笑いが緊張をほぐし、発想力を高める
- ユーモアは上下関係をフラットにする
- チームの効率・成果にも良い影響を与える

私がリーダーを任されたとき、真面目に進行することばかりを意識してしまい、場の空気が固くなってしまったことがあります。
そのとき気づいたのは、リーダーシップには「正確さ」だけでなく、「ほっとできる余白」も必要だということでした。
ストレス軽減と人間関係の改善
ユーモアは、ストレスマネジメントの一つでもあります。
緊張した場面で笑いが生まれると、脳内でストレスホルモンの分泌が減少し、心が軽くなることが知られています。
たとえば、ミスをした同僚に「自分もこんなミスをした」と明るく声をかけるだけで、重い空気が変わります。
責めるのではなく、軽い笑いで受け入れる。それだけで職場の空気は穏やかになります。
- ユーモアはストレス軽減に役立つ
- 人間関係の衝突を和らげる
- 軽い笑いがチーム全体の安心感を育てる

笑いは「共感のサイン」として働き、互いの信頼を自然に深めるのです。
無理に笑わせる必要はありません。
ちょっとした言葉の選び方や柔らかい反応でも、安心感を生みだせるでしょう。
職場でユーモアのある人になる方法
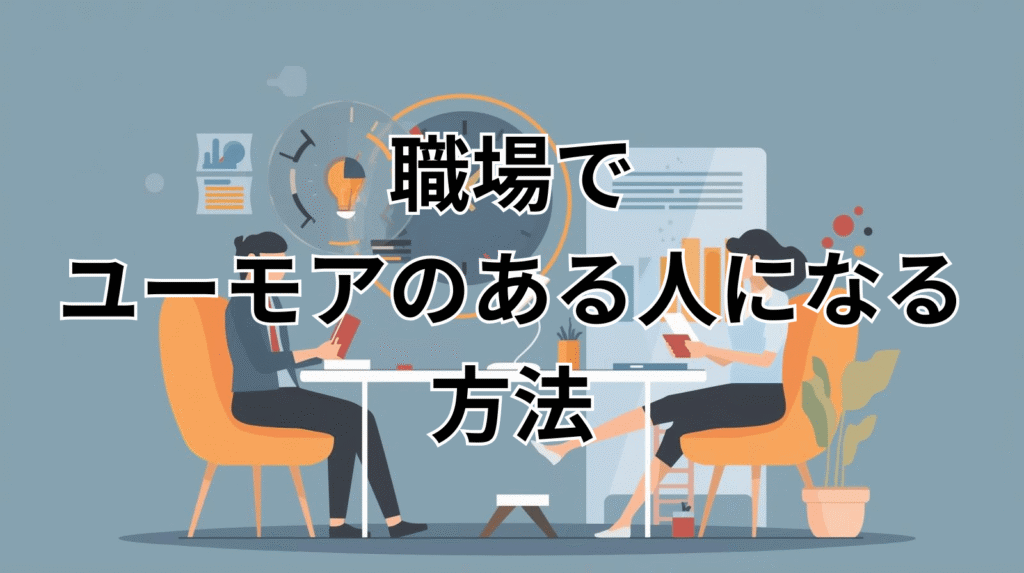
「どうすればユーモアのある人になれるのか?」
そう思っても、“お笑いの才能”が必要なわけではありません。
ユーモアはセンスではなく、日常のちょっとした工夫や習慣から身につけられるのです。
ここでは、明日から実践できる「職場でユーモアを使う方法」を具体的に紹介します。
- 会話や会議で使える和ませるフレーズ例
- 相手に合わせた笑いの取り方
- “スベった”ときのフォロー方法
- 日常でユーモア感覚を鍛える3つの習慣
雑談・会議で使える“和ませるフレーズ”例
まずは、日常会話の中で使いやすい「和ませる一言」から始めましょう。
たとえば、次のような軽い言葉が職場の空気をやわらげます。
| シーン | フレーズ例 |
|---|---|
| 朝のあいさつ | 「今日もエンジンがかかるのは昼過ぎかも」 |
| 会議前 | 「この案件、昨日の夢にも出てきました」 |
| ミスが起きたとき | 「これ、未来の自分に謝っておきます」 |
| 雑談中 | 「この話、3回目聞いても面白いですね」 |
こうした一言は、笑いを取るためではなく“壁を下げる”ためのもの。
ちょっとしたユーモアが、相手の緊張を解き、会話のリズムを生み出します。
- フレーズは「笑わせる」より「やわらげる」目的で使う
- 誇張・比喩を入れると自然にユーモラスになる
- 無理に面白くしようとせず「軽く口角を上げる」だけでも十分

私も会議が苦手でしたが、「今日もZoomが私の集中力を試してます」と言うだけで空気が少し和らぎました。
相手に合わせた笑いの取り方
ユーモアの効果は、相手によって違います。
同じ冗談でも、上司に言うのか、部下に言うのかで伝わり方が変わります。
| 相手 | 効果的なユーモア | 注意点 |
|---|---|---|
| 上司 | 自分を軽く下げるタイプの冗談(例:「私の報告書、また小説みたいになっちゃいました」) | 相手をいじらないこと |
| 同僚 | 共通の話題をネタにする(例:「この会議、毎回デジャヴですね」) | 内輪ノリになりすぎないこと |
| 部下 | 親近感を出す自虐や日常ネタ(例:「このミス、私も新人時代に3回やりました」) | 指導の場で使いすぎないこと |
相手に合わせたユーモアは、「あなたを理解しています」というサインにもなります。
人間関係の信頼を深めるきっかけにもなるでしょう。
- 相手によってユーモアのトーンを変える
- “上下関係の緊張”をやわらげる言葉を意識する
- 共通の話題・失敗・季節ネタは汎用性が高い

私は後輩に対して「完璧な人間はAIだけ」と言ったら笑われました。
軽いユーモアが距離を縮めると実感しました。
“スベった”ときのフォロー方法
ユーモアは時に外れることもあります。
しかし、スベった後の対応次第で信頼はむしろ深まります。
たとえば「今12月でしたっけ?」と軽く言い直すだけで、場の緊張はほぐれます。
失敗を気にせず、笑いを自分ごとに変えることが大切です。
むしろ“空気を気にできる人”として、相手に好印象を与えることもあります。
- スベったら“明るく受け止める”姿勢を見せる
- 自分を笑うことで相手を安心させる
- 完璧にしようとせず、自然体で対応する

私も何度もスベりました。
しかし、スベった状況自体もユーモアに利用できるのです。
日常でユーモア感覚を鍛える3つの習慣
ユーモアは一日で身につくものではありません。
ですが、少しずつ意識を変えることで自然に育ちます。
- 観察・傾聴トレーニング
相手の表情・トーンを意識して聞く - 1日1回の小ネタメモ
職場や通勤中に起きた「ちょっと面白いこと」を記録 - 感情を言語化してみる
「今ちょっと疲れてる」「集中切れてきたかも」と口に出すだけでも柔らかい印象に
日常を“ネタ帳”のように観察することで、自然と会話にユーモアが混ざってきます。
無理に笑わせる必要はありません。
日々の余白に気づくことが第一歩です。
- ユーモアは日常の観察力から育つ
- 言葉にすることで心の柔軟さが増す
- “小さな余裕”が笑いの原点になる

私も最初は無理でした。
でも、ニュースなどから毎日1つだけ“軽いネタ”をメモする習慣で、ユーモアを鍛えられたのです。
職場でユーモアを使うときの注意点
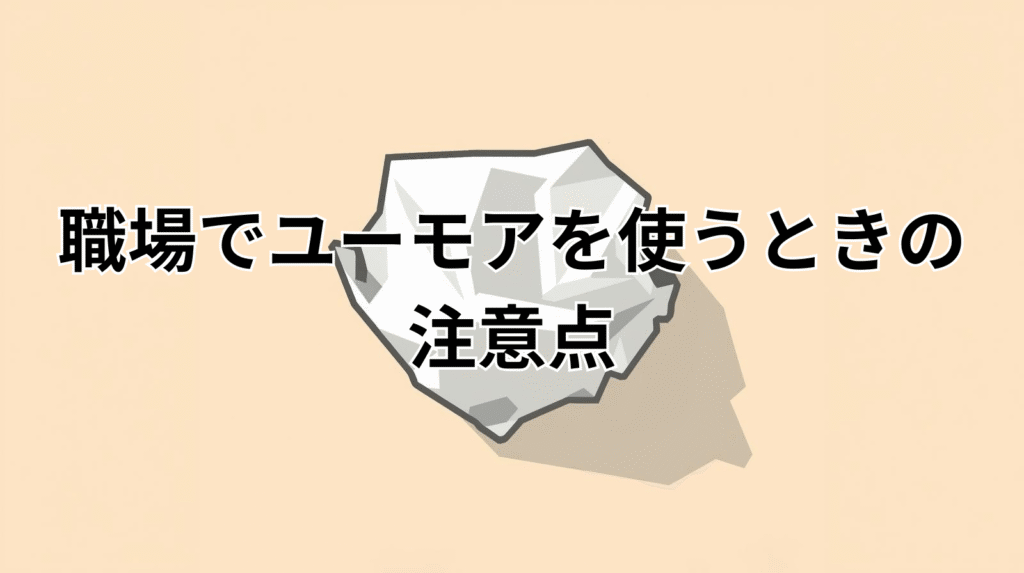
ユーモアは職場を明るくしますが、使い方を誤ると誤解や不快感を生むこともあります。
特にビジネスの場では「笑い」が立場や価値観の違いに影響されやすいため、配慮が欠かせません。
ここでは、ユーモアを使うときに気をつけたいポイントと、避けるべきNG例を紹介します。
- 相手をいじる・否定する笑いの危険性
- 性・年齢・容姿に関する冗談のリスク
- 自虐しすぎるユーモアの落とし穴
- 公私の線引きとユーモア管理の考え方
相手をいじる・否定する笑いは逆効果
「仲が良いから大丈夫」と思って言った冗談が、相手を傷つけることがあります。
悪意のない冗談でも、状況や関係性によっては不快感を与える場合があるでしょう。
たとえば「ミス常習犯だね」と軽く言ったつもりでも、相手にとっては信頼を損なう一言になりかねません。
ユーモアは“対等な関係の上”で成り立つもの。
相手の立場や性格を見極めることが大切です。
- 「いじり」は笑いではなく攻撃になることがある
- 相手のリアクションを観察しながら使う
- 冗談よりも「共感」を優先する姿勢を持つ

以前、軽い冗談を言った後に相手の笑顔が引きつっていたことがあります。
その日から「笑わせるよりも、笑い合う」を意識するようになりました。
性・年齢・容姿に関する冗談はNG
最も避けるべきなのが、性別・年齢・見た目に関する話題です。
どんなに親しい間柄でも、これらはハラスメントと紙一重。
笑いのつもりが「からかい」として受け止められ、職場全体の信頼を損ねるリスクがあります。
特に立場が上の人ほど注意が必要です。
上司の冗談は、相手に“笑うしかない空気”を作ることがあり、強制的な笑いに変わってしまうのです。
- 性・年齢・容姿の話題は避ける
- “笑ってもらえた”=“楽しんでもらえた”ではない
- 立場が上の人ほど慎重に使う

私も以前、年齢の話題を軽く出してしまい、後で「不快に感じた」と伝えられたことがあります。
悪気がなくても、受け取り方は人それぞれ。
笑いより信頼を優先すべきだと痛感しました。
自虐が過ぎると信頼を損なうことも
「自分を笑うユーモア」は場を和ませる効果があります。
しかし、過剰な自虐は“自己否定”として受け止められることもあるのです。
たとえば「自分は何をやってもダメです」と繰り返すと、笑いよりも心配を招いてしまいます。
自虐ユーモアのコツは“軽さ”と“回復力”にあります。
「今のミス、前世の私のせいですね」といった明るいトーンなら、前向きな印象を残せるでしょう。
- 自虐ユーモアは軽く・明るく
- 度が過ぎると「ネガティブ印象」を与える
- “笑ってもらう”より“安心してもらう”意識を持つ

私も一時期「自分下げネタ」を多用していましたが、同僚に「本気で落ち込んでる?」と聞かれたことがありました。
それ以来、笑いの中にも“前向きさ”を残すよう心がけています。
公私の線引きを意識したユーモア管理
ユーモアは職場を明るくする一方で、「公私の境界」を曖昧にしやすい側面があります。
仲良くなるほど距離感が近づき、ついプライベートな話題や内輪ノリに踏み込みがちです。
しかし、それが周囲に“排他的な空気”を生むこともあるのです。
特定の人だけが笑っている状況は、他の人には疎外感を与えます。
職場のユーモアは“全員が安心して共有できる笑い”であることが理想です。
- ユーモアは「共有の場」で使う
- 内輪ネタは“外の人”を置き去りにしやすい
- 全員が安心できる範囲で使うのが基本

仲の良い人とだけ盛り上がる笑いは、他の人にとって「壁」にもなります。
私は今、“誰も置いていかない笑い”を意識するようにしています。
まとめ|職場でユーモアのある人は“信頼を生む人”
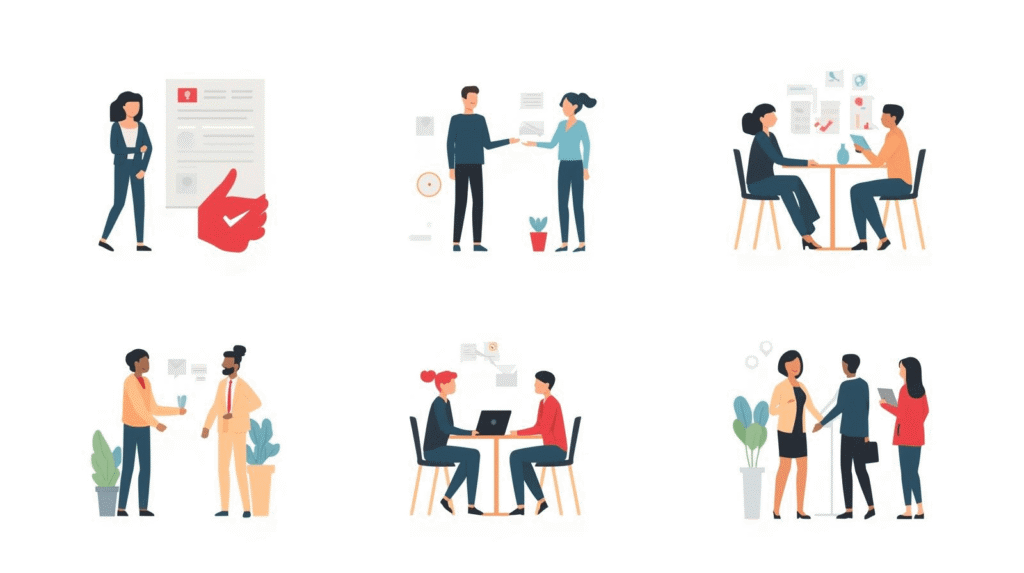
これまで見てきたように、「職場でユーモアのある人」は単なる“面白い人”ではありません。
その本質は「人に安心感を与え、信頼を築く人」です。
最後に、本記事の要点を整理しながら、あなたが明日から取り入れられる実践のヒントをまとめます。
本記事の要点まとめ(特徴・効果・実践法)
| 観点 | 要点 | 補足 |
|---|---|---|
| 特徴 | 観察力・言葉の丁寧さ・距離感 | ユーモアは相手への思いやりの延長線上にある |
| 効果 | 心理的安全性・創造性・信頼の向上 | 小さな笑いが組織の風通しを変える |
| 実践 | 和ませるフレーズ・失敗の共有・余白を持つ姿勢 | ユーモアは“安心を作る技術”であり、努力で身につく |
ユーモアは一朝一夕では身につきません。
しかし、日々の会話の中で「相手が少しでも楽になれる一言」を意識するだけで、あなたの印象は確実に変わります。
FAQ(よくある質問)
Q1.ユーモアが苦手な人でも身につけられますか
A.もちろん可能です。観察力と共感力を磨くことで自然とユーモアは育ちます。
Q2.どんな職場でもユーモアは通じますか?
A.基本的にどんな環境でも有効ですが、相手の性格や文化を尊重する姿勢が大切です。
Q3.ユーモアで失敗したときはどう立て直せばいい
A.間を取って滑ったことに関連する言葉を言えば、場が和むでしょう。
職場で真面目な人がユーモアのある人になれば、最強
真面目な人ほど、ユーモアを上手に使えます。
それは、相手を思いやる気持ちが根底にあるからです。
真面目さが誠実さを生み、そこに少しの遊び心を加えると、信頼と親しみの両方が得られます。
笑いは、相手を軽くするものであって、自分を軽くするものではありません。
“真面目さと柔らかさ”の両立こそ、これからの職場で求められる人間力です。
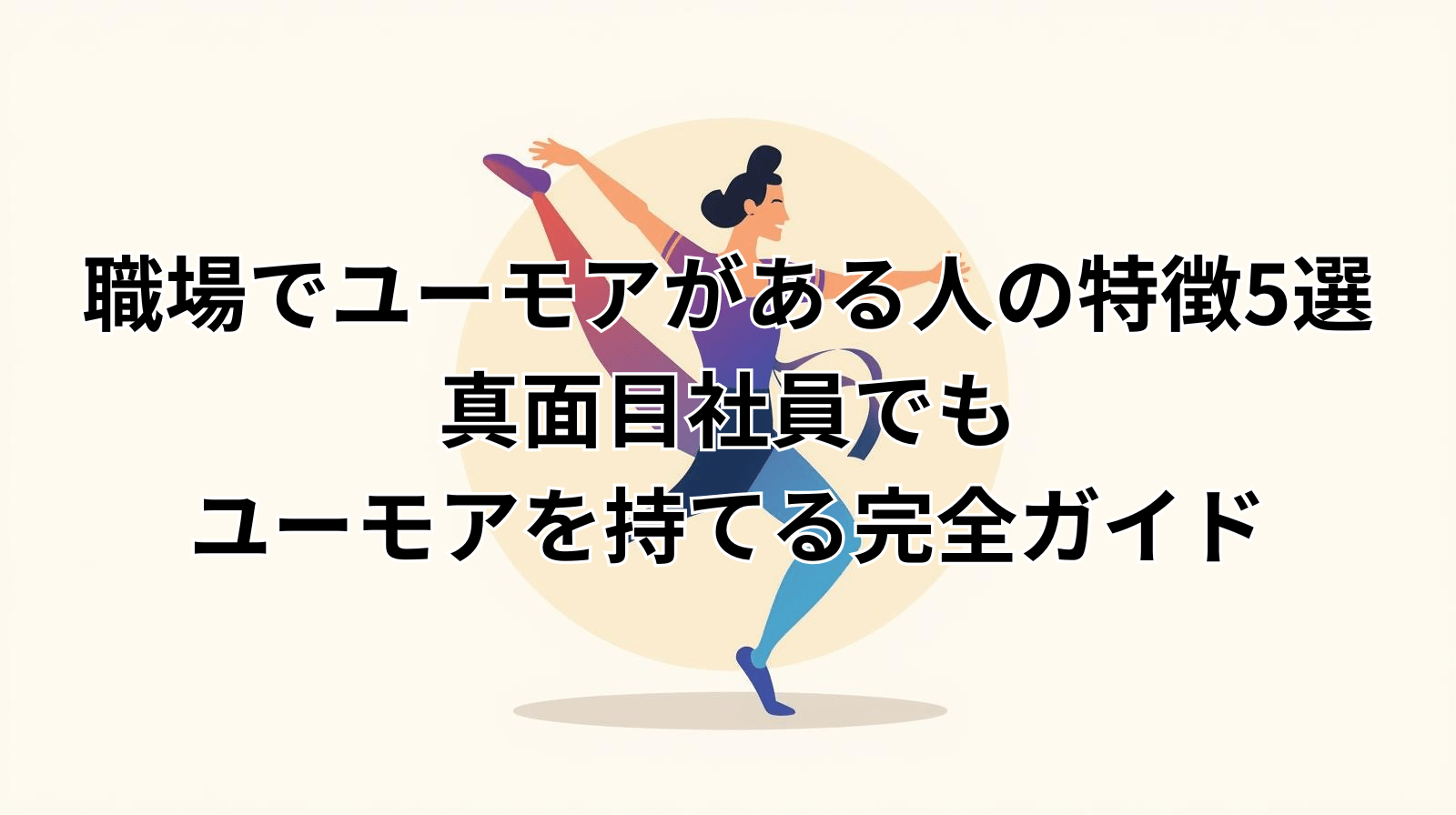
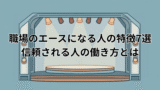
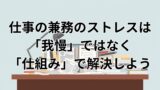
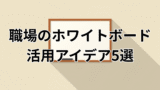
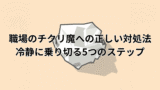
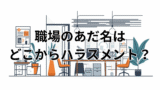
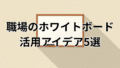

コメント