そんな不安を抱えてこの記事にたどり着いた方は多いのではないでしょうか。
職場で突然静かになるのは、ストレス・人間関係・業務の忙しさなど、複数の要因が絡む“よくある変化”です。
本記事では、厚生労働省・JILPTなどの信頼できる一次情報をもとに、原因の見分け方・正しい接し方・相談すべきラインを整理します。
決して「相手の問題をあなたが背負う必要はない」という前提で、安心して読める構成にしています。
この記事を読み終えるころには、「どう接すべきか」「どこまで踏み込むべきか」が、無理なく判断できるようになるはずです。

私自身、職場で急に静かになった同僚にどう接するべきか悩んだ経験があります。
過剰に気にしすぎて疲れてしまったこともありました。
だからこそ、読者の方が“自分を責めすぎずに済むための視点”を大切にして書いています。
- 「喋らなくなる」理由は一つではなく、心理・人間関係・業務負荷・性格など多面的に存在する。
- 決めつけず“安全に見分ける”ことが大切で、ストレス・業務負荷・トラブルのサインには特徴がある。
- 接し方の基本は、相手の負担を増やさない距離感を保つこと。無理に理由を聞かないほうが良い場合も多い。
- あなた自身の心を守る行動(心理的距離・環境調整・相談窓口の利用)が、長期的には最も大切。
職場で喋らなくなった人には何が起きているのか
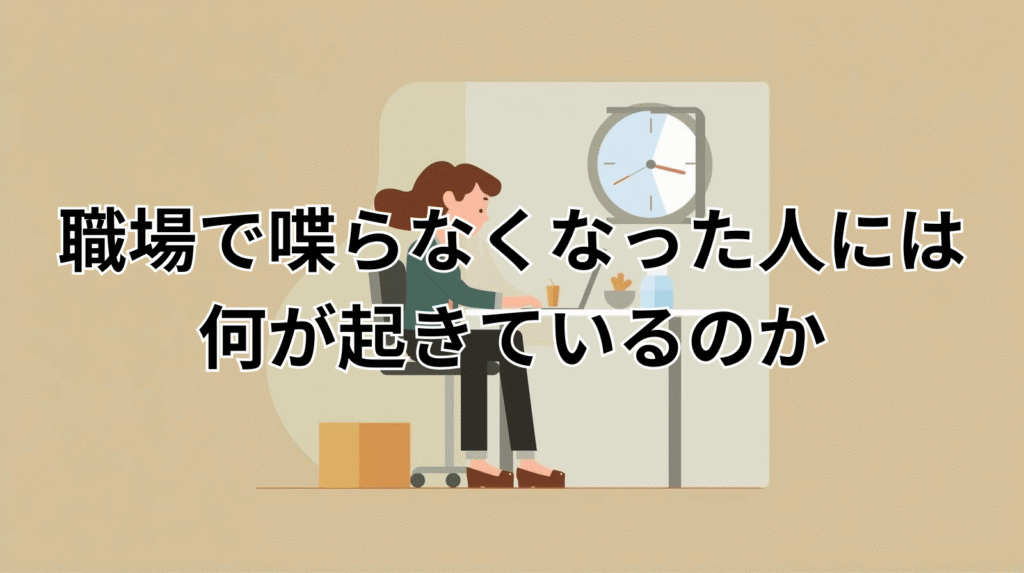
職場で急に静かになる人を見ると、「自分が何かしてしまったのでは…」と不安になるものです。
ただ、厚生労働省のメンタルヘルス資料でも示されているように、沈黙には複数の背景が重なって起こることが多いとされています。(参考:こころの耳)
この章では、喋らなくなる理由を 心理・人間関係・業務負荷・性格 の4つに分類し、それぞれの特徴を整理します。
- 心理的ストレス・メンタル不調が原因の場合とは?
- 人間関係トラブル・ハラスメントが背景にあるケース
- 単純に忙しい・業務に余裕がないパターン
- 性格要因・一時的な気分変化
心理的ストレス・メンタル不調が原因の場合とは?
職場で急に静かになる背景として、最も多いのが心理的ストレスやメンタル不調だといわれています。
コミュニケーションの減少はメンタル不調の要因として考えられ、会話の減少が心の疲れのサインである可能性もあります。(参考:こころの耳)
実際、私自身も以前、業務過多で心の余裕がなくなった時期は、必要な会話以外ほとんど話す気力が湧きませんでした。
「話したくない」のではなく、「話す力が残っていない」状態だったのです。
沈黙は“相手からの拒絶”ではなく、心が疲れて助けを求めているサインとも受け取れるでしょう。
- 心の負荷が高いと、言葉が出なくなることがある
- “コミュニケーション減少”は不調の兆候と考えられる
- 相手の沈黙=自分への否定ではない

ストレスが溜まった時ほど、人は「誰とも話したくない」気分になりやすくなります。
私も同じ経験があるので、読者の方には自分を責めすぎないでほしいです。
人間関係トラブル・ハラスメントが背景にあるケース
人間関係のこじれやハラスメントの発生も、沈黙の大きな要因です。
JILPT(労働政策研究・研修機構)の調査でも「職場内人間関係の不満」が職場トラブルの主要要因として挙げられています。(出典:JILPT「職場におけるコミュニケーションの状況と苦情・不満の解決に関する調査」)
トラブルが続くと、相手は「誰とも関わりたくない」「誤解を生むくらいなら黙っていよう」と感じやすくなります。
喋らないことで身を守ろうとする“防衛的沈黙”とも言えるでしょう。
- 人間関係の悪化は沈黙の大きな原因
- 防衛のために「話さない」を選ぶことがある
- 背景にトラブルがある可能性も考慮する

人間関係で傷ついた人ほど、言葉を閉ざす傾向があります。
無理に問い詰めるより、そっと距離を置くほうが相手の安心につながる場合もあるでしょう。
単純に忙しい・業務に余裕がないパターン
沈黙は必ずしもネガティブな理由とは限りません。
業務が立て込んでいるだけで、会話に回すエネルギーがないケースもよくあります。
私自身、締め切り前になると「話しかけられると逆に焦る」状態になり、必要最低限しか喋らない時期がありました。
沈黙=不機嫌ではなく、ただ“手一杯”になっているだけの可能性もあります。
- 忙しさだけで口数が減るのはよくある
- 生産性向上のために一時的に静かになることも
- ネガティブな推測をしないことが大切

余裕がないときは、誰でも静かになりがちです。
相手の忙しさを尊重するだけで、関係はずっとスムーズになります。
性格要因・一時的な気分変化
無口になる原因として、性格や気分の一時的な波も少なくありません。
内向型の人は、外刺激が多い職場だと疲れやすく、沈黙でエネルギーを回復することがあります。
また、プライベートの事情(家族の問題・体調不良・睡眠不足など)がその日の気分に影響する場合もあります。
性格や気分の波があることを考え、深読みしすぎて疲れないようにしたいですね。
- 性格的に“静かな時間”を必要とする人もいる
- プライベート要因が沈黙を引き起こすこともある
- 深読みしすぎない姿勢が大切

性格やその日の体調で会話量は簡単に変わります。
相手の感情を深読みしすぎないことも、気持ちが楽になるポイントです。
職場で喋らなくなった人の原因別の見分け方
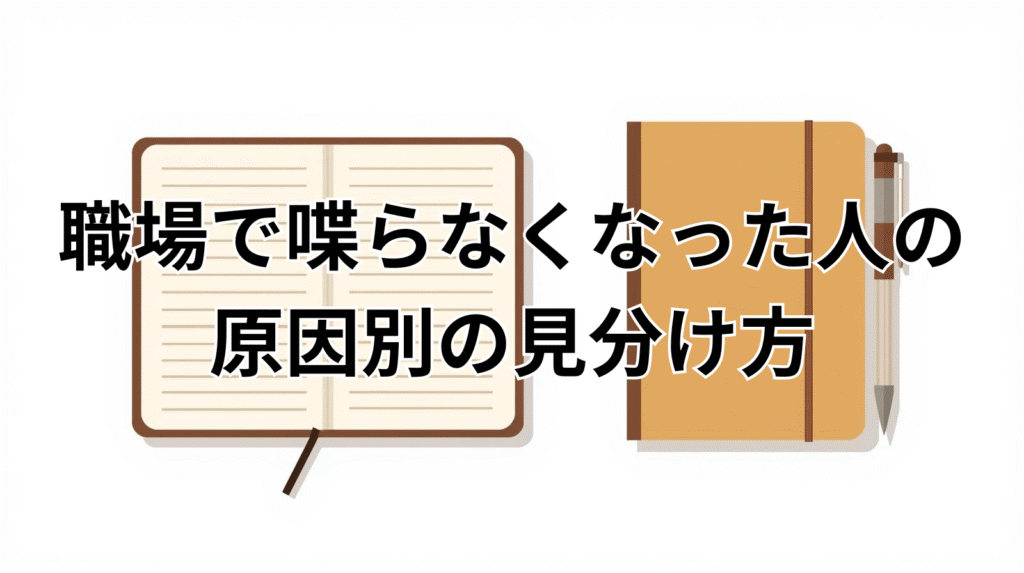
喋らなくなった理由を深読みしすぎると、自分が必要以上に疲れてしまいます。
一方で、無視できないサインを見逃すのも不安が残りますよね。
そこでこの章では、厚生労働省・JILPTなどの一次情報を踏まえながら、相手を決めつけずに“安全に状況を読み取る”ためのチェックポイントを整理します。
あくまで「観察の目安」であり、相手の心理を断定するものではありません。
落ち着いて状況を確認するための補助として使ってみてください。
- ストレス・メンタル不調のサインを正しく捉える
- 業務負荷による沈黙の特徴とは?
- 人間関係トラブルが原因の“距離取り”行動
- 性格的沈黙と問題沈黙の違い
ストレス・メンタル不調のサインを正しく捉える
会話が減る背景として、心理的ストレスやメンタル不調が関係していることは珍しくありません。
こころの耳でも、メンタル不調の兆候として「疲労感」「集中困難」「周囲との関わりの減少」などが挙げられています。(参考:こころの耳)
そのため、沈黙が次のような変化とセットで起きている場合は、“心の余裕の低下”を示している可能性があるでしょう。
- 目が合いにくくなった、もしくは反応が薄い
- 明らかに表情が乏しくなった
- 返信・反応の速度が遅くなった
- ケアレスミスが増えている
- 休憩が増える/席を外す時間が長くなる
私自身、業務が重なって心が追いつかない時期には、まさにこのチェック項目が当てはまりました。
「話したくない」のではなく、「話すためのエネルギーが残っていない」状態だったのを覚えています。
- 厚労省も「関わりの減少」を不調の兆候として提示
- 会話量だけで判断しない
- 行動変化の“組み合わせ”を見ると理解しやすい

沈黙が続く相手を前にすると不安になりますが、まずは事実を静かに確認するだけで心の負担が軽くなります。
業務負荷による沈黙の特徴とは?
「忙しすぎて話せない」というシンプルな理由もよくあります。
日本生産性本部のアンケート調査では、メンタル不調が増加している企業ほど「職場のコミュニケーションが減少している」と回答する割合が高いことが示されています。
(参考:日本生産性本部「第7回 『メンタルヘルスの取り組み』に関する企業アンケート調査結果」)
以下のような行動が見られる場合、メンタルというより“物理的に話す時間がない”状態のことが多いです。
- 常にパソコンに向かっている
- タスクの切れ目がほとんどない
- 短時間で作業を切り替えている
- 話しかけると「あとでいい?」と言われる
- 昼休みも作業に使っている
忙しいだけの人に踏み込みすぎると、逆に負担をかけてしまうことがあります。
私も締め切り前は「今は会話より目の前の作業を終わらせたい」という気持ちが強くなり、静かになりがちでした。
- 忙しさから沈黙が生まれるケースは非常に多い
- “余裕の有無”を見ると判断がしやすい
- 深刻に捉えすぎなくてよいこともある

沈黙の理由を“心”ではなく“状況”から読み取ることで、相手を誤解しにくくなります。
忙しいだけの可能性は常に考えておきたいですね。
人間関係トラブルが原因の“距離取り”行動
人間関係のこじれは、最も沈黙につながりやすい背景のひとつです。
JILPTの調査でも、職場のトラブル要因として「人間関係のストレス」が高い割合を占めています。
(出典:JILPT「職場におけるコミュニケーションの状況と苦情・不満の解決に関する調査」)
人間関係の負担が原因で沈黙が生まれている場合、次のような“距離取り”の行動が見られることがあります。
- 特定の相手とだけ距離を置いている
- 最低限の会話しかしない
- 会議で発言が減り、表情も固い
- 昼休みや退勤時に単独行動が増える
- トラブルが起きた後に口数が一気に減る
以前、私の職場で、人間関係の摩擦を抱えた同僚が「話すほど状況が悪化しそうだから」と話さなくなってしまったことがありました。
沈黙は、自分を守るための“防衛手段”になり得るのだと痛感しました。
- 人間関係の影響は沈黙の大きな要素
- “特定の相手だけ避ける”行動はわかりやすいサイン
- 話さない=相手を拒絶しているとは限らない

人間関係で傷ついたとき、人は沈黙に逃げ場をつくることがあります。
心を守るための自然な反応だと感じます。
性格的沈黙と問題沈黙の違い
「ただの無口」なのか、「問題を抱えている沈黙」なのかは、混同しやすいポイントです。
性格的な沈黙は一時的な変化が少なく、落ち着いたペースで続くことが多い一方、問題沈黙は急激な変化を伴うケースが多いとされています。
次の違いを見ると判断がしやすくなるでしょう。
| 観点 | 性格的沈黙 | 問題沈黙 |
|---|---|---|
| 変化のスピード | ゆっくり・安定 | 急に静かになる |
| 表情 | 穏やか/通常 | 固い・疲れている |
| 行動 | 普段と大きく変わらない | 避ける・反応が薄い |
| 会話の質 | 必要な時は話す | 最低限でも難しそう |
私の同僚にも「静かだけど穏やかで、普通に仕事はこなす」タイプの人がいました。
こうしたケースは問題ではなく、ただの“その人らしさ”です。
- 性格的沈黙は変化が小さく安定している
- 問題沈黙は急激な変化や強い疲労感が出やすい
- “急に”を基準に判断すると混乱が減る

相手の性格を尊重するだけで、こちらの心がずっと軽くなります。変化の大きさを見ることが大切です。
職場で喋らなくなった人への正しい接し方4選
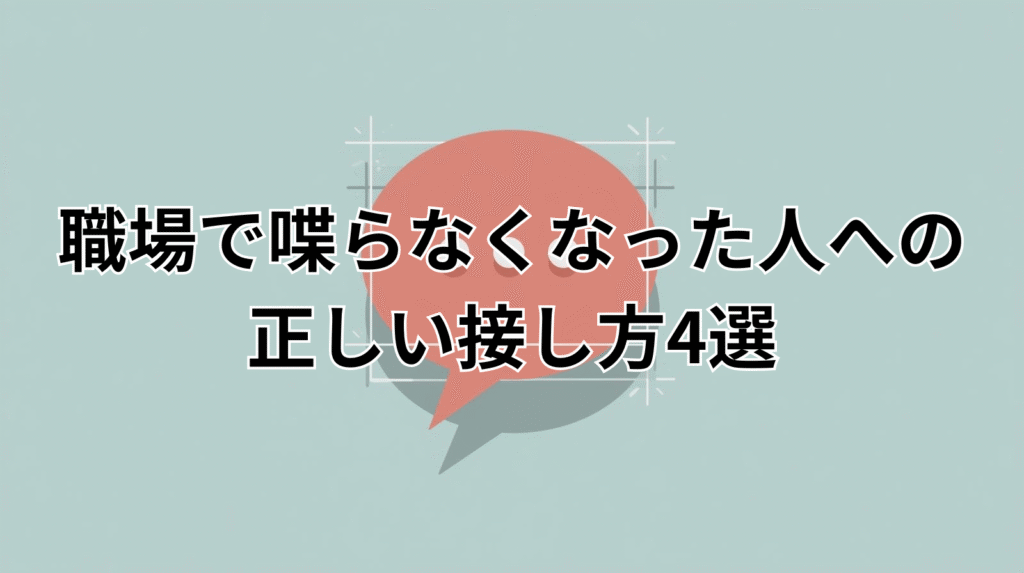
喋らなくなった人に接するとき、最も大切なのは「相手の負担を増やさないこと」です。
厚生労働省のメンタルヘルス指針でも、相手の状況を“無理に変えようとしない関わり方”が推奨されています。(参考:こころの耳)
無理に理由を聞いたり励ましたりすると、状況を悪化させる場合もあるのです。
この章では、距離の取り方・声かけの基準・関わらないほうが良いサインを整理し、あなた自身も疲れないコミュニケーション方法をまとめます。
- 無理に理由を聞かないほうがいい場面
- さりげない声かけの方法(定型文例つき)
- 距離を置いたほうがいいサイン
- 周囲の人が取れるフォロー行動
無理に理由を聞かないほうがいい場面
沈黙の理由を知りたい気持ちは自然ですが、状況によっては逆効果になることがあります。
特に、ストレス・トラブル・業務過多が背景にある場合、「どうしたの?」と踏み込まれること自体が負担に感じられるのです。
以下のような場合は、無理に聞き出さないほうが良いでしょう。
- 顔色が悪く、明らかに疲れている
- 会話を避けようとしている
- 返答が極端に短い・硬い
- 明らかに忙しそう/集中している
- トラブルが起きた直後
私自身も、忙しいときに理由を聞かれたことで、逆に「話すエネルギーまで奪われる」と感じたことがあります。
沈黙は“話したくない”ではなく、“話す余裕がない”だけということも多いのです。
- 無理に理由を聞くと負担になる
- 状況を観察し、“聞かない勇気”を持つ
- 相手の余裕の有無を重視する

相手に寄り添いたい気持ちは素晴らしいですが、ときには「そっとしておく」ことが最大の思いやりになる場合があります。
さりげない声かけの方法(定型文例つき)
必要以上に踏み込まず、負担にならない声かけを選ぶと、相手の気持ちを乱さずにコミュニケーションが保てます。
以下のような一言で済む「観察→配慮」の声かけを試してみてください。
- 「おつかれさま、無理しすぎないでね」
- 「何か必要なことがあったら言ってね」
- 「あとで大丈夫だよ、今は集中してね」
- 「ゆっくりで大丈夫だからね」
- 「話したくなったら声かけてね」
過度に心配を伝えるのではなく、“いつでも距離を保ちながら関われるよ”という姿勢を示すのがポイントです。
大げさな助言ではなく、小さな一言が心の余白をつくります。
- 一言で完結する声かけが負担にならない
- 心配を押しつけず、余白を渡す
- タイミングよりも“短さと優しさ”が鍵

声かけは長くなくて大丈夫です。
たった数秒のやり取りが、相手の安心につながることがあります。
距離を置いたほうがいいサイン
沈黙が続く相手に関わるとき、“あえて距離を置く”ことが最適な場合があります。
相手が明確に「今は誰とも関わりたくない」というサインを出していることもあるからです。
以下に当てはまる場合は、距離を置いた方が良いでしょう。
- 明らかに反応が硬い/短い
- 目を合わせたがらない
- 会話を打ち切るような態度が見られる
- 通常より表情が険しい
- トラブル後で、周囲から距離を取ろうとしている
これ以上踏み込まないでほしいという無言のサインを尊重することで、相手が安心できるのです。
実際に、私の前職でも、ある同僚がトラブル後に数日ほど静かになった場面がありました。
そのとき無理に話しかける人もいましたが、結果として彼はさらに壁を作ってしまい、関係がこじれたことがあります。
適切な距離感は、お互いを守るための大切な視点です。
- 相手の拒否サインを見逃さない
- 距離を置くのも立派な“関わり方”
- 見守る姿勢が結果的に関係を守る

寄り添いと同じくらい、「立ち止まる勇気」も大切です。
無理に関わらないことが、双方にとって良い結果を生むことがあります。
周囲の人が取れるフォロー行動
喋らなくなった本人だけでなく、周囲の環境が整うことで、相手の負担が軽くなる場合があります。
(参考:こころの耳「動画で学ぶ『職場環境等の改善』」)
以下のようなフォローを試してみてください。
- 挨拶だけ続ける(距離感を保ちながら関係を維持)
- タスクを押しつけない
- 無理な“励まし”を控える
- 必要な情報だけ簡潔に伝える
- 匿名相談窓口の存在だけ共有しておく
以前、私の職場で「挨拶だけ続ける」という方法がとても効果的だったことがあります。
踏み込みすぎず、かといって突き放さない。
その“ほどよい距離”が、自然と相手を安心させることにつながりました。
- 周囲もできる小さな工夫がある
- 必要な情報だけ伝えると負担が減る
- あいさつは“距離を保つ優しい関係維持”

誰かが沈黙していると不安になりますが、無理に変えようとせず、できる小さな行動だけ続けることで環境は少しずつ整っていきます。
職場で喋らなくなった人への対応で迷ったときの相談ライン

相手が喋らなくなる状況はさまざまですが、すべてを“様子を見る”だけで済ませてよいわけではありません。
とくに 明らかな異変が続く場合や、ハラスメントの可能性がある場合 は、専門窓口や上司など第三者に相談したほうが安全です。
厚生労働省も、困ったときに一人で抱え込まず相談することを推奨しています。
(参考:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」)
この章では、相談すべきタイミングを明確にし、負担を増やさずに頼れる場所を整理します。
- 上司や人事へ相談すべき状況とは?
- 相談窓口(総合労働相談コーナー/こころの耳)の使い方
- ハラスメントの可能性を感じた場合の行動
- 環境が改善しないときの選択肢(異動・転職)
上司や人事へ相談すべき状況とは?
沈黙が長引き、自分の業務にまで影響が出ている場合は、上司や人事のサポートを得ることが適切です。
以下の場合には、相談したほうが良いでしょう。
- 2週間以上、明らかな異変が続いている
- 明らかな敵意・威圧・無視が始まった
- トラブル後に沈黙と距離取りが強まっている
- あなたの業務に支障が出ている
- 相手本人が“助けを求めたい”サインを出している
相談する際は、感情ではなく“事実だけ”を淡々と伝えるのがポイントです。
メモなどで記録を取って、事実を正確に伝えられるように準備をしましょう。
- 異変が長引くなら早めに相談
- 相談時は“事実のみ”を伝えると伝わりやすい
- 自分だけで抱え込まなくてよい

相談は「弱さ」ではなく、「適切な対応」です。早く動くほど、状況がこじれずに済むことが多いと感じています。
相談窓口(総合労働相談コーナー/こころの耳)の使い方
厚労省が設置する 総合労働相談コーナー は、労働問題・ハラスメント・人間関係の悩みを無料で相談できる公的窓口です。(出典:厚生労働省「総合労働相談コーナー」)
また、メンタル支援に特化した こころの耳 では、電話相談やセルフケア情報が提供されており、「話すのが苦手な人」でも使いやすいサポートが用意されています。(参考:こころの耳)
利用時は以下のポイントを意識しましょう。
- 匿名相談も可能
- 相談内容は組織に直接通知されない
- 不安・違和感レベルの相談でも問題なし
- 行動の選択肢を“整理するだけ”でもOK
公的機関への相談は大ごとにすることではなく、心や状況の整理として活用できることを覚えておいてください。
- 公的窓口は無料かつ匿名可
- 早期利用が状況悪化の防止につながる
- 悩みの整理だけでもOK

自分の気持ちを言葉にする場があるだけで、心の負担は驚くほど軽くなります。
困ったときは、大ごとにしてしまうと恐れずに、相談してみてください。
ハラスメントの可能性を感じた場合の行動
もし沈黙の裏側にハラスメントがあると感じた場合は、早めに専門窓口に相談することをおすすめします。
相談したことを理由とした不利益取扱いを受けることは禁止されているため、遠慮をしないでください。
(出典:厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」)
- 事実をメモして記録
- 信頼できる上司または人事に相談
- 必要に応じて総合労働相談コーナーへ
- 状況が改善しない場合は、社外機関へエスカレーション
昔、私が勤めていた会社でも、ある社員が「相談しただけで立場が悪くなるのでは」と恐れていました。
しかし実際は、相談したことで問題が明確化され、職場環境が改善したケースもありました。
- ハラスメントは早期相談が重要
- “相談しただけで不利益扱い”は法律で禁止
- 記録と事実整理が心の支えになる

不安な状況では冷静さが失われがちですが、記録を残すだけでも落ち着きを取り戻せます。
自分が今置かれている状況を、客観的に見えるようにしましょう。
環境が改善しないときの選択肢(異動・転職)
改善の兆しがなく、沈黙が続いてストレスが限界に近づいている場合は、環境を変える選択も視野に入れましょう。
- 信頼できる上司へ異動を相談
- 人事面談で配置転換を希望
- 転職活動を少しずつ始める
- 外部のキャリア相談を利用する
沈黙に振り回され続けるのは辛いものです。
環境を変えることで、思った以上に気持ちが軽くなることもあります。
これは「逃げ」ではなく、むしろ健全な判断です。
- 環境の変更は適切な選択肢
- 異動・転職も“自分を守る方法”
- 迷うなら第三者の意見を取り入れてよい

環境は人を大きく左右します。心が限界に近いと感じたら、選択肢を少し広げるだけで未来が変わります。
職場で喋らなくなった人に疲れてしまったときのセルフケア

誰かの沈黙に気を取られすぎると、あなた自身がどんどん疲れてしまいます。
「相手の様子が気になる」「なぜ喋らないのか、自分が悪いのか」と考え続けてしまうのは自然なことですが、心のエネルギーを消耗する大きな原因にもなるでしょう。
この章では、相手に合わせすぎず、あなたの心を守るためのセルフケア方法を整理します。
- 心理的距離を取る方法(短期・中期)
- 職場環境を少しだけ整える工夫
- どうしても不安が消えないときの対処
心理的距離を取る方法(短期・中期)
相手の沈黙が気になりすぎると、頭の中が相手のことでいっぱいになってしまいます。
まずは“心の距離”を少しだけ取ることが、最も効果的なセルフケアです。
- 深呼吸して「自分の時間」を意識的につくる
- 相手ではなく“タスク”に意識を向ける
- 「相手の課題」と「自分の課題」を分けて考える
- 昼休みをひとりで過ごす日をつくる
- メモを書いて気持ちを外に出す
- 趣味・運動など“生活の軸”を強める
私も以前、無口になった同僚に気を取られすぎて疲れ切った経験があります。
ただ、昼休みを少し一人で過ごし、帰宅後にメモを取る習慣を作るだけで、驚くほど心が軽くなりました。
- 距離を取るのは“相手を拒否すること”ではない
- 心の余白ができると、相手の変化に振り回されにくくなる
- 自分の軸を少し強めるだけで安定する

人の変化に敏感な人ほど、自分の心を守る工夫が必要です。距離を取ることは優しさの欠如ではなく、健全なセルフケアといえるでしょう。
職場環境を少しだけ整える工夫
周囲の影響で気疲れしている場合、小さな環境改善でも気持ちが大きく変わります。
以下のように、職場環境を少しだけ整える工夫をしてみましょう。
- 座席の向きを少し変える
- ノイズキャンセリングイヤホンを使用
- ToDoリストで“今日やること”を明確にする
- 離席して軽く体を動かす
- 朝一に“自分のペース”を作るルーティンを入れる
私も以前の職場で、定期的に離席して軽く体を動かすようにしたことで集中力が戻った経験があります。
環境はほんの小さな工夫で変えられるのです。
- 環境調整はストレス軽減に役立つ
- 気疲れは“周囲の刺激の多さ”でも生じる
- 小さな変化で働くリズムが整いやすくなる

環境を整えることは、どんな人でも今日からできる“優しいセルフケア”です。
身の回りで、少しでもストレスを改善できるような場所がないか探してみましょう。
どうしても不安が消えないときの対処
心理的距離を取っても、環境を整えても、どうしても不安が消えないこともあります。
不安が消えないときは、以下のように自分だけで抱え込まないことが大切です。
- 信頼できる同僚に“事実だけ”を共有する
- 上司や人事に早めに相談
- メンタルヘルス窓口(こころの耳)でセルフチェック
- 体調が悪い場合は休む勇気を持つ
厚労省の相談窓口は匿名で利用でき、「悩みの整理だけ」でも使えるため、心理的ハードルを下げて相談できます。(参考:こころの耳)
周囲に信頼できる人がいない場合には、メンタルヘルス窓口などに相談することも考えましょう。
- 不安が続くときは“共有”が効果的
- 公的窓口は匿名で使える
- がんばり続けるより、休むことのほうが重要な日もある

あなたの不安は、あなたひとりだけの責任ではありません。
外部の力を借りることは、とても健全な行動です。
職場で喋らなくなった人への対応まとめ
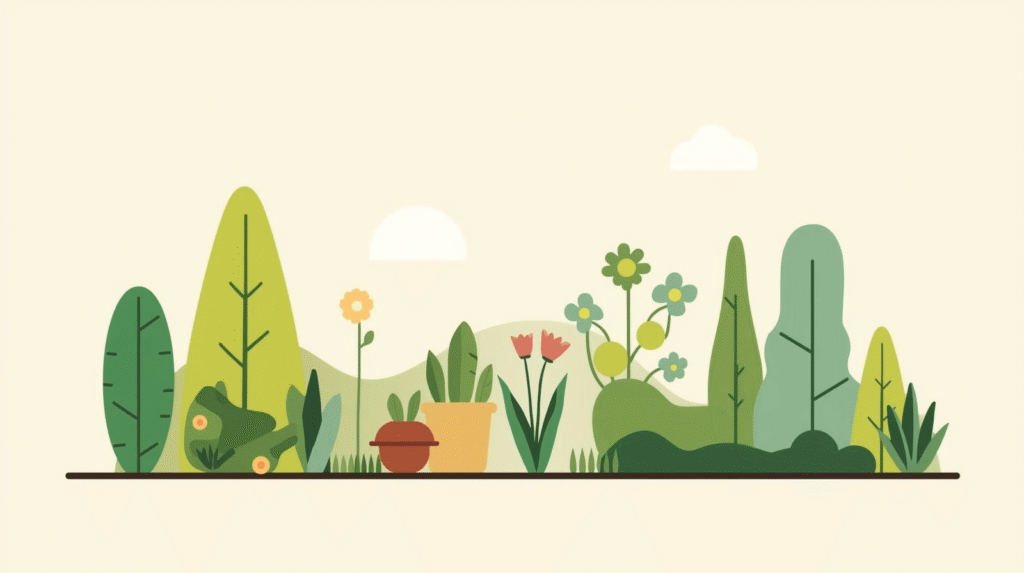
ここまで、「職場で喋らなくなった人」に起きている背景・安全な見分け方・適切な接し方・相談すべきライン・あなた自身を守るセルフケアまでを整理してきました。
結論として最も大切なのは “相手の沈黙をすべて自分の問題と結びつけないこと” です。
沈黙の背景は多様で、あなたが原因とは限りません。むしろ、その可能性のほうが低い場合もあります。
本章では、記事を読み終えた読者が安心して次の行動に進めるよう、要点の再掲とFAQをまとめています。
本記事で伝えた重要ポイント
- 沈黙は必ずしも「拒絶」ではない。
心理・人間関係・忙しさ・性格など、複数の要因が絡む。 - 相手の様子を“決めつけない”ことが安全。
厚労省のメンタルヘルス資料でも、状況の観察が重要とされている。 - 距離感の基準は“相手の負担を増やさないこと”。
無理に理由を聞かない、短い声かけ、見守り姿勢が役立つ。 - あなた自身の心を守る選択肢を持つ。
心理的距離、環境調整、早めの相談、公的窓口の利用など。
よくある質問(FAQ)
Q1:無視されている気がするのは気のせい?
必ずしも「無視」ではない可能性があります。
ストレス・忙しさ・心の疲れなど、相手の内側の要因で沈黙しているケースが多く、厚労省の資料でも“関わりの減少は不調のサイン”とされています。
相手の事情をすべて自分に結びつけず、まずは行動の変化を冷静に観察してみましょう。
Q2:話しかけるタイミングはどう決めればいい?
「相手の余裕があるかどうか」を基準に判断するのがおすすめです。
疲れている表情・反応が遅い・作業に深く集中しているなどのサインがある場合は、踏み込まないほうが安全です。
声をかける際は、一言で済む短い言葉を選ぶと負担を与えにくくなります。
Q3:距離を置かれた理由を直接聞いてもいい?
基本的には、急に距離を置かれた理由を“問い詰める”のは逆効果になりやすいです。
相手が整理できていない段階では、質問そのものがストレスになります。
ただし、業務に支障が出ている場合は、上司や人事など第三者を介して状況を整える方法もあります。
困った時は総合労働相談コーナーの利用も選択肢です(参考:厚労省 総合労働相談コーナー)。
職場で喋らなくなった人に、あなたが振り回されないために
私自身、職場で急に静かになる人に振り回されて、必要以上に疲れたことがあります。
「自分のせいでは?」と考えて落ち込んだ日もありましたが、沈黙の理由は人それぞれであり、自分ではどうにもできない領域があることを知ってから、気持ちがとても軽くなりました。
この記事を読んでくださったあなたにも、必要以上に背負い込まないでほしいです。
あなたが悪いとは限りませんし、むしろ“あなた自身を守ること”のほうが大切です。
焦らず、ゆっくりと、できる範囲の行動から整えてみてください。

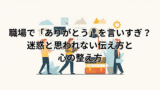
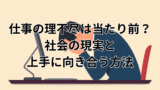
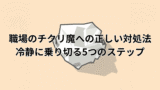
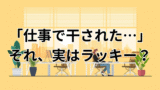
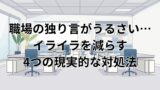
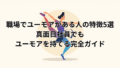
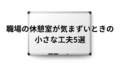
コメント