「仕事にも使うけど、家族の送迎にも使いたい」
車選びで悩みを持つ個人事業主の方は多いのではないでしょうか。
平日は仕事の打ち合わせや現場への移動に使い、
週末は家族と出かける──そんな“兼用スタイル”が一般的になりつつあります。
しかしここで気になるのが、「どの車を選べばいいのか」という点です。
どの車両を選ぶとよいのか、購入・リース・中古のうち、どの車両を保有すればよいのか。
「どこまで経費にできるのか」という点も気になります。
車は高額な資産であり、税務上の扱いを間違えると、
思わぬ課税リスクが発生することもあるでしょう。
この記事では、「仕事とプライベート兼用車」をどう扱えばよいのか、徹底解説します。
最後まで読めば、必要な情報をすべて整理できるでしょう。
この記事でわかること
- おすすめの車種・選び方
- 購入・リース・中古の比較
- 仕事とプライベートを兼用した車の扱い方(経費・税務)
- 節税・保険・トラブル対策まで網羅

仕事と家庭、どちらの時間も大切にしたい──。
そんな個人事業主にとって、兼用車は“働き方と暮らし方”のバランスを取るための重要なツールです。
経費処理を正しく理解すれば、安心してビジネスにもプライベートにも使えるでしょう。
※記事に掲載する情報は、筆者が調べた国税庁のサイトや法律などを元に掲載しています。
しかし、筆者は専門家ではないため情報が誤っている可能性もあります。
あらかじめご了承ください。
仕事とプライベートを両立できる兼用車の選び方|おすすめ車種と失敗しないポイント
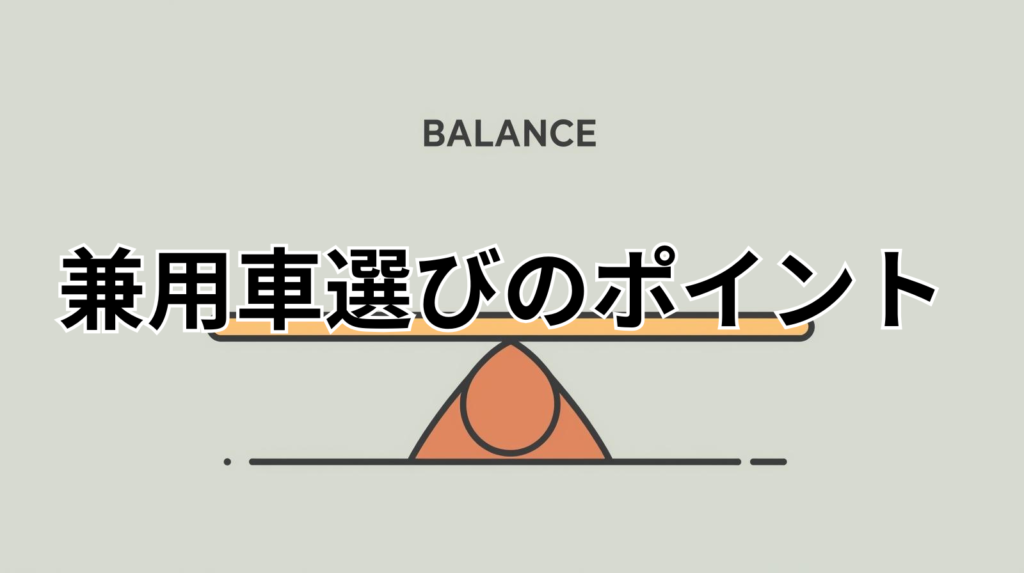
「仕事でも家庭でも使える車」を探すとき、
注目すべきは“スペック”よりもバランスです。
この章では、兼用車に向く車種のタイプや、
選び方のチェックポイント、そして実際の利用者の質問傾向まで整理していきます。
この章でわかること
- 兼用車に向いている車種の特徴
- 燃費・積載・安全性・快適性のバランス
- 維持費と節税の観点から見る選び方
兼用車に向くタイプの車両
兼用車として人気が高いのは、次の3タイプです。
| タイプ | 主な車種 | 特徴 |
|---|---|---|
| コンパクトミニバン | セレナ/ステップワゴン | 荷室と居住性のバランスが良く、業務・家族兼用に最適 |
| 軽バン | エブリイ/ハイゼットカーゴ | 維持費が安く、都市部の現場・配達に強い |
| SUV系 | ライズ/ヴェゼル | デザイン性と走破性が高く、ビジネスイメージも良い |
仕事では荷物を積み、休日は家族で遠出。
この2つを両立できるのが、ミニバン・軽バン・SUVの共通点です。
燃費性能や運転のしやすさを考えると、
個人事業主の兼用車には排気量1.5〜2.0Lクラスの中型車がもっとも人気です。
- ミニバンは「仕事+家族」の両立に最適
- 軽バンは維持費・機動力重視派におすすめ
- SUVは見た目と快適性を両立した選択肢
選び方のチェックリスト
車選びの際は、次の項目を基準に考えると失敗しません。
- 荷室の広さ:仕事道具が積めるか
- 燃費性能:20km/L以上が理想
- シート可動性:2列・3列目の可動や収納性を確認
- 取り回しやすさ:都市部や駐車場で困らないか
- 耐久性と維持費:車検・整備コストを含めたトータルで比較
「業務と家庭のバランス」を意識することで、
無駄な維持費や車両の使い分けコストを抑えられます。
- 荷室・燃費・可動性の3点が重要
- 維持費込みでのコスト比較を忘れない
- 都市部ではコンパクトな車体が有利
Yahoo!知恵袋で多い質問傾向
Yahoo!知恵袋では、「仕事と家庭の兼用車」に関する質問が増えています。
主な傾向としては次の通りです。
- 「ハイエースは維持費が高いが経費に有利?」
- 「どの車種が節税効果が高い?」
これらの質問に共通する答えは、
「業務利用割合(家事按分)を明確にすれば問題ない」ということです。
車種よりも、“どう記録を残すか”が重要といえます。
家事按分や節税についても後ほど詳しく解説しますので、最後まで見ていってください。
- 経費にできるかどうかは按分と記録次第
- 高額車でも、正しい記録があれば節税可能

筆者は車を選ぶ際、快適性を重視しました。
長く乗るほど、日常使いの快適さがストレスを減らします。
税制やコストに加え、乗りやすさもも選定基準のひとつにしてみてください。
仕事・プライベート兼用車の購入・リース・中古比較|経費・節税・維持費を徹底比較
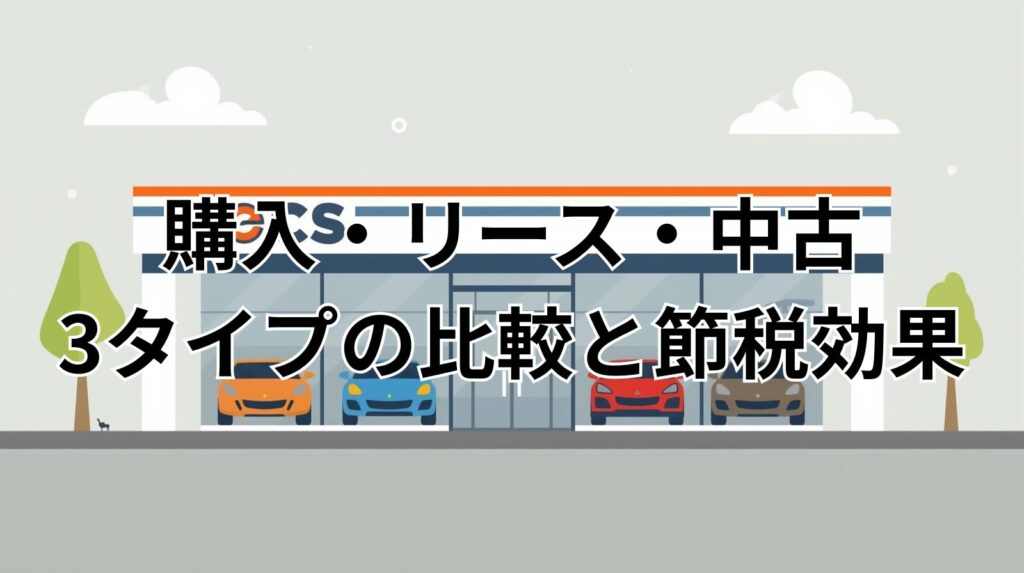
車を仕事で使う場合、「購入・リース・中古購入」のどれが一番お得なのか?
この章では、それぞれの経費処理の違いと節税効果を比較し、
あなたの事業スタイルに合った選択を見つけることを目的とします。
この章でわかること
- 契約形態による経費・節税の違い
- 初期費用・年間維持費・税制上の優位性の比較
- 個人事業主が選ぶべき最適な方法
3タイプの比較表
購入・リース・中古購入について、費用や節税効果等の面で比較して表にまとめました。
比較表(※)
| 項目 | 購入 | リース | 中古購入 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 高い(頭金・税金・登録費用) | 低い(契約時のみ) | 低〜中(車両による) |
| 経費化 | 減価償却で分割 | 全額経費化可 | 短期償却可能 |
| 節税効果 | 徐々に発生 | 即時反映 | 年数短縮で高い |
| 所有権 | 自分 | リース会社 | 自分 |
| 手間 | 維持管理あり | 手続き簡単 | メンテ必要 |
※参考
- e-Gov 法令検索「所得税法第37条」
- 国税庁「タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし」
- 国税庁「タックスアンサー No.2210 必要経費の知識」
- 国税庁「タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数」
- 国税庁「タックスアンサー No.5704 所有権移転外リース取引」
- 国税庁「家事関連費(第1号関係)」
- 国税庁「減価償却資産の償却率表」
- 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
- 現金購入は長期的に安定した資産管理が可能。
- リースは経理処理の手間がなく、初期費用を抑えたい個人事業主向き。
- 中古購入は減価償却期間が短く、節税効果を早く得たい人に最適。
購入型の特徴と減価償却
購入型の最大の特徴は、車両が資産になること。
ただし、税務上は購入費を一括で経費にできず、「減価償却」で数年に分けて計上します。
定額法と定率法の2種類がありますが、個人事業主の場合は原則として定額法です。
(例:300万円の普通車を購入 → 年間約50万円ずつ6年間で償却)(※)
中古車の場合、法定耐用年数から経過年数を引いて再計算できます。
たとえば4年落ちの車なら、耐用年数は約2年。
つまり、2年間で全額経費化できるという強みがあります。(※)
※参考
- e-Gov 法令検索「所得税法49条1項」
- e-Gov 法令検索「所得税法施行令第125条」
- e-Gov 法令検索「所得税法施行令第120条の2」
- e-Gov 法令検索「所得税法施行令第6条」
- 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
- 国税庁「タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし」
- 国税庁「タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数」
- 車は資産扱いとなり、減価償却で分割経費化
- 定額法が原則(個人事業主)
- 中古車は短期償却でき、節税効果が早い
リース型の特徴と注意点
カーリースは、契約した期間中のリース料を全額経費にできる(※)のが最大のメリットです。
減価償却や資産計上の手間がなく、毎月の経費として処理できます。
ただし、注意点もあります。
- 契約期間中の走行距離制限
- 中途解約が原則できない
- 契約終了時に残価精算が発生することも
とはいえ、資金繰りを安定させたい個人事業主や、事務処理を簡略化したい人には最適です。
※参考
- e-Gov 法令検索「所得税法第37条」
- 国税庁「家事関連費(第1号関係)」
ポイントまとめ
- 毎月の支払いを全額経費にできる
- 減価償却不要で手間が少ない
- 契約条件(距離・期間)に注意
中古車・ミニバンが選ばれる理由
中古ミニバンは、仕事+家庭の兼用に最も適しています。
理由は以下の3点です。
- 初期費用が抑えられる
- 減価償却が短期で完了する(※)
- 広い荷室で仕事道具も家族の荷物も載せられる
※参考
- 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
- 国税庁「タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし」
- 国税庁「タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数」
実際、ラインアップ社やガリバーなどの中古車専門店では、
ステップワゴン・セレナ・エスティマなどが「兼用車ランキング」上位に入っています。
信頼できる専門店を選べば、納車前整備や保証・代車対応など、業務にも支障をきたしません。
ポイントまとめ
- 中古車はコスパと節税効果が高い
- ミニバン系は仕事と家庭の両立に最適
- 整備・保証付きの専門店を選ぶと安心

筆者の経験でも、リースの手軽さと中古車のコスパはどちらも魅力的。
「初期費用を抑えたいならリース」「短期で節税を狙うなら中古」と覚えておくと判断しやすいです。
仕事とプライベートの兼用車の経費処理と家事按分の考え方
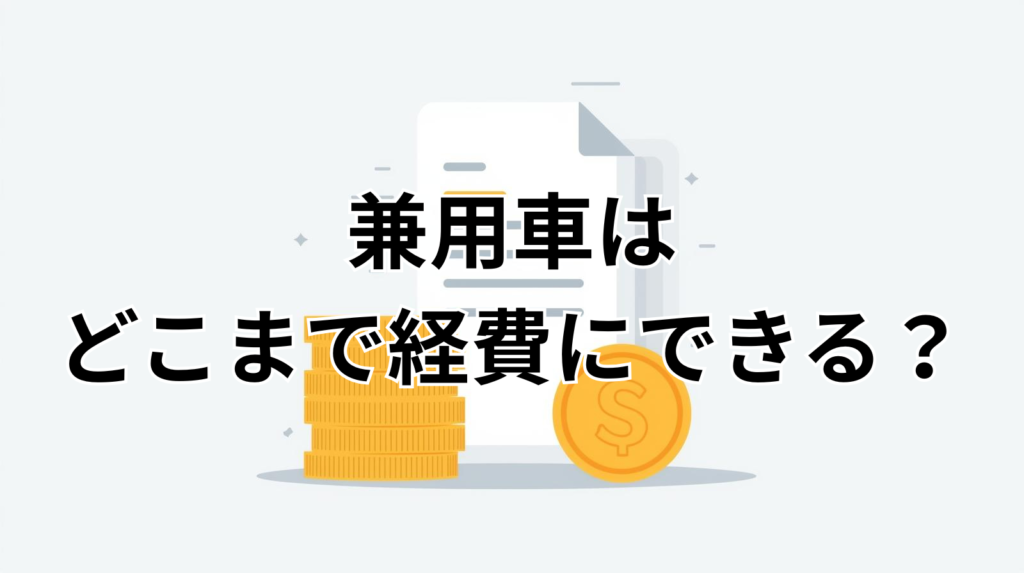
仕事とプライベートのどちらにも使う「兼用車」。
多くの個人事業主が気になるのが、「どこまで経費にしてよいのか」という点です。
この章では、税務上の扱い方から、経費にできる範囲、
家事按分や記録の残し方までをわかりやすく整理します。
ここを理解しておくことで、安心して車をビジネスにもプライベートにも使えるようになります。
この章でわかること
- 「完全業務用」と「兼用車」の違い
- 家事按分の考え方と、税務署に説明できる記録方法
- 経費になる費用・ならない費用の線引き
兼用車の定義と税務上の扱い
「兼用車」とは、仕事とプライベートの両方で使用する車のこと。
税務上は「完全業務用」と異なり、使用割合に応じて経費化する必要があります。
このとき使われるのが「家事按分(かじあんぶん)」という考え方です。
月間の走行距離が1,000kmで、そのうち400kmが仕事利用なら、経費にできるのは40%分です。
家事按分を行う際には、根拠を示す記録が必須。
走行メーターの記録、訪問先リスト、Googleマップ履歴など、
業務使用を数字で説明できる資料を残しておきましょう。
※参考:国税庁「減価償却資産の償却率表」
- 「兼用車」は業務使用割合に応じて経費化
- 家事按分(距離・日数・目的)で算出
- 記録を残すことで税務署への説明が容易
経費にできる主な項目
仕事とプライベートを兼ねて車を使う場合でも、業務に直接関係する支出は経費として認められます。
主な経費項目は以下のとおりです。
- ガソリン代(業務での走行分)
- 高速道路料金・有料道路代
- 駐車場代(業務目的地での使用)
- 車検・定期整備・修理費用
- 自動車保険料(業務使用特約を含む)
- 自動車税・重量税
- 洗車代(業務使用部分に応じた按分)
- カーナビ・ドラレコなど、業務遂行上必要な機器費用
※参考
- 国税庁「タックスアンサー No.2210 必要経費の知識」
- 国税庁「家事関連費(第1号関係)」
- 国税庁「タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし」
さらに、車両購入費用は減価償却で分割して経費計上します。
国税庁の基準によれば、普通車は6年、軽自動車は4年、トラックは3年が目安です。
※参考
- 国税庁「減価償却資産の償却率表」
- 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
- 維持費・保険・税金は業務割合で按分して経費化
- 車両本体は減価償却で分割処理
- 領収書・明細書をすべて保管
経費にならないケース
仕事とプライベートを兼用していても、次のような支出は必要経費として認められません。
業務上直接必要な部分のみが必要経費になり、私用が中心・按分根拠が不十分な場合は否認されます。
該当しやすいNG
- 家族の送迎・買い物・レジャーなど、明らかに私用目的のガソリン代・駐車場代・高速代
- 業務との関連が説明できないカーナビ、ドライブレコーダー、内外装カスタム費用
- 交通違反金(反則金・罰金)や延滞金・反則金に付随する費用(制裁金は経費不可)
- 按分根拠の記録がないのに「なんとなく◯割を経費」など、合理的な計算根拠を欠く計上
- 契約・名義が事業と無関係(例:別居親族名義の車を事業車として計上、事業実態と乖離)
- 白色申告で業務利用がごくわずかかつ記録なし(家事関連費として全額否認されやすい)
「これは経費?」の判断早見表
| ケース | 取り扱い | 理由 | 対応策 |
|---|---|---|---|
| 取引先訪問の高速料金・駐車場代 | ◯(経費) | 業務遂行上の直接必要費 | 行き先・目的を走行ログや領収書に記載 |
| 家族ドライブのガソリン代 | ×(経費不可) | 私用目的(家事費) | 業務と私用を走行距離等で分けて記録 |
| 車検・保険料(兼用車) | △(按分で経費) | 家事関連費に該当 | 「業務走行距離÷総走行距離」で按分 |
| 交通違反金(反則金・罰金) | ×(経費不可) | 制裁金は必要経費にならない | 経費計上せず、私費処理 |
| カーナビ・ドラレコ | △(業務関連性が明確なら可) | 業務必要性の立証が前提 | 導入目的・業務使用状況をメモ化 |
※参考・根拠
- 国税庁「タックスアンサー No.2210 必要経費の知識」
- 国税庁「家事関連費(第1号関係)」
- 国税庁「タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし」
- プライベート利用が中心の支出は経費にならない
- 按分の根拠(走行距離や記録)がないと否認されやすい
- 白色申告では業務利用50%未満は経費化できない

経費にできる・できないの判断は「どれだけ業務として使っているか」。
日常的にメモや走行記録を残すだけで、節税効果と安心感は格段に高まります。
仕事・プライベート兼用車の保険・税金・維持費ルールまとめ
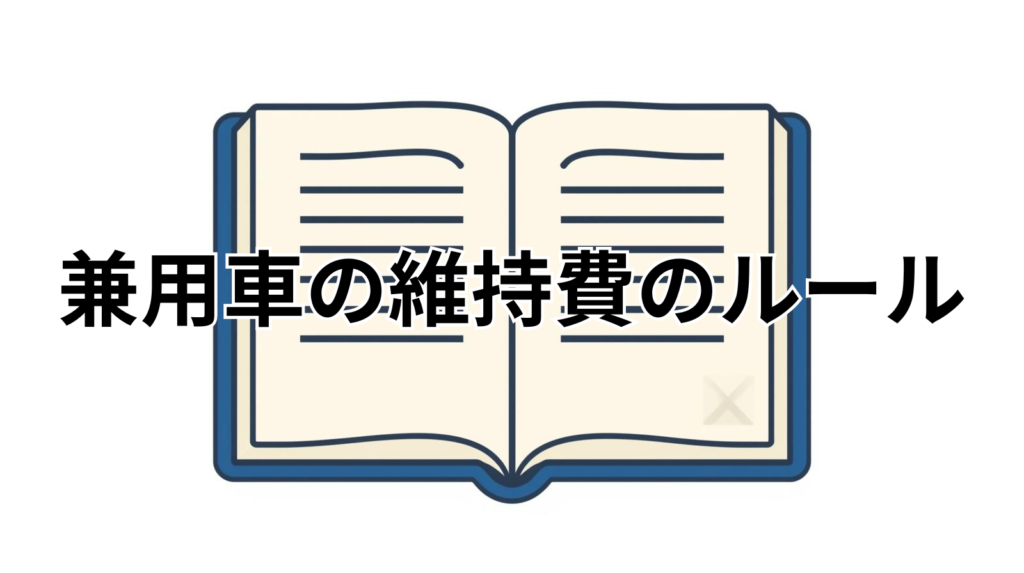
車を「仕事兼用」で使うときに見落としがちなのが、保険と税金の扱い方です。
契約を間違えると、事故時の補償が受けられなかったり、経費処理が否認されるケースもあります。
ここでは、個人事業主が押さえておくべき維持費のルールと、
税務上の注意点を整理します。
この章でわかること
- 業務使用特約の仕組みと重要性
- 税金・保険料の経費化のコツ
- 車検や維持費を見える化する方法
業務使用特約の確認
「自動車保険」は、契約時に設定する使用目的の区分によって補償内容が異なります。
プライベート利用(「日常・レジャー使用」など)のまま仕事に車を使い、
業務中に事故を起こした場合、契約条件によっては補償の対象外となることがあります。
ソニー損保(※)によると、
自動車保険では主に以下の3区分が設定されています。
- 業務使用:営業・配達・訪問など、業務で車を頻繁に使う場合
- 通勤使用:通勤で使用するが、業務にはほとんど使わない場合
- 日常・レジャー使用:週末の買い物や家族の送迎など、私用が中心の場合
※参考:ソニー損保「自動車保険における車の「使用目的」とは?保険料への影響と選ぶ基準をFPが解説」
なお、「業務使用」の判断基準は、
損害保険会社ごとの引受基準によって異なります。
業務での使用頻度が高い場合は、
契約時に「業務使用特約」や「使用目的の変更」を行うことで、
業務中の移動や取引先訪問なども補償対象になります。
この手続きを怠ると、事故時に保険金が支払われないリスクがあるため注意が必要です。
- プライベート契約のまま業務利用すると補償外になる可能性がある
- 業務利用の割合が高い場合は「業務使用」区分や特約への変更が必要
- 契約内容を見直すことで、事故時の補償リスクを防げる
税金・保険料を正しく経費化するコツ
車にかかる主な固定費は以下の通りです。
- 自動車税
- 重量税
- 自動車保険料
- 駐車場代
これらはすべて業務使用割合で按分して経費計上します。
「業務利用60%」の場合は、各費用の60%を経費にできます。
駐車場を事務所名義で契約すれば、
支払いの全額を経費処理できるため、節税効果も高まるでしょう。
※参考
- 国税庁「タックスアンサー No.2210 必要経費の知識」
- 国税庁「家事関連費(第1号関係)」
- 保険料・税金・駐車場代は業務割合で按分
- 駐車場を事務所名義にすると処理が簡単
- 経費処理時は支払先と領収書を必ず保管
車検周期・維持コストを見える化
兼用車は、維持コストを見える化しておくと、
節税と家計管理の両面でメリットがあります。
| 車種区分 | 車検周期(※) | 年間維持費(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 軽バン/軽自動車 | 2年ごと | 約20〜30万円 | 自動車税・保険が安い |
| ミニバン・SUV | 2年ごと | 約30〜40万円 | 家族利用も多くバランス型 |
| 貨物登録車(商用) | 1年ごと | 約40〜50万円 | 事業専用車扱いで点検多め |
仕事中心で使うなら、貨物登録車(商用車)にして経費化率を上げる方法もあります。
ただし、用途変更の手続きや保険契約の再設定が必要になるため、
安易に登録区分を変えるのは避けましょう。
※参考:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「自動車検査証の有効期間」
- 車検周期は車種によって異なる
- 維持費を年単位で把握して予算化
- 商用登録は経費率が上がるが手続き注意

保険や税金は“地味”な部分ですが、最も差が出るポイントです。
特約や名義の設定を見直すだけで、毎年数万円単位でコストが変わります。
一度専門家(税理士・保険代理店)に相談しておくのもおすすめです。
兼用車で節税する方法|仕事・プライベート兼用車の経費計上の実例
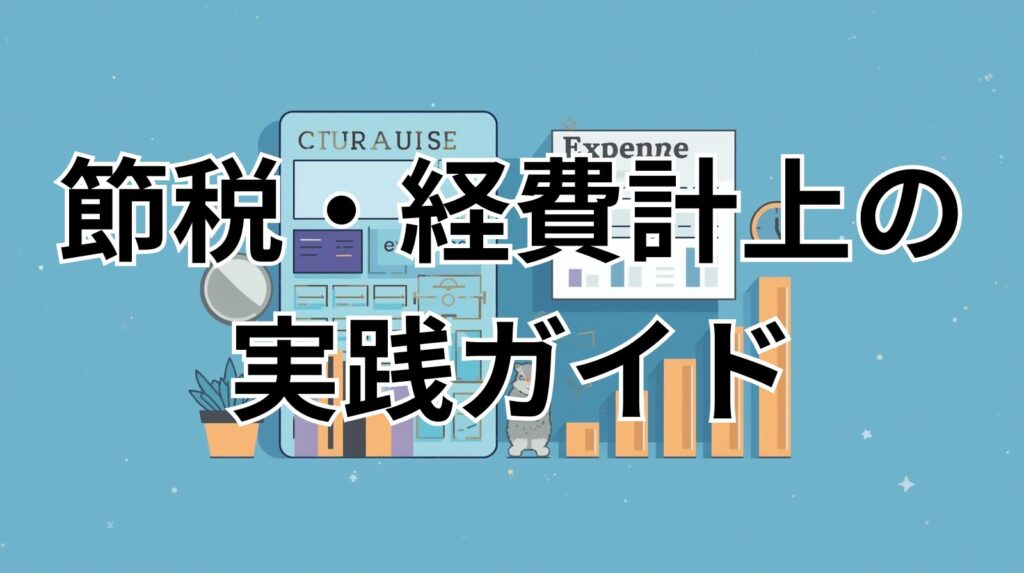
理論を理解しても、「実際にどう計算すればいいの?」と悩む人は多いでしょう。
この章では、実際の金額や走行割合を使って、
個人事業主がどのように経費を算出し、節税を実現できるのかを具体的に紹介します。
この章でわかること
- 減価償却・家事按分・経費区分の具体的な計算例
- 青色申告・白色申告での違い
- 節税効果を最大化する実践ポイント
減価償却の実例
たとえば300万円の普通車を購入した場合、
耐用年数6年(国税庁の耐用年数表による)を基準に、
毎年50万円ずつ経費として計上できます。
もし中古車を購入した場合、耐用年数は「6年 − 経過年数 × 0.2」で再計算されます。
4年落ちの車なら、耐用年数は約2年となり、
年150万円を2年間で償却できる計算です。
実例の方法を使うと、早期に経費化が進み、
開業初期や利益が出始めた時期の節税効果が高まります。
※参考
- 国税庁「タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数」
- 国税庁「タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし」
- 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
- 新車は6年、中古は短期償却で節税効果が高い
- 減価償却を活用すれば高額支出を分散できる
- 開業初期の利益調整にも有効
家事按分の実務
仕事とプライベートの兼用車は、「家事按分」によって経費割合を決めます。
基本式は次の通りです。
業務使用割合 = 業務走行距離 ÷ 総走行距離
たとえば、年間10,000km走行のうち、
業務利用が6,000kmであれば、経費割合は60%となります。
この数値をもとに、ガソリン代・保険料・税金などを按分します。
走行距離の記録はメーター記録やアプリ管理でもOK。
Excelなどで月単位にまとめておくと、税務署への説明もスムーズです。
※参考:国税庁「家事関連費(第1号関係)」
- 「業務走行距離 ÷ 総走行距離」で割合を算出
- メーター記録やアプリで走行ログを管理
- 証拠を残しておくと税務署にも説明しやすい
青色申告・白色申告での違い
経費処理の自由度は、申告区分によって異なります。(※)
| 区分 | 経費按分の扱い | 節税効果 | 確定申告時の優遇 |
|---|---|---|---|
| 青色申告 | 50%未満でも家事按分可能 | 高い | 青色申告特別控除(最大65万円)あり |
| 白色申告 | 業務利用が50%以上でないと経費化不可 | 低い | 控除・節税制度が少ない |
青色申告は手間がかかりますが、
節税面では圧倒的に有利です。
特に兼用車を持つ個人事業主は、青色申告+家事按分+減価償却を組み合わせることで、
年間10〜30万円以上の節税も十分に可能です。
※参考
- 国税庁「家事関連費(第1号関係)」
- 国税庁「タックスアンサーNo.2072 青色申告特別控除」
- 青色申告は按分自由度が高く節税効果も大きい
- 白色申告は50%以上業務使用が条件
- 兼用車を持つなら青色申告が圧倒的に有利

私は、経費処理で最も大切なのは「記録を残すこと」だと考えています。
走行距離やガソリン代の領収書をきちんと保管しておけば、後からでも業務利用の根拠を明確に説明できるからです。
日々の小さな記録が、安心して節税を続けるための最大の備えになります。
仕事とプライベートの兼用車について、よくある質問(FAQ)
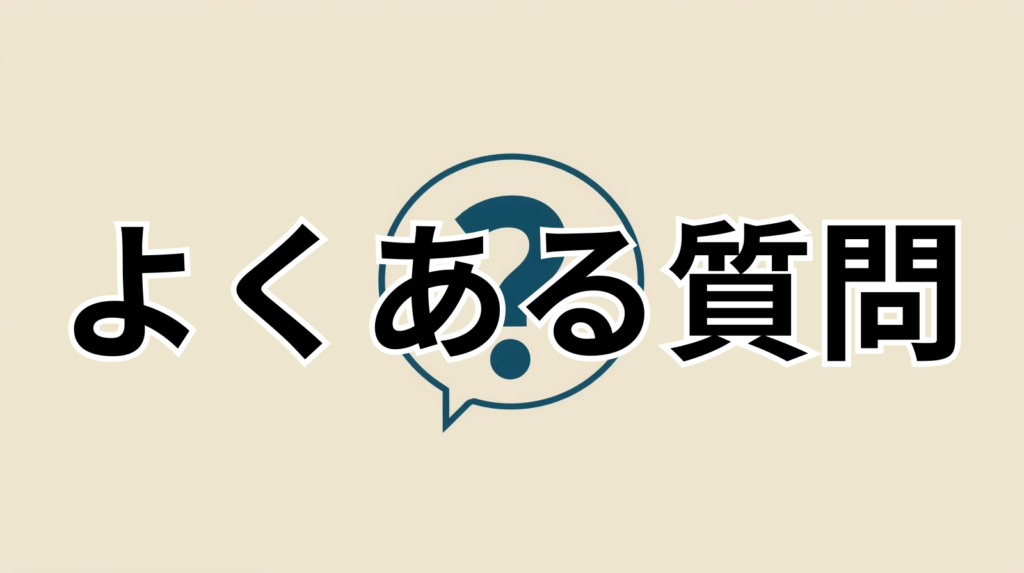
ここでは、「仕事とプライベート兼用車」に関して読者から特に多い質問をまとめました。
実際に税理士が回答している内容をもとに、ポイントをわかりやすく整理しています。
この記事でわかること
- 仕事と家庭で車を共有する際の経費ルール
- ローンやリースに関する税務上の扱い
- 解約・変更時の注意点
Q1. 車を家族も使う場合、経費にできますか?
→ 可能です。
ただし「業務使用割合」に応じて按分する必要があります。
たとえば、年間走行距離10,000kmのうち、業務で4,000kmなら経費割合は40%。
その40%分のガソリン代・保険料・税金を経費にできます。
記録があれば、家族が乗る車でも税務署に説明可能です。
※参考
- 国税庁「タックスアンサー No.2210 必要経費の知識」
- 国税庁「家事関連費(第1号関係)」
- 家族利用でも割合を明確にすればOK
- 走行距離や使用目的の記録が必須
- 税務署は「記録の有無」を最重視
Q2. 車のローンは経費になりますか?
→ 元金部分は経費になりません。
経費にできるのは「利息部分」だけです。
ただし、車の本体価格は減価償却によって年単位で経費化できます。
たとえば300万円の車を6年償却なら、毎年50万円を経費にできます。
ローンの利息は金利によって異なりますが、支払利息の明細を保管しておくことが重要です。
※参考
- e-Gov 法令検索「所得税法第37条」
- 国税庁「タックスアンサー No.2210 必要経費の知識」
- 国税庁「タックスアンサー No.3264 借入金の利子が取得費になるとき」
- 元金は資産、利息のみ経費化可能
- 減価償却と併用して処理
- 支払明細は領収書と一緒に保管
Q3. リース契約中に解約したらどうなりますか?
→ 違約金・残価精算が発生します。
契約期間の途中で解約すると、リース会社との残り期間分の費用精算が必要です。
残価設定型契約では、返却時に「車の査定額」が残価を下回ると差額負担が発生します。
そのため、契約前に走行距離・契約期間・残価設定をしっかり確認しておきましょう。
- 中途解約には違約金・残価精算が発生
- 契約期間と走行距離を事前確認
- 返却時の査定額にも注意

よくある誤解のひとつが、「家族が乗る車は経費にできない」という思い込みです。
実際には、記録と割合が明確であれば問題ありません。
不安な場合は、税理士や会計ソフトの相談機能を活用すると安心です。
まとめ:仕事とプライベートを両立できる兼用車でムダなく節税しよう

ここまで、仕事とプライベートを兼ねる車の扱い方を解説してきました。
兼用車は「家事按分」「減価償却」「記録管理」という3つの要素を押さえることで、
安心して節税しながら効率的に使うことができます。
購入・リース・中古のいずれを選ぶにしても、
「経費化できる根拠を残す」ことが最大のポイントです。
特に、走行距離・業務内容・使用割合を月単位で記録しておくことで、
税務署への説明もスムーズに行えます。
保険や駐車場の契約名義を見直すだけでも、
年間数万円のコスト削減につながるケースもあります。
「どこまでが経費か」を知っておくことは、リスク回避と節税の両立につながるでしょう。
まとめポイント
- 仕事とプライベート兼用車の経費処理の基本
- 減価償却・家事按分を活用した節税方法
- 購入・リース・中古それぞれのメリットと注意点
- 保険・税金の見直しでコスト最適化
- 兼用車は「家事按分+減価償却+記録管理」が節税の三本柱
- 購入・リース・中古はライフスタイルに合わせて選択
- 中古ミニバンはコスパと汎用性の両立で人気
- 保険・税金も“業務割合”に合わせて調整
- 記録を残すことで税務リスクをゼロに近づける

仕事でも家族でも使う車は、どうしても「どこまで経費にできるんだろう?」と迷うものですよね。
でも、走行距離やガソリン代などをきちんと記録しておくだけで、経費処理の不安はぐっと減ります。
無理のない範囲で記録を続ければ、節税もカーライフも、どちらも安心して楽しめますよ。
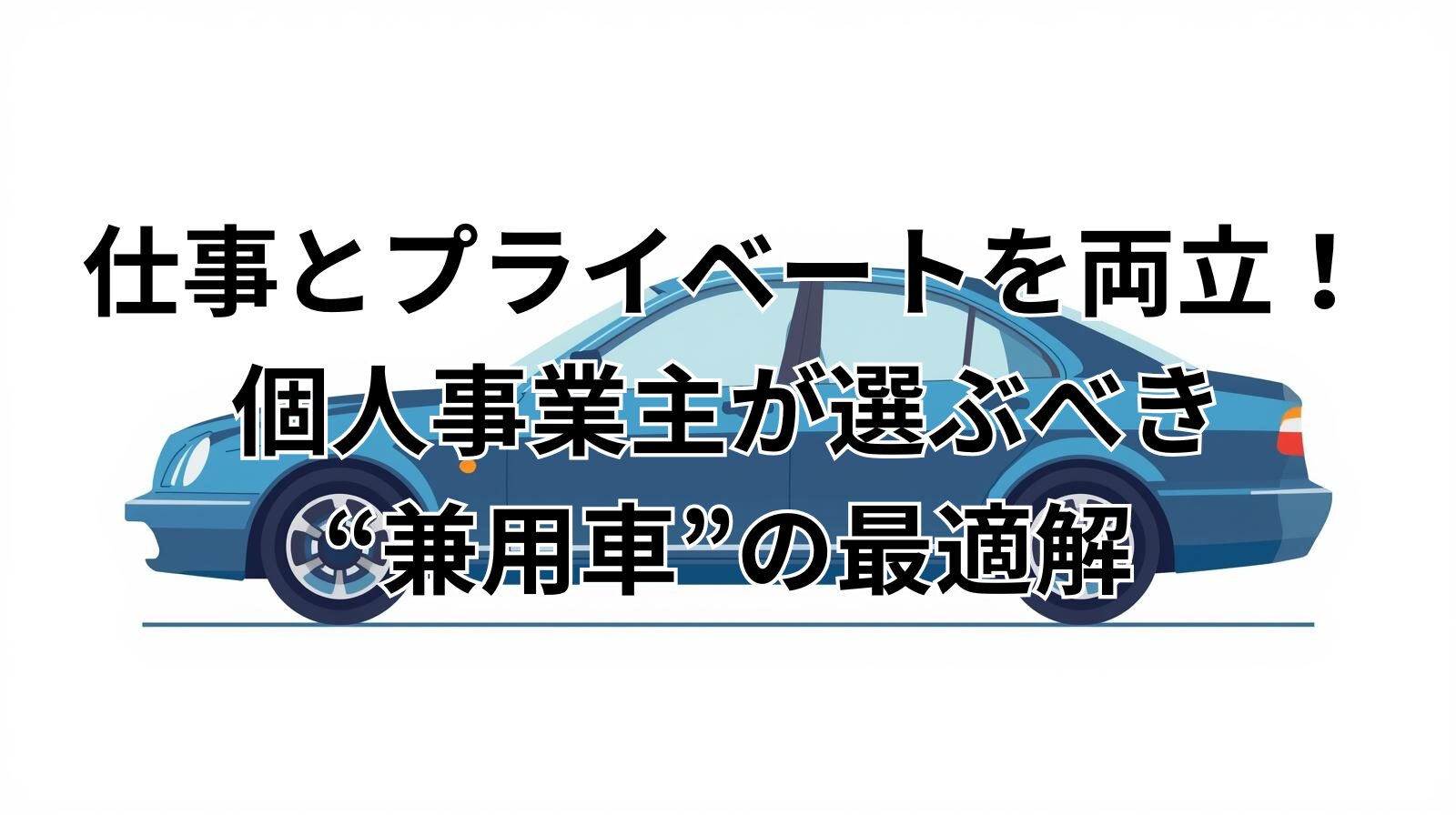
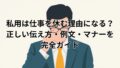

コメント