職場のずるい人にイライラしてしまう瞬間は、誰にでもあります。
放っておくとストレスが積もり、仕事への意欲まで奪われてしまうことも。
本記事では、職場のずるい人に振り回されないための考え方と対処法を、心理的な背景から具体的な行動術まで体系的に解説します。
感情の整理・距離の取り方・心を守る習慣までを一つの記事でまとめました。
読後には「もうイライラに支配されない自分」に近づけるでしょう。

私自身も、ずるい人に悩み「なんで自分だけ…」と感じた時期がありました。
けれど、相手を変えるより“自分を守る視点”を持つことで、驚くほど心が軽くなったのです。
この記事が、あなたが自分のペースで働ける一歩につながれば嬉しいです。
- ずるい人の行動の裏には「自己防衛心理」がある
- 感情を抑えるのではなく「距離を取る」ことで心を守る
- 職場ストレスの主因は「人間関係」——我慢せず共有・相談を
- イライラを減らすには「日々の習慣とメンタルケア」が鍵
職場のずるい人とは?イライラする原因と特徴を解説

職場にいる「ずるい人」は、周囲の努力を利用して自分だけ得をするように見える存在です。
この章では、そんなずるい人の特徴や心理背景、そしてなぜ私たちはそこまで強くイライラを感じてしまうのかを整理します。
- ずるい人に共通する特徴と行動パターン
- なぜずるい人にイライラしてしまうのか
- 職場ストレスの主因は人間関係
ずるい人に共通する特徴と行動パターン
職場のずるい人に共通するのは、「自分の損得を優先し、責任を取らない」という傾向です。
成果が出たときは自分の手柄にし、失敗すると他人のせいにする。報告や相談を後回しにして、周囲に混乱を生むこともあります。
こうした行動の背景には、「評価されたい」「失敗を恐れたくない」という防衛心理が働いていると考えられます。
自己保身型の行動パターンで、本人に悪意がなくても他人に不公平感を与えることが多いのです。
実際の職場では、以下のようなタイプが多く見られます。
| タイプ | 行動の特徴 | 周囲への影響 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 責任回避型 | ミスを他人に押しつける | 信頼関係を損ねる | 証拠を残すことが有効 |
| 手柄横取り型 | 成果を自分のものにする | モチベーション低下を招く | チームで共有する文化を作る |
| ゴマすり型 | 上司だけに愛想がよい | 公平性が欠ける職場風土に | 評価基準を明確にすることが重要 |
| 自己優先型 | 周囲の状況より自分の予定を優先 | チームワークが乱れる | 業務ルールを可視化して防ぐ |
「ずるい人」は意図的というよりも、評価への不安や自己防衛本能から行動していることが多いです。
感情的に反発する前に「なぜそうなるのか」を冷静に見極めることで、職場のずるい人にイライラせずに済むでしょう。
- 自分の損得を優先する行動が「ずるい」と見なされやすい
- 背景には「評価されたい」「責められたくない」という心理がある
- 対応の第一歩は「感情よりも構造を理解する」こと

私も以前の職場で、同僚に上司からの評価を横取りされたように感じたことがあります。
当時は怒りと悔しさでいっぱいでしたが、冷静に考えると、相手は“自分をよく見せること”に必死だっただけなのかもしれません。
相手の策略を理解した瞬間、ようやく感情よりも距離を取る冷静さを持てるようになりました。
なぜずるい人にイライラしてしまうのか
ずるい人にイライラする理由は、「公平さが損なわれた」と脳が感じるためです。
人は社会的動物であり、公平・公正の感覚が働かない状況では、怒りやストレスを強く感じます。
たとえば、上司にゴマをすって昇進した人を見たとき、私たちは理屈ではなく感情的に「不当だ」と反応します。
この感情は自然なもので、ストレス反応の一種といわれています。
ストレスを感じたときに心身を守るための対処法として、「距離を取る」「感情を認知する」「事実を整理する」という3ステップが有効です。
怒りを我慢するのではなく、「なぜ自分が怒っているのか」を理解することで、状況を客観的に見られるようになるでしょう。
- 不公平さへの感情は人間の自然な反応
- イライラを抑えるより、まず「認識する」ことが第一歩
- 「距離を取る」「感情を認知する」「事実を整理する」3ステップで対処

ずるい人に怒りを感じること自体は、決して悪いことではありません。
その感情があるからこそ、正義感や公平さを大切にできるのだと思います。
ただ、その怒りに支配されないよう、少し距離を取ることを意識しています。
職場ストレスの主因は人間関係
職場のストレス要因の中でも、最も多くの人が挙げるのが「人間関係の問題」です。
厚生労働省の「こころの耳」によると、仕事でストレスを感じる理由の約4割が「人間関係」とされ、特に上司・同僚との摩擦が多いと報告されています。
(出典:こころの耳「ストレス軽減ノウハウ」)
人間関係のうち、職場のずるい人に悩む人の数も多いと考えられるでしょう。
つまり、自分だけがイライラしているのではなく、全国の多くの労働者が同じ悩みを共有しているのです。
データを知ることで、「自分の感じ方はおかしくない」と安心できる人も多いでしょう。
| 主なストレス要因 | 割合(%) | 出典 |
|---|---|---|
| 職場の人間関係 | 41.3 | 厚労省「こころの耳」 |
| 仕事の量・質 | 33.6 | 同上 |
| 会社の将来性 | 14.5 | 同上 |
職場ストレスの多くが「人間関係」に集中しており、ずるい人の存在もその一部に含まれます。
これは個人の問題ではなく、職場文化全体の課題ともいえるでしょう。
- 職場ストレスの主因は「人間関係」にある
- 自分だけの悩みではなく、多くの人が同じ問題を抱えている
- データを知ることが「安心」と「冷静さ」につながる

公的データを見れば、職場の人間関係に悩まされている人は多いと分かります。
あなたの悩みは、自然なことなのです。
職場のずるい人にイライラしないための考え方と心の整え方

「ずるい人」を変えようとしても、現実的には難しいものです。
この章では、相手を変えるのではなく「自分の心の持ち方を整える」ことで、イライラを減らす方法を解説します。
焦りや怒りを抑えるのではなく、考え方の整理を通じて自分のペースを取り戻せるようになるでしょう。
- 「正義感の罠」から抜け出す|損をしている気持ちの正体
- 相手を変えようとせず「距離を取る」発想へシフト
- 感情を整理する3ステップ(認知→分離→切り替え)
「正義感の罠」から抜け出す|損をしている気持ちの正体
ずるい人にイライラするのは、自分が「正しく行動しているのに報われない」と感じるからです。
この「正義感の罠」に陥ると、相手の行動ばかりが気になり、心が疲れてしまいます。
心理学では「公正世界仮説」という考え方があります。人は「正しく努力すれば報われる」と信じたい生き物であり、その秩序が崩れると強い不快感を覚えるのです。
しかし、現実の職場では努力と評価が必ずしも比例するとは限りません。社会的な評価には運や人間関係も影響します。
私も新人のころ、要領の良い同僚が上司に気に入られ、評価を受けたときに強い不公平感を覚えました。
しかし、私は他人の評価軸ではなく自分の軸で考えることにして、自分が達成したことなどに注目するようにしました。
相手ではなく、自分の成長や目標にエネルギーを向ける方が、長い目で見て確実に報われると、私は考えています。
- 「正しく頑張っているのに報われない」とき、人は強い不快感を覚える
- 公正世界仮説が崩れると、怒りが増す傾向にある
- 相手を責めるより、自分の目的を見つめ直すほうが前進できる

正義感は人を支える力でもあり、同時に自分を縛ることもあります。
ずるい人への怒りは、実は「自分も真面目にやりたい」という気持ちの裏返し。
その思いを大切に、行動の方向を少し変えるだけで気持ちが楽になります。
相手を変えようとせず「距離を取る」発想へシフト
職場のずるい人は、自分の行動を省みない場合が多く、注意しても改善しないことがあります。
そのため、対処のポイントは「相手を変えようとしないこと」。
変えられない他人にエネルギーを使うより、自分の心を守るための距離を取る方が有効です。
心理的距離を取る具体的な方法としては、以下のような工夫があります。
- 仕事上の関わりを必要最低限にする
- 感情的な会話を避け、事実だけを共有する
- SNSや私的な話題を控える
自分を守る距離を取ることは「逃げ」ではありません。むしろ冷静に判断するための戦略的選択です。
他人に合わせることより、自分のペースで働ける状態を優先しましょう。
- 他人を変えるより、自分を守る方が結果的に健全
- 心理的距離を置くことでストレスが軽減される
- 自分のペースを優先する

状況によっては、あえて距離を取ることで関係が安定する場合もあります。
無理に関わろうとせず、冷静な距離感を保つことが、自分と職場の両方を守ることにつながるでしょう。
感情を整理する3ステップ(認知→分離→切り替え)
ずるい人に対して感じる怒りや不満を抑えるのではなく、客観的に整理することが重要です。
心理学的には、次の3ステップが有効だとされています。
| ステップ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 認知 | 「自分はいま怒っている」と自覚する | 感情を客観視する |
| 分離 | 「相手の問題」と「自分の問題」を切り分ける | 過剰な共感を防ぐ |
| 切り替え | 気持ちを別の行動や思考に移す | ストレスを減らす |
このプロセスは「アンガーマネジメント」の基本でもあります。
怒りを押し殺すのではなく、認知して流すことでストレスが蓄積しにくくなるのです。
相手に腹が立ったとき、「この感情は自分を守る反応なんだ」と考えるだけでも冷静さが戻るでしょう。
- 怒りを抑えるのではなく、「認知→分離→切り替え」で整理する
- 感情を認識することでストレスが減少しやすい
- 自分の感情と他人の行動を混同しないことがポイント

感情を言葉にして認識するだけでも、気持ちの整理が進みやすくなります。
「イライラする自分を責めずに受け止めること」から、穏やかに働く一歩が始まります。
職場のずるい人への上手な対処法【イライラを減らす実践編】

「理解」や「考え方の整理」だけでは、現実の職場ストレスは完全には解消できません。
この章では、ずるい人にイライラしないための具体的な行動・対処法を紹介します。
感情ではなく、事実と仕組みで自分を守る姿勢を意識しましょう。
- 直接注意せずに自分を守る立ち回り方
- 上司や同僚と協力してトラブルを防ぐ
- 証拠・記録を残すことで自分を守る(労務リスク対策)
- 相談先・社内外のサポート窓口(こころの耳・労働局など)
直接注意せずに自分を守る立ち回り方
ずるい人に直接注意しても、相手が反発する場合が多く、関係が悪化するリスクがあります。
有効なのが、「注意」ではなく「防御」に意識を置く対応です。
相手が自分の仕事を押しつけてくる場合、曖昧な返事をせず「◯日までに終えられる範囲で対応します」と、具体的に期限や範囲を示すことが大切です。
業務分担をメールやチャットで明文化しておくと、後のトラブル防止にもなります。
心理的にも、「戦うより離れるほうがエネルギーの消耗が少ない」と言われています。
行動心理学の観点からも、相手を変えようとするより“環境を変える”ほうが成功率が高いとされるのです。
- 直接的な注意は逆効果になることが多い
- 範囲・期限を明確にして防御的な立ち回りを
- 書面・メールで記録を残すと安心

私も以前、同僚の頼みを断れずに抱え込み、結果的に自分のミスのように扱われたことがありました。
その経験から、「断る勇気と記録を残す意識」が心の安定を守ると感じています。
上司や同僚と協力してトラブルを防ぐ
ずるい人への対応を個人で抱え込むと、ストレスが限界に達しやすくなります。
一人で戦うのではなく、上司や信頼できる同僚に「状況を共有する」ことが有効です。
業務報告の場で「このタスクの担当を再確認したいのですが」と客観的に話題にするだけでも、周囲に現状を共有できます。
それにより、ずるい人が一方的に主張しづらくなる環境をつくれるでしょう。
厚生労働省の「職場における心の健康づくりのための指針」では、事業者・上司・同僚などが連携して支援することや、労働者が早期に相談しやすい環境を整えることの重要性が示されています。
これにより、職場全体でのストレス軽減や早期対応が促されるのです。
(出典:厚労省「職場における心の健康づくり」)
周囲に相談することは「弱さ」ではなく、「職場の健全性を守る行動」です。
共有の輪を広げることで、ずるい人の行動が抑制される効果も期待できます。
- 一人で抱え込まず、信頼できる上司・同僚と共有する
- 客観的な言葉で状況を説明し、感情的にならない
- 厚労省も「早期共有と相談」を推奨している

以前は「我慢していれば波風が立たない」と思っていましたが、結果的に問題が大きくなったことがあります。
相談することは勇気のある選択であり、職場全体の改善にもつながるでしょう。
証拠・記録を残すことで自分を守る(労務リスク対策)
職場でのトラブルは、記録を残すことが重要です。
ずるい人の行動によって不利益を受けた場合、日時・内容・状況を簡単にメモしておくだけでも、後から自分を守る証拠になります。
責任の押しつけや業務放棄に関する問題は、記録がなければ立証が難しいため注意が必要です。
メールやチャットの履歴を残しておく、業務の進捗を共有フォルダにまとめるなど、日常的に“可視化”を意識することがポイントです。
また、法的なトラブルに発展した場合は、労働局の総合労働相談コーナーが無料で対応してくれます。
(出典:厚生労働省「総合労働相談コーナー」)
記録を残しておけば、職場のずるい人から自分を守れるでしょう。
- トラブル防止には「記録」が最も有効
- メール・日報・共有フォルダを活用
- 公的相談窓口では無料でアドバイスを受けられる

私は「記録なんて大げさ」と思っていましたが、実際に助かったことがあります。
客観的な事実があるだけで、心の負担が軽くなり、安心して行動できるようになりました。
相談先・社内外のサポート窓口(こころの耳・労働局など)
ずるい人との関係で限界を感じたときは、早めに相談することが大切です。
身近な人に話すのが難しい場合は、外部の専門機関を活用しましょう。
代表的な公的サポート窓口は以下の通りです。
| 相談先 | 内容 | 利用方法 | 費用 |
|---|---|---|---|
| こころの耳 相談ダイヤル | 職場のストレス・人間関係に関する相談 | 電話またはメール(24時間対応) | 無料 |
| 労働局 総合労働相談コーナー | 労務・パワハラ・職場環境の相談 | 各都道府県で受付 | 無料 |
| 産業医・社内メンタル相談窓口 | 健康や勤務環境の相談 | 社内専用窓口に連絡 | 無料(勤務先による) |
どの窓口も守秘義務があり、匿名でも相談できます。
早めの相談が、深刻化を防ぐ最大のポイントです。
- 我慢せず、外部機関の相談を早めに活用
- 「こころの耳」や「労働局」は無料で利用可能
- 一人で抱え込まないことが最大の予防策

専門家に話すことで、自分の感じていた違和感や悩みを整理でき、安心感につながるケースもあります。
一人で抱え込まず外部の支援を活用することで、冷静な判断ができるでしょう。
職場のずるい人にイライラしない習慣づくりとメンタルケア

ずるい人に出会うたびにストレスを感じるのは、誰にとっても自然なことです。
しかし、毎回感情に振り回されていては、自分のエネルギーが消耗してしまいます。
この章では、日常の習慣と心のメンテナンスによってイライラを軽減する方法を紹介します。
- アンガーマネジメントで「瞬間の怒り」を制御する
- ストレスを溜めない1日の過ごし方(休息・切り替え法)
- 心理的安全性を高めるセルフチェックリスト
- 限界を感じたら環境を見直す(転職・部署異動も選択肢)
アンガーマネジメントで「瞬間の怒り」を制御する
「ずるい人」にイライラした瞬間、その感情をいかにコントロールするかがカギです。
アンガーマネジメントの基本は、「6秒ルール」と呼ばれる感情のクールダウン法。
人の怒りは最初の6秒が最も強く、そこをやり過ごすと冷静さを取り戻せるといわれています。
怒りを感じた瞬間に「深呼吸を3回する」「一歩後ろに下がる」「紙に感情を書く」といった小さな行動を取るだけで、脳の緊張が和らぐでしょう。
厚生労働省の「こころの耳」でも、感情が高ぶったときは深呼吸や一時的にその場を離れることが有効とされています。
一度距離を置くことで冷静さを取り戻し、ストレス反応を和らげる効果が期待できるのです。
(出典:こころの耳「15分でわかるセルフケア」)
重要なのは、怒りを「抑える」ことではなく「扱う」こと。
感情の存在を認めながらも、行動を選ぶ力を養うことが、心の安定につながります。
- 怒りのピークは最初の6秒間
- 深呼吸や物理的距離を取ると冷静さが戻る
- 感情を「抑える」より「扱う」意識を持つ

私も以前の職場でイライラさせられることがあったため、アンガーマネジメントを実践していました。
「6秒だけ待つ」を意識したことで、衝動的な反応を減らせるようになったのです。
ストレスを溜めない1日の過ごし方(休息・切り替え法)
仕事でストレスを感じた日は、帰宅後の時間の使い方が重要です。
ずるい人の言動を思い出してしまうときは、頭の中で「仕事のスイッチを切る」意識を持ちましょう。
以下のような小さな行動で、心の負担を大きく減らせます。
- 通勤中にお気に入りの音楽を聴く
- 15分だけ散歩する
- スマホを見ずに湯船に浸かる
厚生労働省の「こころの耳」では、
ストレスの予防法として睡眠や運動のほか、趣味に打ち込むこと、なども効果的だと紹介されています。
(出典:こころの耳「15分でわかるセルフケア」)
嫌なことを思い出してしまう時は、仕事のスイッチを切って切り替える習慣を意識しましょう。
- 帰宅後は「仕事のスイッチを切る」習慣を
- 小さな行動でリセットできる
- 趣味に打ち込むことも効果的

私も以前、寝る直前まで仕事のことを考えて眠れませんでした。
しかし、仕事が終わったら完全に気持ちを切り替えることで、家でリラックスできるようになったのです。
心理的安全性を高めるセルフチェックリスト
職場でストレスを感じやすい人ほど、自分を責めやすい傾向があります。
そんなときは、「心理的安全性」という観点から自分の状態を確認してみましょう。
| チェック項目 | 改善のヒント |
|---|---|
| 意見を言うときに緊張する | 信頼できる人と少人数で話してみる |
| ミスを恐れて萎縮する | 完璧を求めず「小さな成功」を意識する |
| 同僚と話すのが億劫 | 雑談から再スタートする |
| 感情を我慢してしまう | 書き出して整理すると落ち着く |
| 頼ることに罪悪感がある | 「相談=信頼の証」と考える |
心理的安全性が下がると、人間関係の摩擦が強く感じられやすくなります。
逆に「話しても大丈夫」と思える関係があると、ずるい人の言動も軽く受け流せるようになります。
職場に限らず、自分の気持ちを吐き出せる場所を一つ持っておくとよいでしょう。
- 心理的安全性の低下がストレスを増幅させる
- チェック項目で自分の状態を可視化する
- 「話せる相手」を持つことが安心感を生む

多くの人が「弱音を見せてはいけない」と感じてしまうことがあります。
しかし、信頼できる人に話すことで気持ちが整理され、心が軽くなる場合も少なくありません。
頼ることは甘えではなく、冷静さを取り戻すための大切な手段のひとつです。
限界を感じたら環境を見直す(転職・部署異動も選択肢)
どれだけ努力しても、環境そのものが合わない場合があります。
もし毎日が苦痛で、心身に不調が出ているなら、「環境を変える」ことも前向きな選択です。
たとえば、社内異動の希望を出す、休職制度を利用する、外部転職エージェントに相談するなど、行動の選択肢を持つだけでも安心感が生まれます。
転職を検討する際は、ハローワークやキャリアコンサルティング制度などの公的サービスも検討してみましょう。
大切なのは「逃げる」ではなく、「より健全に働くための移動」だと捉えることです。
- 限界を感じたら、環境を見直すのも有効
- 異動・転職・休職などの制度を早めに確認
- 公的支援を利用すれば安心して行動できる

私も一度環境を変えたことで、心が驚くほど落ち着きました。
「逃げた」ではなく「自分を守る選択をした」と思えた瞬間、ようやく前向きになれました。
職場のずるい人に振り回されずイライラを手放すまとめ

ここまで、ずるい人の特徴や心理的背景、そしてイライラを減らす考え方と対処法、さらに日常でできるメンタルケアの方法を紹介してきました。
この章では、記事全体の要点を整理しながら、読者が「自分を守りながら穏やかに働く」ための心構えをまとめます。
- この記事で伝えたい3つのポイント
- 自分を守るための「考え方リマインダー」
- よくある質問(FAQ)
- 職場のずるい人にイライラさせられないために
この記事で伝えたい3つのポイント
- 原因理解:ずるい人の行動には防衛心理や不安があると知る
ずるい行動の背景には、評価への不安や自己防衛の心理が隠れています。
相手の行動を「自分への攻撃」と捉えず、心理的背景を理解することで冷静に対応可能です。 - 距離の取り方:心理的な距離を保ち、相手の問題を自分に持ち込まない
必要以上に関わらず、業務上の関係にとどめることが効果的です。「これは相手の課題」と切り分けることで、心の余裕を保てます。 - 行動とケア:記録・共有・相談・休息など、環境と習慣で自分を守る
記録を残し、信頼できる人に共有・相談することで客観的に整理できます。
深呼吸や短い休息など、小さなセルフケアを続けることも効果的です。
自分を守るための「考え方リマインダー」
ずるい人に遭遇したとき、すぐに感情を整理するのは難しいものです。
そんなときのために、心を保つための「考え方リマインダー」を持っておきましょう。
| シーン | 考え方の切り替え例 |
|---|---|
| 手柄を横取りされたとき | 「本当に評価してくれる人は見ている」 |
| 責任を押しつけられたとき | 「自分の誠実さを記録で残そう」 |
| 媚びる人が得していると感じたとき | 「短期的な得より信頼が残る」 |
| 不公平さに怒りを感じたとき | 「自分の行動で変えられる範囲に集中しよう」 |
| 限界を感じたとき | 「助けを求めてもいい、自分を守る選択を」 |
このリマインダーは、自分の軸を取り戻すための小さな支えです。
人間関係に疲れたときほど、自分の内側に目を向ける時間を意識して取りましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 職場のずるい人を無視すると悪化しますか?
A.完全に無視するより、「必要最低限の業務連絡だけ行う」が安全です。
相手の感情を刺激せず、自分の平穏を守る形で関わりを最小化しましょう。
Q2. 上司がずるい場合はどうすれば?
A.記録を残しつつ、同僚や人事に状況を共有することが有効です。
上司への直接的な指摘はリスクが高いため、第三者の介入を前提に動きましょう。
Q3. 我慢しすぎて限界を感じたときの対処法は?
A.休職・異動・転職など、「環境を変える選択肢」を検討してください。
厚労省のこころの耳 相談ダイヤルや労働局相談コーナーでは無料相談も可能です。
職場のずるい人にイライラさせられないために
職場のずるい人に振り回される時間は、本来自分の力を発揮できる時間でもあります。
相手を変えることは難しくても、捉え方や行動を少し変えるだけで、心の消耗は確実に減らせます。
「イライラする自分を責めず、まずは距離を置く」——その一歩が、穏やかに働ける環境を取り戻すきっかけになります。
無理に我慢せず、信頼できる人や専門機関を頼ることも、自分を守る大切な選択です。
- フリーランスがバイトしながら働くコツ|両立を成功させる時間・スキル・思考法
- 【2025年版】転職までのつなぎバイトおすすめランキングTOP5|後悔しない選び方を解説
- 転職のWebテストがボロボロでも受かる?落ちたと思った人が通過する理由と対策
- 転職エージェントを休止したいときの正しい手順|退会との違いと再開のコツを解説
- 職場で「ありがとう」を言いすぎ?|迷惑と思われない伝え方と心の整え方
- 「仕事で干された…」それ、実はラッキー?今すぐ見直したい原因と対処法
- 「勉強したくない…」と思う人へ|資格なしでも続けられる仕事10選
- 仕事の理不尽は当たり前?|社会の現実と上手に向き合う方法
- 仕事の兼務のストレスは「我慢」ではなく「仕組み」で解決しよう|原因と改善策を徹底解説
- 仕事がわからないことだらけの中堅社員が増えている理由と乗り越え方|焦らず前に進むキャリア再設計ガイド

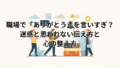

コメント