「仕事を兼務していて、毎日がいっぱいいっぱい」
「責任が重く、ミスを恐れて眠れない」
そんな悩みを抱える人は少なくありません。複数の業務を担うことでスキルアップを感じる一方で、
過剰な負担や曖昧な役割分担によって、ストレスを感じるケースも増えています。
本記事では、仕事の兼務によるストレスの原因と、その仕組み的な背景を整理し、
無理をせず負担を減らすための現実的な方法を紹介します。
「我慢」ではなく「仕組みの改善」で、働きやすい環境を整えるヒントをまとめました。

責任感が強い人ほど、知らず知らずのうちに抱え込みやすいものです。
本記事では、読者の方に少しでも役に立つような、実践的な方法をまとめました。
- 仕事の兼務によるストレスの主な原因と背景を理解できる
- 負担を減らすための具体的な改善策と相談ルートを知る
- 我慢ではなく「仕組み」で解決する考え方を学べる
- 長期的に働きやすいキャリア形成のヒントを得られる
仕事の兼務でストレスを感じるのはなぜ?【原因と背景を解説】

兼務は「経験を広げるチャンス」と捉えられる一方で、負担が増すことでストレスを感じやすい仕組みでもあります。
ここでは、なぜ兼務が生まれ、どのようにして心身の余裕を奪うのかを整理します。
- 兼務が生まれる背景と現代職場の構造
- 兼務によって発生する主な負荷(時間・責任・情報量)
- 負担が大きくなりやすい職場・人の特徴
- 厚労省データで見る「働きすぎ実感」とストレスの関係
兼務が生まれる背景と現代職場の構造
近年、企業のスリム化やプロジェクト型組織の増加により、
一人の社員が複数の役割を担う「兼務体制」が一般化しているのです。
特に中小企業では、人員を増やせない事情から、既存メンバーに追加業務が割り当てられるケースも多く見られます。
また、DX推進やリモートワーク拡大によって、
“物理的な部署の境界”が曖昧になったことも兼務を加速させています。
たとえば、マーケティングと営業支援、経理と総務など、業務の垣根が低くなった結果、
複数分野を並行して担当する流れが定着しつつあるのです。
企業の効率化や働き方の多様化が進む中で、部署の境界が薄れ、複数の役割を担う「兼務体制」は現代の職場では一般的な構造となっています。
- 組織の効率化と人員削減が背景にある
- DX化により役割の境界が曖昧に
- 中小企業では兼務が制度化しているケースもある

兼務は一見「柔軟な働き方」に見えますが、
適切な分担やサポート体制がないと、個人の負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。
兼務によって発生する主な負荷(時間・責任・情報量)
兼務で最も多い悩みは、「時間の足りなさ」です。
複数業務を並行することで、作業の切り替えや調整が増え、結果的に生産性が下がることもあります。
担当範囲が広がるほど「どこまで責任を持つべきか」が不明確になり、
心理的なプレッシャーが高まる傾向も見られます。
情報量の増加も見逃せません。
各部署やプロジェクトで扱うデータ・会議・報告などを整理しきれず、
「頭の中が常にフル稼働している」状態が続くこともあるでしょう。
限られた時間の中で複数の仕事をこなさなければいけない環境が、
ストレスを生み出しているのです。
- 時間的制約による疲労蓄積
- 責任範囲の不明確さによる精神的負担
- 情報過多による集中力の低下

「忙しいのに終わらない」という感覚は、兼務の典型的なサインです。
単なる努力不足ではなく、構造的な課題として捉えることが大切です。
負担が大きくなりやすい職場・人の特徴
兼務で負担を感じやすいのは、個人の性格だけでなく職場の文化にも左右されます。
「報告よりも結果重視」「助け合いが少ない」「残業が前提」といった風土では、
兼務者が孤立しやすく、サポートが得られない傾向があるのです。
また、真面目で責任感の強い人ほど「自分が頑張ればいい」と抱え込みやすく、
助けを求めるタイミングを逃すことがあります。
これは性格の問題ではなく、組織内のコミュニケーション構造が影響している場合もあります。
仕事が集中している状況でサポートを得られず、一人で抱え込んでしまうことがストレスに繋がっているのです。
- 結果重視でサポートが少ない職場
- 助けを求めにくい文化
- 責任感の強い人ほどリスクを抱えやすい

負担を感じやすいのは「弱いから」ではありません。
仕組みがサポートを前提としていない職場では、誰にでも起こり得ることです。
厚労省データで見る「働きすぎ実感」とストレスの関係
厚生労働省の「労働安全衛生調査(令和6年)」によると、
6割以上の労働者が「仕事で強い不安・悩み・ストレスを感じている」と回答しています。
(出典:厚生労働省「令和6年『労働安全衛生調査(実態調査)』の概況」)
特に「仕事の量」「責任の重さ」「人間関係」に関する項目が上位を占めており、
兼務が重なることでこれらの要因が複合的に作用しているといえるでしょう。
同調査では「上司や同僚からの支援がある」と回答した層ほど、
ストレスを感じにくい傾向が示されています。
以上のことから、個人の努力よりも組織的な支援の有無が重要であるといえるのです。
- 労働者の6割がストレスを実感(厚労省調査より)
- 負担の内容は「量」「責任」「人間関係」が中心
- 支援体制の有無がストレス軽減に大きく影響

データからもわかるように、兼務の負担は「仕組みの問題」です。
個人が我慢するより、支援を受けられる環境づくりを重視する視点が欠かせません。
仕事の兼務によるストレスが大きくなる主なポイント4選

兼務によるストレスは、「仕事が多いから」という単純な理由では語れません。
背景には、役割の重なりや評価のズレ、情報共有の不足など、職場構造に起因する要因が複雑に関わっています。
ここでは、その仕組みを具体的に見ていきましょう。
- タスク量と役割のバランスが崩れる理由
- 評価や報酬とのギャップが生む不満
- 情報共有不足によるコミュニケーション負荷
- リソース配分が曖昧な組織の問題点
タスク量と役割のバランスが崩れる理由
兼務では、各業務が独立しているわけではなく、互いに連動して進行します。
たとえば「A業務の報告を出す前に、B業務のデータが必要」といったケースが多く、
時間配分が難しくなります。結果として、どの業務も中途半端にしか進まない感覚に陥りがちです。
加えて、各部署が「自分の業務を優先してほしい」と考えると、
兼務者は複数の上司やチームからの指示に板挟みになります。
“優先順位の曖昧さ”が、ストレスの根本的な原因の一つです。
- 複数業務の依存関係が生まれやすい
- 各部署の要望が重なり優先順位が混乱
- タスク管理が複雑化して精神的負担が増す

タスク管理が追いつかないのは怠慢ではありません。
構造的に整理しづらい仕組みが背景にある場合が多いのです。
評価や報酬とのギャップが生む不満
兼務で成果を上げても、評価基準が単一の職務に合わせられている場合、
努力が十分に反映されないことがあります。
たとえば、A部署の成果を出してもB部署では目立たない、
あるいは「どちらの成果として評価すべきか」が不明確なケースです。
このような状況は、「やっても報われない」という感情につながり、
モチベーションの低下を招きます。
報酬や評価制度が曖昧なままでは、
社員の負担だけが増えてしまうという悪循環が起きるでしょう。
- 兼務の成果が正当に評価されにくい
- 「努力と報酬の不一致」が不満を生む
- 長期的なモチベーション低下につながる

兼務が多い職場ほど、評価基準の明確化が求められます。
透明性のある仕組みが、信頼と継続意欲を支えるのです。
情報共有不足によるコミュニケーション負荷
兼務を行う人は、複数の部署・プロジェクトに関わるため、
常に多方向の情報を扱う必要があります。
しかし、情報共有のルールやツールが統一されていないと、
伝達ミスや確認の手間が増え、結果的に業務効率が低下するでしょう。
「誰に何を伝えたか」が把握できない状態は、ミスの原因にもなり、
心理的な緊張を高める要因となります。
SlackやTeamsなどのツールを活用し、
情報共有のルートを明確にすることが重要です。
- 部署間で情報共有の仕組みが異なる
- 確認や報告の手間が増えやすい
- 情報の重複や抜け漏れがストレスを生む

情報共有の仕組みを整えるだけで、兼務の負担は大きく軽減します。
コミュニケーション設計も、立派な業務改善の一環です。
リソース配分が曖昧な組織の問題点
兼務体制を導入している企業では、リソース(時間・人材)の配分が明確でないケースが多く見られます。
「この業務は何割の時間を使っていいのか」「どこまで責任を負うのか」が定義されていないと、
結果的に全ての業務が“中途半端”に進行してしまうのです。
また、上司やチーム間で認識のズレがあると、同じタスクを複数人が重複して行うなどの非効率も発生するでしょう。
リソース配分が曖昧な状態が続くと、個人だけでなくチーム全体の生産性にも影響を及ぼします。
- リソース配分が不明確だと非効率が増える
- 責任範囲の曖昧さが混乱を招く
- 組織全体の生産性低下につながる

兼務が多い組織ほど、「誰が・どこまで」を明確にすることが不可欠です。
境界を見える化することで、責任も成果も共有しやすくなります。
仕事の兼務によるストレスを減らすための具体的な対処法3選+α

兼務によるストレスは、職場全体の仕組みを見直すことで改善できますが、
まずは自分でできる範囲から負担を軽減することも大切です。
ここでは、日常の業務整理から上司への相談、タスク効率化まで、
現実的に取り入れやすい対処法を紹介します。
- 業務を整理し、優先順位を明確にする方法
- 上司への相談をスムーズにする伝え方
- 会議やタスク管理を効率化して負担を減らすコツ
- 【比較表】自分で調整/上司に相談/仕組みを変える それぞれの特徴
業務を整理し、優先順位を明確にする方法
兼務をこなす上で、最初に行いたいのは「業務の見える化」です。
まず、自分が担当しているすべてのタスクを書き出し、
それぞれの重要度・緊急度・依存関係を分類して整理します。
ToDoリストではなく、「タスク構造図」や「優先マトリクス」を使うと、
どの業務が本当に優先すべきかが明確になるでしょう。
また、期限の重複や業務の抜け漏れを防ぐ効果もあります。
- すべてのタスクを書き出して可視化する
- 重要度と緊急度で分類する
- 優先順位を見える化し、時間配分を決める

忙しさを減らすには「整理の技術」が不可欠です。
可視化するだけで、頭の中の混乱が落ち着き、行動の優先度が見えてきます。
上司への相談をスムーズにする伝え方
兼務の負担を軽減するには、上司とのコミュニケーションが重要です。
ただし、「忙しい」「無理です」といった感情的な訴えではなく、
事実ベースで整理した情報をもとに話すことが効果的です。
たとえば、「現状の業務量が1.5倍になり、納期が重なっている」
「業務の一部を他メンバーに分担してもらえると助かる」と具体的に伝えましょう。
上司は数値やスケジュールで整理された話を聞くと、判断しやすくなります。
- 現状を数値や事実で整理して伝える
- 感情ではなく具体的な課題を共有する
- 代替案や希望を添えると建設的な話し合いになりやすい

相談は「弱音」ではなく「改善提案」です。
状況を整理して伝えることで、上司との信頼関係を深める機会にもなります。
会議やタスク管理を効率化して負担を減らすコツ
兼務者にとって、会議や報告の時間は大きな負担となります。
特に複数部署をまたぐ場合、会議が重なって時間が奪われがちです。
そこで有効なのが、会議時間の短縮と議題の事前共有です。
また、タスク管理ツール(Asana・Trello・Notionなど)を活用し、
「誰が何をいつまでに行うか」を明確に可視化することで、
やるべきことの抜け漏れや重複を減らせます。
- 会議は目的と終了時間を明確に設定する
- 議題を事前に共有して時間を短縮
- タスク管理ツールで作業を見える化

業務を効率化するためのツール導入は、「自分を守る工夫」です。
小さな改善でも、日々の負担を確実に軽くできます。
【比較表】自分で調整/上司に相談/仕組みを変える それぞれの特徴
| 対応方法 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 自分で調整する | タスクの見直しや時間管理で対応 | 即効性があり自律的 | 根本的解決には限界がある |
| 上司に相談する | 業務分担・支援体制を話し合う | 負担が分散されやすい | 話し方次第で印象が変わる |
| 仕組みを変える | チームや制度の改革を提案 | 長期的に効果が持続 | 実現まで時間がかかる |

兼務による負担を軽減するには、短期的な調整と長期的な仕組み改善の両立が必要です。
どちらか一方に偏らず、状況に合わせて柔軟に選ぶことが大切です。
仕事の兼務でストレスが限界になる前に見直すべきポイント4選

「もう限界かもしれない」と感じる前に、立ち止まって状況を整理することが大切です。
ここでは、兼務による過負荷が続く際に見直したい視点と、
改善のための具体的なアクションを紹介します。
- 社内での役割・担当を再確認するステップ
- 業務量が改善しないときの相談ルート(上司・人事・キャリア支援)
- 転職を考える際のチェックポイント
- 働き方をリセットするための現実的アプローチ
社内での役割・担当を再確認するステップ
兼務状態が長く続くと、どこまでが自分の責任範囲なのか見失いがちです。
責任の範囲を見失わないように、「自分が担当している業務のリスト」を見直し、
上司と一緒に役割の重なりや優先度を確認することから始めましょう。
また、チーム内で「誰が何を担当しているか」を共有することで、
業務の偏りや認識のズレを防げます。
特に、新しいプロジェクトが増えるタイミングでは、
この再確認を定期的に行うことが効果的です。
- 担当業務の範囲を整理する
- 上司と優先順位を共有する
- チーム全体で分担を可視化する

「やることが多すぎる」と感じたら、まず境界を見直すことから。
役割の線引きが曖昧なままでは、努力も成果も評価されにくくなります。
業務量が改善しないときの相談ルート(上司・人事・キャリア支援)
上司に相談しても改善が見られない場合、
次のステップとして「人事部門」や「社内キャリア支援窓口」を活用する方法を検討しましょう。
多くの企業では、働き方改革の一環として業務改善やメンタルケアの相談窓口を設置しています。
また、外部の公的機関(例:こころの耳)では、
職場ストレスや働き方の悩みを専門家に無料で相談できます。
社内だけに頼らず、客観的な視点を取り入れることで、
新しい解決策が見つかることもあるでしょう。
- 人事部やキャリア相談室を活用する
- 外部機関や専門家に相談して客観的意見を得る
- 解決策を複数ルートで模索する姿勢が大切

社内の関係だけで行き詰まったら、外の視点を借りましょう。
客観的な助言が、意外な突破口になることがあります。
転職を考える際のチェックポイント
兼務が常態化し、改善の見込みがない場合は、
環境を変えることも選択肢の一つです。
ただし、「今すぐ辞めたい」という衝動ではなく、
自分のキャリアを整理したうえで判断することが重要です。
たとえば、以下のポイントを整理しておくと、
転職活動でも自信を持って話すことができます。
- 今の環境で得たスキル・経験
- 今後のキャリアで重視したい働き方
- 転職先で避けたい課題(過重労働・曖昧な評価など)
これらを明確にすることで、「逃げの転職」ではなく「前向きな選択」がしやすくなります。
- 転職を考える際は、現職で得た経験とスキルを整理する
- 理想の働き方と避けたい課題を明確にする
- 感情ではなく、将来のキャリア軸に沿って判断する

転職はリスクではなく、キャリアのリセットの機会です。
自分の価値を見つめ直すことで、次の環境での成長が見えてきます。
働き方をリセットするための現実的アプローチ
ストレスが限界に達する前に、働き方をリセットする準備を進めておくことも大切です。
たとえば、業務時間を記録して「自分が何に時間を使っているか」を可視化することで、
改善点が見つかりやすくなります。
また、業務改善やキャリア相談を行う外部サービス(例:リクルートワークス研究所の調査資料など)を活用すれば、他社の働き方や成功事例を参考にすることも可能です。
最終的に、働く目的や生活とのバランスを見直すことが、長期的な安定につながるでしょう。
- 自分の労働時間を記録・分析する
- 他社の事例や専門家の意見を参考にする
- 「働く目的」を見直して軸を整える

リセットとは、逃げることではありません。
自分の働き方を整えるための前向きな選択です。無理のないペースを取り戻しましょう。
仕事の兼務によるストレスに悩む人へのアドバイス4選

仕事の兼務によるストレスは、誰にでも起こり得るものです。
しかし、「自分が弱いから」と考える必要はありません。
環境や組織の構造を見直しながら、自分に合った働き方を模索することが大切です。
ここでは、兼務を前向きに乗り越えるための考え方と、職場全体で支え合うための工夫を紹介します。
- 責任感が強い人ほど抱え込みやすい理由
- 職場全体で負担を分散するための工夫
- 自分のペースを取り戻すための環境づくり
- キャリアを長期的に守る「調整力」の身につけ方
責任感が強い人ほど抱え込みやすい理由
責任感が強い人ほど、「自分がやらなければ」と考え、業務を抱え込みやすい傾向があります。
この姿勢は誠実さの表れでもありますが、同時に自分を追い込む要因にもなりかねません。
特に、上司や同僚から信頼されている人ほど、「頼られる=応えるべき」と感じやすく、
断ることに罪悪感を覚えるケースも多いです。
しかし、限界を超えた努力は結果的に周囲への負担にもつながります。
「できない」と言える勇気もまた、責任感の一部です。
- 頼られるほど断りづらくなる心理
- 真面目な人ほど責任を過剰に背負いやすい
- 「引き受けない勇気」も組織の健全性を守る行動

頼られる人ほど、責任を分け合う意識が必要です。
自分が抱え込みすぎないことが、チームの力を引き出す第一歩になります。
職場全体で負担を分散するための工夫
兼務の負担は、個人の努力だけでは解消できません。
職場全体で業務を可視化し、チームで支え合う体制を作ることが重要です。
たとえば、週次で「業務シェアミーティング」を設け、
各メンバーが現在のタスク量を共有すれば、偏りを防げます。
また、共有ドキュメントやタスクボードを使って、
誰が何を抱えているかを全員が把握できるようにすることも効果的です。
このように、チーム全体で“見える化”を進めることが、
兼務による過負荷を防ぐ最も現実的な方法です。
- タスクをチーム全体で共有する仕組みを作る
- 定期的なミーティングで業務量を調整する
- 一人で抱え込まない文化を醸成する

「助けて」と言える環境を作ることが、チームを強くします。
負担の見える化は、メンバー同士の理解と信頼を深めるきっかけになるでしょう。
自分のペースを取り戻すための環境づくり
兼務による多忙な日々が続くと、自分のペースを見失いがちです。
一日の中で「集中」「休憩」「整理」のリズムを意識的に作ることで、
心身のバランスを整えられます。
たとえば、午前中は思考系タスク、午後は処理系タスクと時間を区切ることで、
切り替えがスムーズになります。
また、休憩時間を“予定に組み込む”ことも効果的です。
短い休息を定期的に取るだけで、集中力が長く保てることが多くの研究で示されています。
- 1日のリズムを意識して設計する
- タスクの種類ごとに時間帯を分ける
- 休息もスケジュール化して確保する

自分のペースを守ることは、成果を出すための基盤です。
忙しい時こそ“立ち止まる時間”を意識的に取るようにしましょう。
キャリアを長期的に守る「調整力」の身につけ方
兼務を続けるうえで欠かせないのが、「調整力」です。
これは、単にスケジュールを管理するだけでなく、
人との関係性を円滑に保ちながら、自分の意見を適切に伝える力を指します。
たとえば、業務の優先順位を調整する際には、
「なぜ今この仕事が必要なのか」「他業務との兼ね合いはどうか」
といった背景を説明できると、周囲の理解を得やすくなるでしょう。
また、相手の状況を理解しながら調整する姿勢があれば、
トラブルを未然に防ぐことにもつながります。
調整力は一朝一夕で身につくものではありませんが、
日々のコミュニケーションを意識することで確実に育てられるでしょう。
- 調整力=スケジュール+人間関係のバランス力
- 背景を説明することで信頼を得やすくなる
- 相手の立場を理解する姿勢が摩擦を防ぐ

調整力は、兼務だけでなくキャリア全体を支える武器になります。
自分の状況を正直に伝えながら、相手と歩調を合わせる意識を持ちましょう。
まとめ:仕事の兼務ストレスは「我慢」ではなく「仕組み」で解決しよう

ここまで、仕事の兼務によるストレスの背景、主な原因、そして改善のための具体策を見てきました。
最後に、この記事全体の要点を整理し、今後の行動につなげるためのヒントをまとめます。
- 要点整理(原因→改善→行動)
- よくある質問(FAQ)
- 関連リンク(厚労省・キャリア支援サービス)
要点整理(原因→改善→行動)
仕事の兼務がストレスにつながるのは、業務量の多さよりも「仕組みの不整合」に原因がある場合が多いです。
責任範囲の曖昧さ、評価の不一致、情報共有の欠如など、複数の要素が重なることで負担が増します。
そのため、個人の努力よりも「仕組みの見直し」が必要です。
タスクを整理し、優先順位を明確にすること。上司と業務配分を話し合うこと。
必要に応じて社内外の支援を活用すること。
これらを繰り返すことで、無理のない働き方を少しずつ取り戻せます。
- 原因:構造的な負担(役割・評価・情報の不均衡)
- 改善:業務整理と対話で仕組みを整える
- 行動:相談・支援・リセットを通じて現実的に対応

兼務によるストレスは、「頑張りが足りないから」ではありません。
負担の仕組みを整えることが、自分を守り、チームを健全に保つ第一歩です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 兼務を断ると評価に影響しますか?
A. 適切に理由を伝えれば、評価を下げることにはなりません。
「業務量が基準を超えている」「他タスクとの両立が難しい」といった客観的事実を説明すれば、
理解を得られるケースが多いです。
Q2. 上司に相談しても変化がない場合は?
A. 人事部門や外部の相談窓口を活用するのがおすすめです。
厚生労働省の「こころの耳」では、職場ストレスや業務負担について専門家に相談できます。
Q3. 兼務がつらくて転職を考えるのは甘いですか?
A. いいえ。自分を守るための選択は「甘え」ではありません。
環境が整っていない場合、転職はキャリアを立て直す有効な手段になり得ます。
行動まとめリスト(おすすめ行動3選)
- タスクを見える化して、優先順位を整理する
- 上司・同僚・外部機関に相談して支援を得る
- 「自分を守る働き方」を意識して、仕組みを整える
関連リンク
- 厚生労働省|労働安全衛生調査
┗ 労働者のストレス要因や労働実態を把握できる調査データ。 - こころの耳(厚生労働省)
┗ 職場の人間関係や業務ストレスについて相談できる公的窓口。 - JILPT(労働政策研究・研修機構)
┗ 働き方改革や兼務制度の調査レポートを掲載。 - リクルートワークス研究所
┗ 働き方のトレンドや人材戦略に関するレポートを公開。
関連記事
- フリーランス適性診断は怪しい?安全な診断サイトと危険なサイトの見分け方
- フリーランスがバイトしながら働くコツ|両立を成功させる時間・スキル・思考法
- 転職エージェントを休止したいときの正しい手順|退会との違いと再開のコツを解説
- 仕事がわからないことだらけの中堅社員が増えている理由と乗り越え方|焦らず前に進むキャリア再設計ガイド
- 仕事が暇なときにエクセルを触るべき理由|スキルアップで評価も変わる
- 仕事の属人化で休めない・退職を考える人へ|原因と改善ステップを実体験から解説
- 仕事が遅い人に「やめてほしい」と思うときの対処法|ストレスを減らす上手な関わり方
- 仕事で嘘を突き通す心理と対処法|人間関係を壊さないための向き合い方
- 仕事でポジションを取られた悔しさを乗り越える方法|原因・立ち直り・信頼回復のステップ
- 【保存版】私用は仕事を休む理由になる?正しい伝え方・例文・マナーを完全ガイド
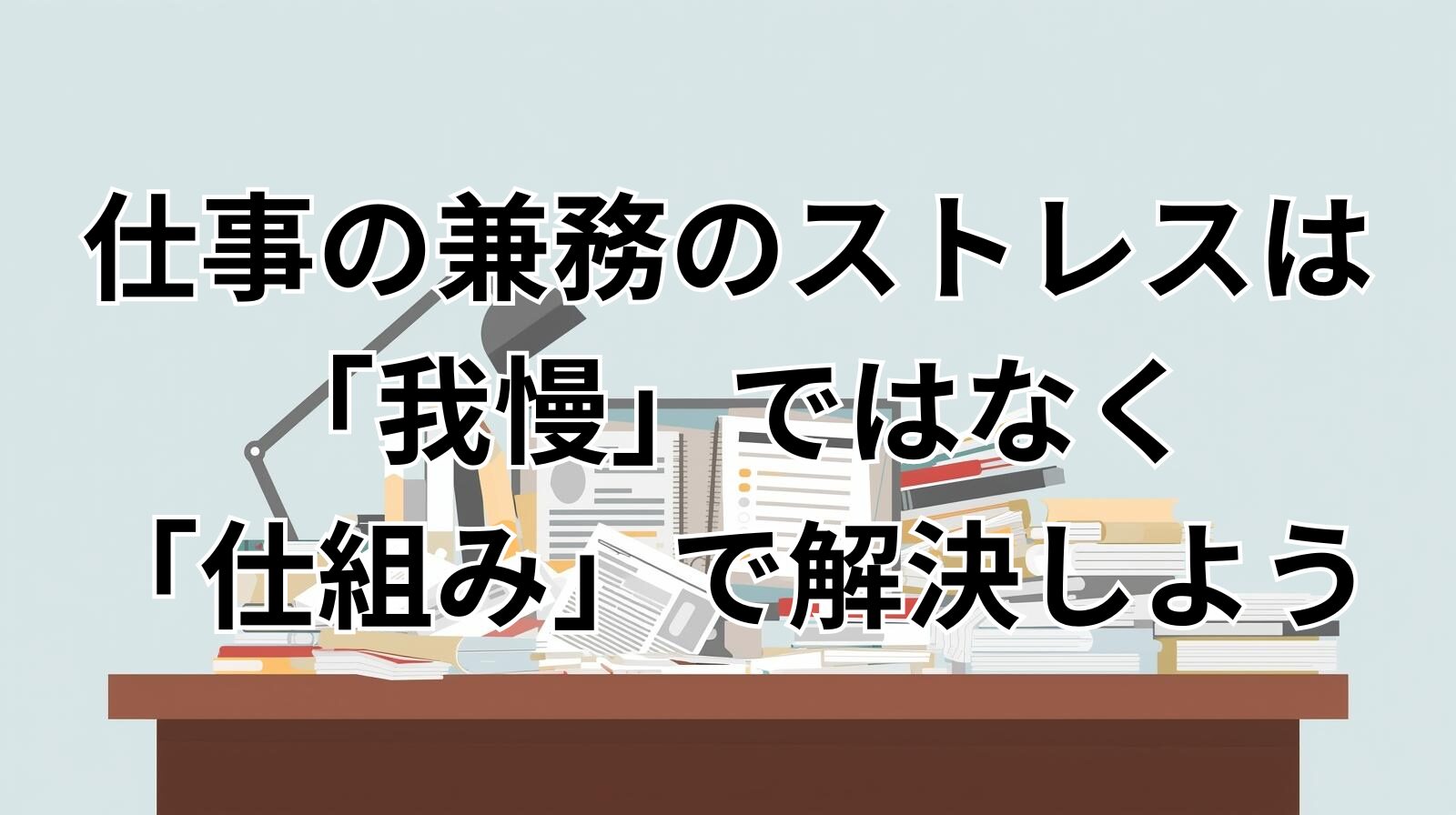

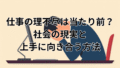
コメント