こうした悩みは、自分だけの問題ではなく“環境によるストレス反応”として多くの人が経験しています。
本記事では、匂いの種類別の原因と対処法、角が立たない伝え方、上司・人事への相談の流れまで、今日から少しでも負担を減らせる方法をまとめました。
匂いの問題は「我慢するしかない」と思われがちですが、対処法はいくつもあります。
この記事が、あなたが無理せず働くための一歩につながればうれしいです。

匂いに関する悩みは、人に話しづらく一人で抱え込みやすいテーマです。
本記事では、できるだけ負担を減らしながら状況を整えるための選択肢を、客観的な情報に基づいてまとめています。
今のつらさが少しでも軽くなるきっかけになればうれしく思います。
- 匂い問題は“環境ストレス”として扱われ、我慢だけで対処する必要はない。
- 段階的に選べる対処ルートがある(自衛 → 伝える → 相談 → 働き方調整)。
- 伝える場合は、クッション言葉+事実ベースが角を立てにくい。
- どうしても改善しない時は、上司・人事・産業医への相談や異動も現実的な選択肢。
職場の臭い人に耐えられないとき、すぐにできる対処法5選
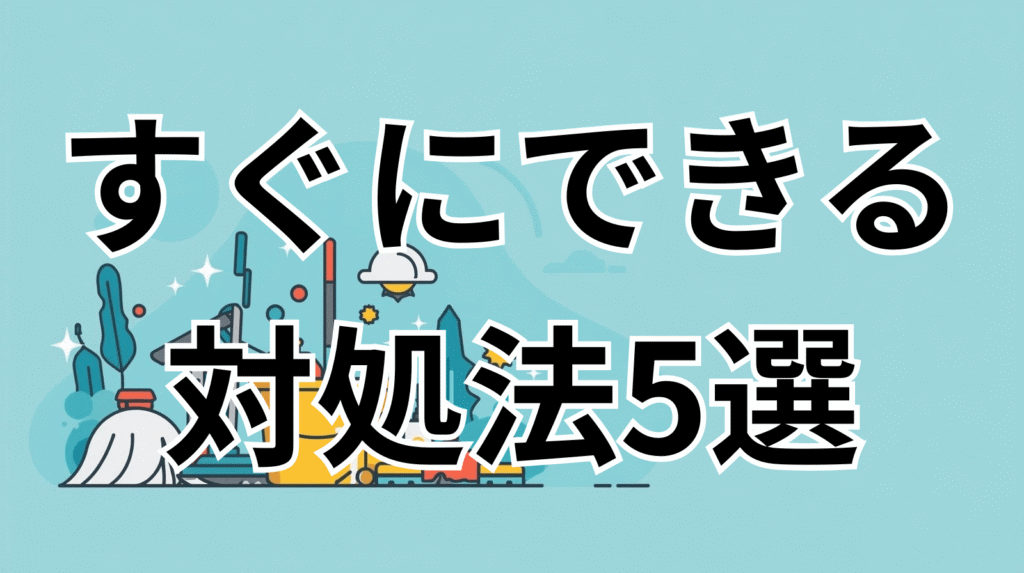
匂いが気になって集中できない日が続くと、思った以上に心身が疲れてしまいます。
職場では「我慢するしかない」と思い込みやすいテーマですが、実際には今日からできる対策がいくつもあります。
この章では、席配置の調整や換気、体調ケア、そして1日の終わりの回復ルーティンまで、無理なく取り入れられる方法をまとめました。
- 席の向き・配置を少しだけ変える
- 空気の流れを整える(換気・サーキュレーター)
- 卓上ファンを「自分用の空気シールド」として使う
- マスクを“予防目的”で使い分ける
- 短時間だけ席を外してリセットする
席の向き・配置を少しだけ変える
匂いのストレスを最も早く減らせる方法のひとつは、座る向きを少し変えることです。
真正面から香りが届くと刺激が強く感じられやすいため、斜め方向に位置をずらすだけでも負担が軽くなることがあります。
席替えが難しい職場でも、椅子の角度を5〜10度変えるだけで体感が変わるケースは少なくありません。
できる範囲で物理的な距離や角度を微調整し、ストレスを溜め込まない形を選んでいきましょう。
- 正面を避けるだけで匂いの刺激は弱くなる
- 大幅な席移動ができなくても“角度の工夫”が有効
- 可能な範囲で、レイアウトを変更して対策する

デスクの向きを斜めにするだけでも、ストレスの軽減につながることがあります。
「大きく変えないと意味がない」と思い込まず、小さな工夫から始めることが大切です。
空気の流れを整える(換気・サーキュレーター)
匂いが強く感じられるのは、空気が滞留しているときです。
そのため、換気や小型サーキュレーターで空気の流れを作るだけでも、匂いの刺激は和らぎます。
風を相手に向ける必要はなく、自分の横に軽く風を送るだけで十分に効果があるでしょう。
職場で共有の扇風機を使える場合は、弱風で空気を動かすだけでも快適になりますね。
- 匂いは“滞留”で強くなるため、風の道をつくる
- 風量は弱めでOK。自分側に向けると自然で角も立たない
- 設備が使えない場合は机まわりだけ動かす工夫も可

私の周囲でも、弱いサーキュレーターを置くだけで匂いのストレスが下がった方が多い印象です。
大げさな機器を使う必要はなく、小さな空気の流れが大きな差を生むことがあります。
卓上ファンを「自分用の空気シールド」として使う
どうしても匂いが直接届く場合は、卓上ファンを“空気のバリア”として使う方法が効果的です。
風を顔に当てると不自然になりやすいため、胸の高さから軽く風を流すと自然なかたちで匂いを拡散できます。
周囲から見ても“暑さ対策”に見えるため、心理的にも使いやすい点がメリットです。
- 不快な匂いは疲労につながり集中力を下げる
- においの少ない場所で短時間休むだけでも効果がある
- 水分・睡眠など基本的な体調管理も負担軽減につながる

仕事中に数分席を離れるだけでも、気持ちが落ち着いて「あと少し頑張れそう」と感じる瞬間があります。
無理をせず、小さな休息を取り入れることは大切ですね。
マスクを“予防目的”で使い分ける
不織布マスクは、匂いの刺激を和らげる“受け止め役”として使えます。
香りつきのマスクで上書きすると逆に混ざった匂いが不快になることもあるため、無香料でしっかり密着するものが向いています。
「今日はきつい」と感じる日だけ使う“予防策”としても効果があるでしょう。
- 不織布マスクは匂いの刺激を弱める
- 無香料タイプを選ぶと混ざり臭を防げる
- 毎日でなく“今日はきつい”という日に使ってもOK

私も「今日は厳しいかも」という日にだけマスクを使っています。
完璧に遮断はできなくても、少し楽になるだけで心の余裕を持てるのです。
短時間だけ席を外してリセットする
嗅覚は疲れやすい感覚で、1〜2分の離席でも回復しやすいといわれています。
ずっと我慢し続けるよりも、コピーを取りに行く・廊下で深呼吸をするなど、こまめに距離を作る方が負担が少なくなります。
特に午後の後半は匂いへの耐性が落ちることが多いため、意識的なリセットが効果的です。
- 嗅覚は短時間でもリセットしやすい
- 仕事の動線に紛らせて自然に離席できる
- 続けて我慢するよりこまめに距離を作るほうが負担は少ない

私も「ちょっとコピーに行こう」と数分席を離れるだけで、戻ったときの体感が軽くなります。
我慢を続けるのではなく、体調を守る行動だと考えてよいのではないでしょうか。
匂いの種類別の原因・特徴と“現実的な距離の取り方”
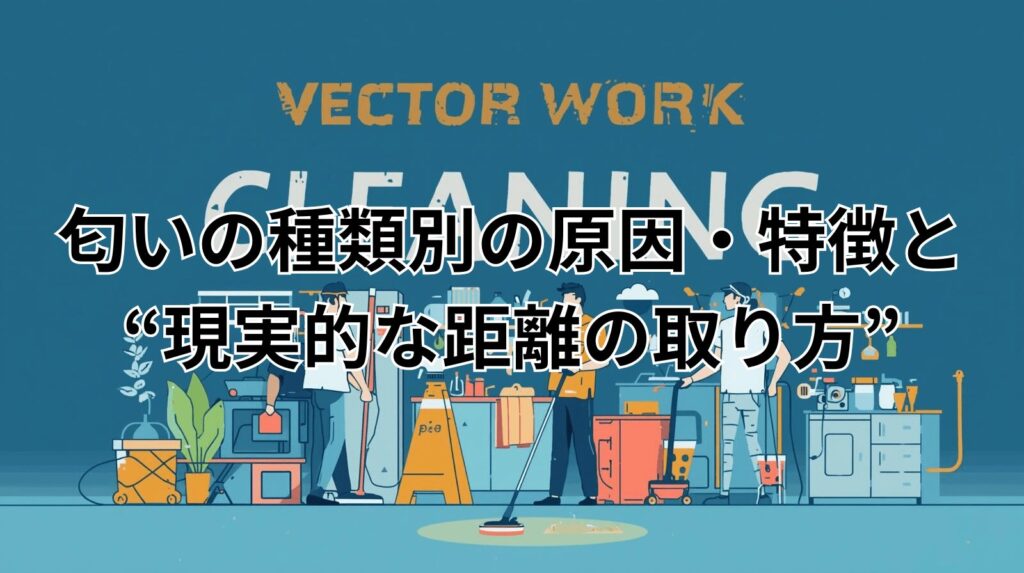
職場で感じる「匂いのつらさ」は、実は種類によって原因も特徴も大きく異なります。
体臭・口臭・香水や柔軟剤の香り、衣類の雑菌臭など、ケースによって距離の取り方や対策は変わってくるでしょう。
この章では、それぞれの特徴を整理しながら、まず自分を守るためにできる距離の取り方をまとめています。
- 体臭・加齢臭|汗・皮脂・生活習慣が原因のケース
- 口臭|近距離の会話で強く感じる理由と特徴
- 香水・柔軟剤|強すぎる香りが起こす「香害」の仕組み
- 衣類の雑菌臭(濡れたタオル臭)|洗濯環境が原因のケース
- 匂い種類別の「まず自分を守る距離の取り方」一覧
体臭・加齢臭|汗・皮脂・生活習慣が原因のケース
体臭や加齢臭は、汗と皮脂が空気に触れて酸化したり、菌と反応することで強まることがあります。
特に、気温が高い季節や、湿度がこもるオフィスでは匂いが強まりやすい傾向があります。
理由として、汗を分解する細菌が増えやすい環境だと匂いの発生量が増えるためです。
体臭は本人が気づきにくい特徴があるため、周囲が強く感じることがあるでしょう。
人事系メディアでも、体臭は「職場のにおいトラブルの上位」に挙がるとされています。
(出典:契約ウォッチ「スメルハラスメント(スメハラ)とは?」)
距離を取りたいときは、真正面を避けて横方向に座る、仕事中の導線が重ならない席を選ぶなど、ストレスが少ない配置に変えるのが効果的です。
席の位置を変えられない場合は、卓上ファンやパーテーションを活用して対策しましょう。
- 汗・皮脂の酸化や菌の増加で匂いが強くなる
- 本人が気づきにくく、周囲が先に負担を感じやすい
- 椅子や席の角度を変えるだけでも負担が軽減する

「少し席の角度を変えるだけで気にならなくなった」という相談は、意外と多いものです。無理のない距離を作るだけでも気持ちが変わることがあります。
口臭|近距離の会話で強く感じる理由と特徴
口臭は、近距離の会話や対面業務で急に強く感じる場合があります。
原因には、舌苔(舌の汚れ)、胃腸の不調、寝不足などさまざまな要因があるのです。
特に密接距離(45cm以内)では匂いが直接届きやすく、強く感じやすいとされています。
会議や面談など、避けにくい場面が続くと精神的な負担にもつながるでしょう。
どうしても距離が取れないときは、席を横並びに変える、相手の真正面に座る時間を短くするなど、身体的距離を微調整して対策しましょう。
活性炭入りマスクや無香料マスクなどでも、ある程度の対策は可能です。
- 近距離ほど口臭を強く感じやすい
- 会議・面談など避けにくい場面で負担が積み重なる
- 横並びの座り方や、マスクなどの対策が有効

会議で真正面に座るとつらかった、という声は珍しくありません。
配置の工夫は小さくても効果がある場合があります。
香水・柔軟剤|強すぎる香りが起こす「香害」の仕組み
香水や柔軟剤の強い香りは、量や種類によっては頭痛や吐き気を引き起こすことがあります。
香料の粒子は衣類や髪に残りやすく、持続時間も長いことが特徴です。
健康被害を訴えるケースもあり、SNS上でも「柔軟剤の香りで頭痛がする」という投稿が増えています。
(参考:マネーフォワードクラウド給与「スメルハラスメント(スメハラ)は労災認定される?具体的な基準や手続き、事例なども解説」)
風下になる席を避ける、距離を確保できる席を選ぶ、短時間だけマスクを使うといった方法で対策をしましょう。
- 香料は持続性が高く、人によっては頭痛の原因になる
- SNSでも「柔軟剤・香水の匂い問題」は相談の多いテーマ
- 風下に座らないなど環境調整が効果的

強い香りは体調に響くことがあり、小さな対策でも負担が減ることがあります。
まずは自分の心身を守ることを優先しましょう。
衣類の雑菌臭(濡れたタオル臭)|洗濯環境が原因のケース
生乾きのような匂いは、衣類に残った水分や雑菌が原因となるケースが多いです。
一度発生すると洗っても取れにくく、職場でも「近くを通ると気になる」という声が多くあります。
特に湿気の多い季節や、繊維が厚い衣類では菌が繁殖しやすいです。
雑菌臭は影響範囲が広がりやすいため、席が近いとストレスを感じやすくなります。
距離を取りづらい場合は、席方向の調整や卓上ファンなどの送風機の利用して対策しましょう。
- 雑菌が原因の“生乾き臭”は落ちにくい
- 湿気が多い環境では匂いが強まりやすい
- 距離確保や風向きの調整が負担軽減につながる

生乾き臭は本人が気づきにくいため、周囲が先に負担を感じることがあります。
距離を取ったり、風通しを良くすることでストレスを減らせるでしょう。
匂い種類別の「まず自分を守る距離の取り方」一覧
ここまで紹介した種類別の特徴を踏まえ、「まず自分を守る」という観点で距離の取り方を整理します。
| 匂いの種類 | 主な原因 | 負担が強くなりやすい理由 | 距離の取り方 |
|---|---|---|---|
| 体臭・加齢臭 | 汗・皮脂・酸化 | 蒸れやすい職場で拡散しやすい | 斜め座り・通路側へ移動 パーテーションや卓上ファンで対策 |
| 口臭 | 口内環境・胃腸・生活習慣 | 近距離の会話で直接届く | 横並びの座り方/向かい合わない 匂いを防止できるマスクを使用 |
| 香水・柔軟剤 | 香料・付着 | 持続性が高く頭痛の原因に | 風下を避ける・距離を確保 マスクを使用 |
| 雑菌臭 | 湿気・洗濯環境 | 匂い範囲が広く残りやすい | 席方向の調整・送風機利用 |
- 種類によって“負担の原因”が異なる
- 距離と風向きの調整は多くの匂いで共通して有効
- 「まず自分を守る」が最優先になる

匂いの種類を知るだけでも、対策の方向性がはっきりします。
無理なくできる範囲で距離を作ることで、自分を守りましょう。
「職場の臭い人」に直接伝えるべきか?迷った時の判断基準3選+α
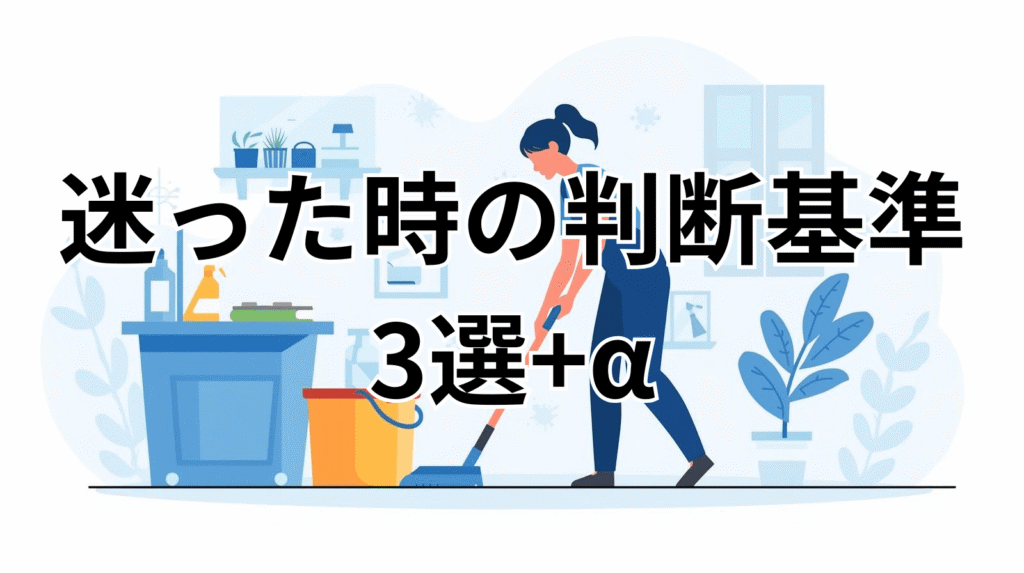
匂いがつらいと感じても、「本人に言っていいのか」「言わないほうがいいのか」で悩む人は多いです。
伝え方を誤ると関係が悪化する心配があり、かといって我慢し続けるのも負担になるでしょう。
この章では、公的資料や人事の現場の考え方を踏まえ、判断の軸を整理していきます。
- ① 業務に支障が出ているか(集中・体調・距離)
- ② 相手との関係性・伝えるリスクはどれくらいか
- ③ 他の人も困っているか(主観だけで判断しない)
- 言わない選択をする際のメンタルケアは?
① 業務に支障が出ているか(集中・体調・距離)
まず確認したいのは「仕事に影響が出ているかどうか」です。
匂いによって集中力が下がったり、頭痛・吐き気などの体調不良が起きている場合は、職場環境の問題として捉えられます。
厚生労働省も、環境要因(温湿度など)が職場のこころの健康に影響を与えると示しています。
(出典:厚生労働省「職場におけるこころの健康づくり」)
我慢が続いて「業務に支障が出ている」と感じるなら、席替えや相談の検討を始めても問題ありません。
自分の体調を守る視点を持つことが大切です。
- 嗅覚ストレスは集中力低下や体調不良の原因になる
- 厚労省も環境要因がこころの健康に影響を与えることを認めている
- 業務に支障が出ているなら、調整や相談を検討してよい

「仕事が終わるころには頭痛がする」という方は少なくありません。
つらさを我慢し続けないことが、本来のパフォーマンスにもつながります。
② 相手との関係性・伝えるリスクはどれくらいか
次に確認したいのは、相手との関係性です。
普段から話しやすい相手なら、やんわり伝えられるケースもありますが、距離のある相手に伝える場合は慎重な判断が必要です。
匂いは“デリケートな問題”であるため、本人が傷ついたり、関係悪化につながるリスクがあります。
人事の相談窓口でも「匂いの話題は、相手の尊厳に触れやすい」という理由から、第三者(上司・人事)を通して調整するケースが推奨される場合があります。
無理に自分で伝える必要はなく、あくまで選択肢のひとつとして考えましょう。
- 匂いは相手の尊厳に関わるため、伝え方が難しい
- 関係の近さによって伝える難易度やリスクが変わる
- 無理に自分で伝える必要はなく、別の選択肢もある

「言って関係が悪くなるのが怖い」と感じるのは当然です。
伝えるかどうかは、自分の心の負担も含めて判断してよいと思います。
③ 他の人も困っているか(主観だけで判断しない)
匂いの感じ方は個人差が大きいため、自分だけが気になっているのか、周囲も困っているのかを見極めることが大切です。
もし複数の人が同じ悩みを持っている場合は、“個人の問題”ではなく“職場環境の問題”として扱いやすくなります。
ただし、周囲に聞くときは配慮が必要です。
噂話にならないよう、必要以上に広げないようにしましょう。
(参考:契約ウォッチ「スメルハラスメント(スメハラ)とは?」)
- 匂いの感じ方は個人差が大きい
- 複数人が困っているなら“職場環境の問題”として対応しやすい
- 周囲に確認する際は、噂にならないよう慎重に

自分だけの問題ではなかったと分かると、少し気持ちが軽くなることがあります。ただし、職場内で話が広がらないよう注意が必要ですね。
言わない選択をする際のメンタルケアは?
伝えることにリスクを感じたり、環境的に難しい状況では、言わないという選択も考えられるでしょう。
その場合は、自分を守るための工夫を強化することがポイントになります。
席配置の微調整や換気、マスクや卓上ファンなどの利用、短時間の離席、終業後のリカバリー習慣など、これまで紹介してきた自衛策が役立つでしょう。
こころの耳(厚労省)でも、環境要因に限らず、自分で負担を減らせる方法を取り入れることが大切とされています。
(参考:こころの耳「15分で分かるセルフケア」)
言わないことを選んだ際は、換気や道具の利用など、別の方法で対策していきましょう。
- 「言わない」という選択も現実的で合理的
- 自衛策を強化することで負担を軽減できる
- 厚労省も“セルフケア”を有効な対処のひとつとして紹介している

言わないことを選ぶ人は少なくありません。
その場合は、これまでに紹介した自衛策を使ってストレスを軽減させましょう。
職場の臭い人に耐えられない時の伝え方
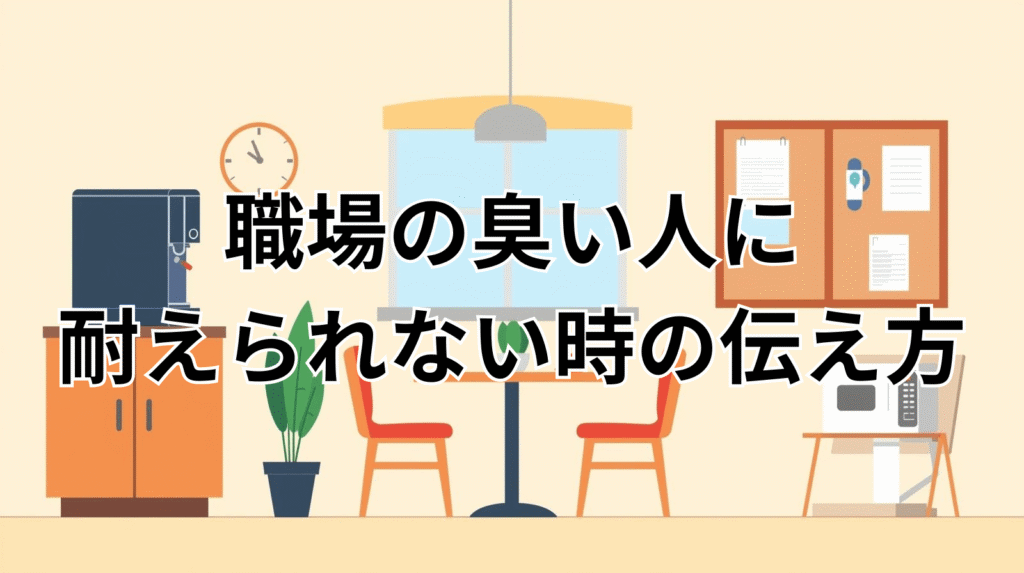
「匂いのことを本人に伝えたいけれど、どう言えばいいかわからない…」と悩む人は多いです。
匂いの話題は相手の尊厳に触れやすく、伝え方を誤ると関係が悪化する可能性があるでしょう。
この章では、クッション言葉の使い方や、事実ベースで伝える会話テンプレート、第三者に着地させる方法など、角を立てにくい伝え方を説明します。
- 避けるべきNGワードと正しいクッション言葉
- 事実ベースで伝える会話テンプレート
- 相手を傷つけにくい「第三者/環境」に着地させる方法
- 伝えた後のフォローで雰囲気を悪化させないコツ
避けるべきNGワードと正しいクッション言葉
匂いの話をする時は、まず“NGワード”を避けることが重要です。
直接的すぎる表現は相手が防御的になりやすく、受け止めにくくなります。
一方で、クッション言葉を添えると伝わり方が柔らかくなり、相手も落ち着いて話を聞きやすくなるでしょう。
たとえば「臭いです」「耐えられません」という強い表現は避け、まずは「少し気になることがあって…」「お伝えしづらいのですが…」などの前置きを使うことで、言葉の衝撃が和らぎます。
適切な言い回しは、伝える側・受け取る側の双方にとって心理的負担を減らす助けになるでしょう。
- 匂いの話題は直接的な表現が相手を傷つけやすい
- クッション言葉で衝撃を和らげると伝わりやすくなる
- 心理的負担を下げることが、冷静な会話につながる

相手の立場に立って言葉を選ぶだけで、伝えやすさが大きく変わります。
強い言い方を避けるだけでも、お互いの心の負担は軽くなるでしょう。
事実ベースで伝える会話テンプレート
次に重要なのは、「感情ではなく事実」で伝えることです。
匂いの問題を“あなたが悪い”と捉えられる言い方を避け、客観的な状況を淡々と共有すると、相手が受け取りやすくなります。
以下は、角が立ちにくい会話テンプレートの一例です。
- 「少し気になっていることがあり、お伝えさせてください。」
- 「最近、席のあたりで香りが強い時があって、頭が痛くなることがあるんです。」
- 「ご本人のご事情もあると思うので、もし調整が可能でしたらお願いできますか?」
ポイントは「あなたの匂いがキツい」ではなく、「香りが強い時がある」「体調に影響が出ることがある」など、“現象”を中心に話すことです。
この方法は、人事・産業医でも推奨される「事実から伝える」コミュニケーションと同じ考え方です。
(参考:White Jack「産業医 平野井先生と考える(6) メンタル不調の対応策と緊急時の対応」)
- 感情的な表現より「事実ベース」の方が受け入れられやすい
- 主語を「あなた」ではなく「香り」「状況」にする
- 会話テンプレートを使うと伝えやすくなる

筆者コメント
事実ベースで話すだけで、相手の受け止め方が変わります。私も、状況を丁寧に共有する方法が一番穏やかに話せると感じています。
相手を傷つけにくい「第三者/環境」に着地させる方法
匂いの話題で角が立ちやすい理由のひとつは、相手が「自分の身体を否定された」と感じやすい点です。
そこで効果的なのが、「第三者」や「環境」の話として着地させる方法です。
例として以下のような伝え方があります。
- 「最近、フロア全体が香りでこもることがあって…」
- 「空調の関係で香りが流れやすいみたいなんです。」
- 「周りでも気になっている方がいるようで、念のため共有させていただきました。」
相手だけに原因を帰属させず、環境要因として扱うことで、責められている印象が軽減できるでしょう。
厚労省が示すハラスメント防止の考え方でも、環境改善を重視する姿勢が示されています。
(出典:厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」)
- 匂い問題では「個人に原因を帰属させない」工夫が重要
- 環境や第三者を軸に話すと角が立ちにくい
- ハラスメント指針でも環境改善の視点が重視されている

相手を責めない伝え方は、お互いの心の負担を大きく減らします。
環境の話にして説明するだけでも、会話がスムーズになるでしょう。
伝えた後のフォローで雰囲気を悪化させないコツ
伝えた後のフォローが不十分だと、相手が気まずさを抱えたままになり、関係に影響することがあります。
大切なのは「変に避けないこと」と「普段通りの態度を心がけること」です。
たとえば、翌日に軽く挨拶するだけでも、相手は「嫌われたわけではない」と安心しやすくなります。
また、必要以上に気にかけすぎず、仕事上のコミュニケーションは通常通り行うことがポイントです。
伝えた後のフォローを十分に行い、気まずい関係にならないよう心がけましょう。
- 伝えた後は普段通りの態度を心がける
- 避けたり距離を置きすぎると誤解が生まれやすい
- 挨拶など小さな行動が安心感につながる

伝えた後は、お互いに少し気まずさを感じるものです。
丁寧な挨拶などの小さな行動が、関係を穏やかに保つ助けになると思います。
職場の臭い人問題を相談するには|上司・人事・産業医への伝え方と手順
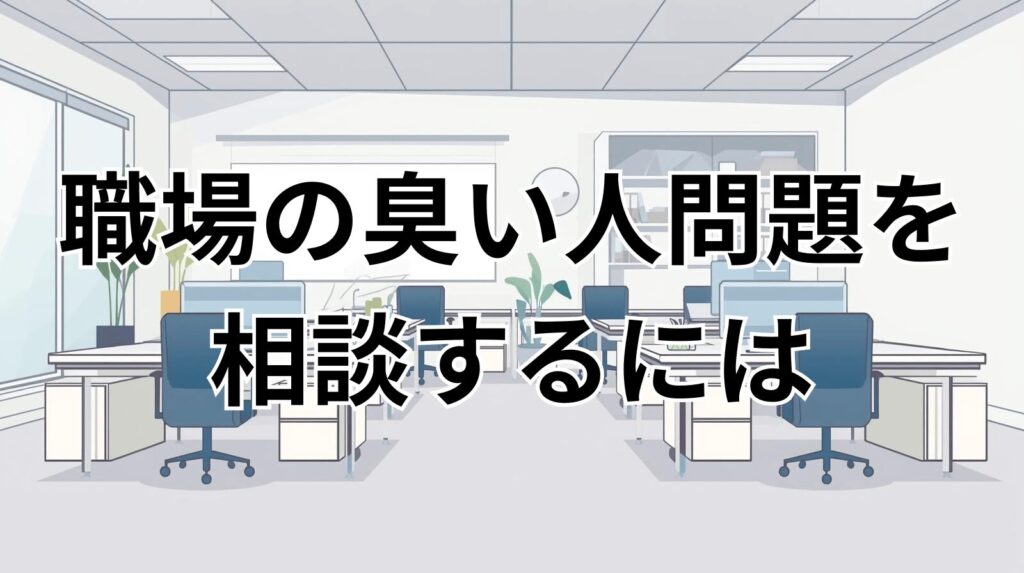
自分で伝えるのが難しいと感じたとき、相談先として頼れるのが「上司 → 人事 → 産業医」というルートです。
匂いは相手の尊厳に関わるデリケートな問題のため、第三者を通して調整したほうが円滑に進むケースが多いとされています。
この章では、相談の順序や手順、相談文例などをまとめました。
- 相談の順番(上司→人事→産業医)が推奨される理由
- 相談文例テンプレ(メール/口頭)
- 相談しても相手にバレない?情報共有の仕組み
- 厚労省のハラスメント指針における“におい問題”の扱い
相談の順番(上司→人事→産業医)が推奨される理由
まず最初の相談先として直属の上司が挙げられます。
問題が環境要因として扱われる場合は、上司の判断だけで改善できることもあるでしょう。
それでも改善が難しい場合は、人事や総務へ相談する流れになります。
人事部門は職場の衛生配慮・ハラスメント防止など、組織的に対応すべき課題として判断しやすい立場です。
さらに体調不良が出ている場合は、産業医への相談も考えましょう。
産業医は医学的観点から助言を行う役割として労働安全衛生法で定められており、働く人の健康を守る立場にあります。
- 最初の相談先は「直属の上司」が基本
- 人事は職場全体の環境改善として判断できる立場
- 体調不良がある場合は産業医への相談も可能

相談先を順番にたどることで、個人だけで抱え込まずに済む場面が増えます。
負担をひとつずつ分散させるイメージで進めると楽になるでしょう。
相談文例テンプレ(メール/口頭)
匂いの問題は直接言いづらい方には、「メール」や「短い口頭相談」が向いています。
相手を責める形にならないよう、“体調・環境・業務への影響”の3点を中心に伝えると、受け手も対応しやすくなるでしょう。
お疲れさまです。〇〇です。
少し相談したいことがあり、ご連絡しました。
最近、フロアで香りが強い時間帯があり、頭痛や集中力の低下が起きることがあります。
業務に支障が出ないように、席の調整や環境改善の相談ができればと思っています。
お手すきの時に少しお時間をいただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 「少し相談したいことがありまして…最近、匂いで体調が悪くなることがあって困っています。」
- 「席の調整など可能性があれば、ご相談したいです。」
事実ベースで淡々と伝えることがポイントです。
- メールは落ち着いて事実を整理して伝えられる
- 「体調・環境・業務への影響」を中心に話す
- 相手を責める語尾を避けることで相談が通りやすくなる

自分の体調を中心に相談の軸を置くと、相手に“責めている印象”を与えにくいため、話をスムーズに進められるでしょう。
相談しても相手にバレない?情報共有の仕組み
「相談したことが本人に知られてしまうのでは?」という不安はとても自然です。
しかし、人事部門やハラスメント窓口では、相談者のプライバシー保護が基本とされています。
厚生労働省の指針でも、相談者への不利益な扱い(いわゆる二次被害)の禁止が明記されているのです。
(出典:厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」)
実際の運用では、席替えや環境改善など、匂いの問題を「個人特定しない形」ですすめることが多く、相談者の名前を伝えないまま調整されるケースもあります。
もちろん職場の運用によって細部は異なりますが、“相談した=本人に伝わる”という仕組みではないと考えて良いでしょう。
- 相談内容はプライバシー保護が原則
- 厚労省指針でも「相談者の不利益な扱い」を禁止
- 実務では個人特定せずに環境調整されることが多い

「相談したらバレてしまうのでは」と心配される方は多いですが、実際には匿名性が保たれる形で動くケースがほとんどです。
厚労省のハラスメント指針における“におい問題”の扱い
厚生労働省のハラスメント関係指針では、におい問題は直接的に「ハラスメント」と定義されているわけではありません。
(出典:厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」)
ただし、“身体的・精神的な苦痛を与える言動”に該当する可能性があるため、状況によっては相談対象となり得ると解釈されています。
(参考:契約ウォッチ「スメルハラスメント(スメハラ)とは?」)
また、指針では「意図の有無にかかわらず、結果として相手が不快と感じる場合が対応の対象になる」と示されています。
記述から、においの問題は相手を不快にさせやすい状況の一つと考えられるでしょう。
職場としては、環境改善・席調整・相談体制を整備し、個人が抱え込まないための仕組みづくりが求められます。
- におい自体が「ハラスメント」と明記されているわけではない
- ただし“相手が不快になる状況”として対応対象になり得る
- 指針では意図よりも「結果」が重視される

公的資料でも「におい=ハラスメント」と断定されてはいませんが、業務に支障がある場合は、相談することで解決に動く可能性があります。
まとめ|職場の臭い人問題も、自分に合う距離感で対処できます
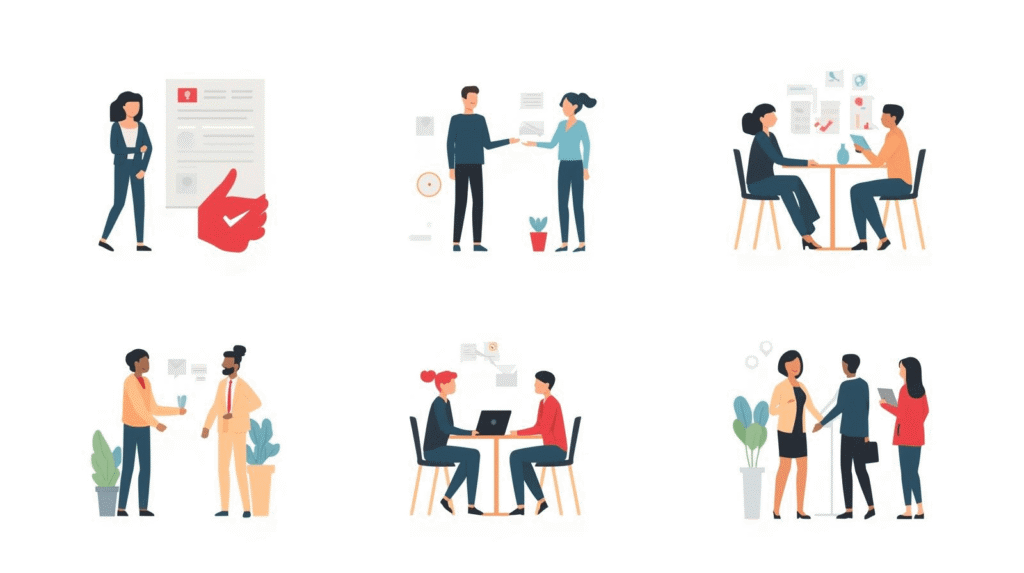
匂いの問題は、我慢し続けるほど心身に負担が溜まりやすいテーマです。
しかし、今日からできる小さな工夫から、ある程度の対策は可能です。
この章では、これまで紹介してきた対処の流れをまとめます。
行動の優先順位(自衛→伝える→相談)
匂い問題を解決するには、段階的に行動することが負担を減らすポイントです。
まずは自分を守る距離の取り方を試し、それでも対策が難しい場合は伝える・相談するという順番で動きましょう。
優先順位は次の通りです。
- 自衛策(距離・換気・休息・体調ケア)
- 伝える(クッション言葉・事実ベース)
- 相談する(上司→人事→産業医)
選べる対処ルートを振り返る
匂い問題の対処には、複数のルートがあります。
様々な選択を取れると知っておくことで、匂いの問題に悩まされることが少なくなるでしょう。
以下は、本記事で紹介した対処ルートのまとめです。
- 自衛ルート:席配置・換気・卓上ファン・マスク・短時間離席
- 会話ルート:クッション言葉・事実ベース・環境の話に置き換える
- 相談ルート:上司 → 人事 → 産業医
- 環境改善ルート:席替え・配置換え・空調調整
今の自分にとって無理のない選択から始めてみてください。
FAQ(よくある質問)
Q1.直接言っていい?言わない方がいい?
A.どちらが正解というわけではなく、関係性・リスク・自分の負担を踏まえて判断するのが現実的です。伝え方に迷う場合は、無理に自分で伝えず相談ルートを使ってかまいません。
Q2.相談すると“告げ口”だと思われない?
A.厚労省指針では、相談者への不利益扱い(いわゆる二次被害)を禁止しています。実務でも相談者を特定しない形で環境改善が進むケースが多いため、必要以上に恐れなくても大丈夫です。
(出典:厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」)
Q3.どの匂いが“相談レベル”に該当する?
A.匂いの種類よりも「体調や業務への影響」が判断軸になります。頭痛・吐き気・集中力低下などが続く場合は相談レベルと考えて問題ありません。
職場の臭い人に耐えられない人へ
匂いの問題は、人間関係や体調にも影響しやすく、一人で抱え込むほど負担が大きくなるものです。
だからこそ、自分に合った距離感や対処法を選ぶことは、決してわがままではなく健康を守るための大切な選択だと感じています。
また、第三者に相談したり環境を調整したりすることも、有効な手段です。
今日できる小さな工夫から始めるだけでも、職場での過ごしやすさは少しずつ変わっていくでしょう。
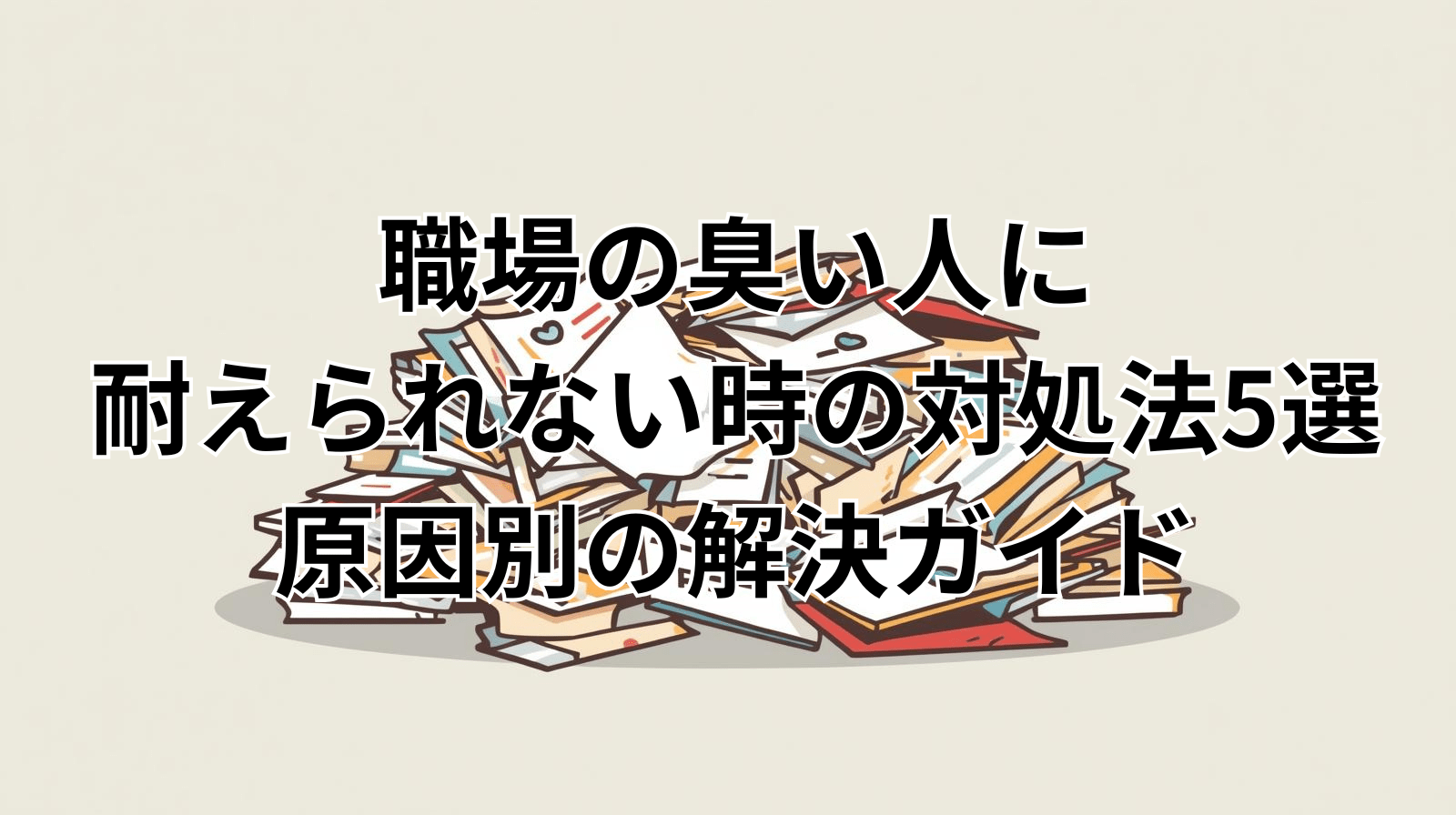
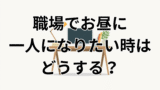
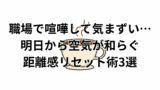
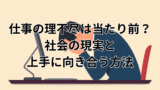
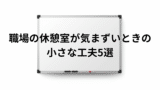
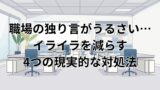
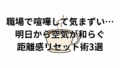
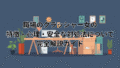
コメント