「明日、私用でお休みしたいのですが…」──この一言、失礼にならないか不安に感じたことはありませんか?
実は「私用で休む」はビジネスマナー的にも法律的にも、問題のない正当な表現です。
ただし、使い方や伝える相手によっては誤解を招くこともあります。
この記事では、「私用・所用・私事」の違い、社内と社外での言い分け方、当日・前日・事前の伝え方例文、有給休暇やハラスメント防止の観点から見た注意点までを詳しく解説します。
2025年の最新マナーと労働法の視点から、
安心して「私用で休む」と伝えられる方法を一緒に整理していきましょう。
この記事のポイント
- 「私用・所用・私事」の意味と正しい使い分けがわかる
- 「私用で休む」は法律的にもマナー的にも問題ない理由を解説
- 社内・社外での伝え方や例文を状況別に紹介
- 有給休暇の申請ルールと個人情報保護の考え方を解説
- 信頼を損なわずに「私用」を伝えるコツと注意点を紹介
私用を理由に仕事を休んでも大丈夫?
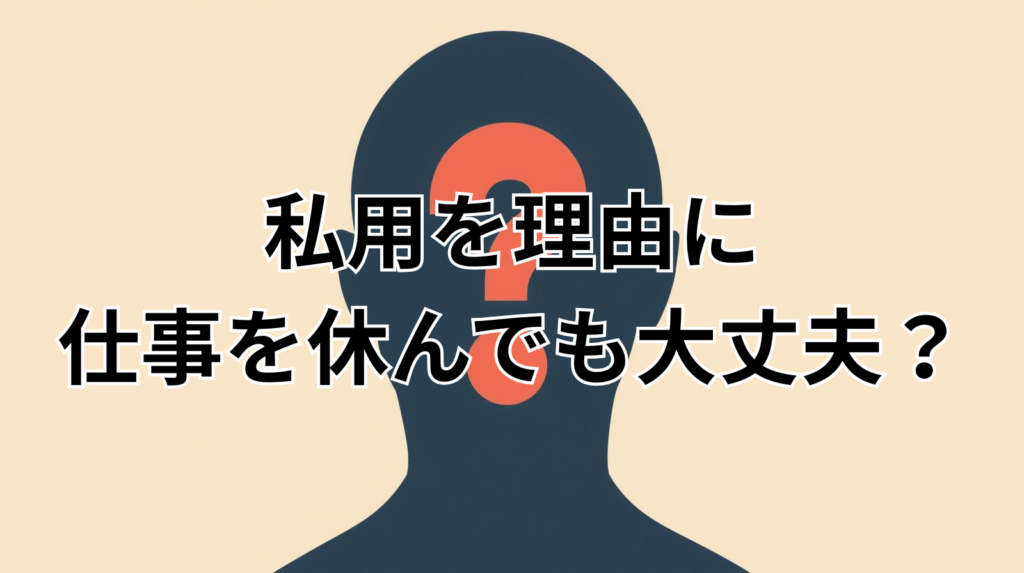
「私用で休む」と伝えるとき、「これで本当に通じるのかな?」「上司に失礼ではないかな?」と不安になる人は少なくありません。
ビジネスシーンでは「私用」「所用」「私事」といった似た表現が多く、使い分けを誤ると誤解を招くこともあります。
ここでは、「私用で休む」は正当な理由なのか、どんな場面でどの表現を使えば印象がよくなるのかを、例文付きで詳しく解説します。
この記事を読むことで、安心して休暇を取るための伝え方とマナー、信頼を損なわない表現のコツがわかります。
- 社会人が「私用で休む」ときに迷う理由
- 「私用」は仕事を休む正当な理由になる?【結論】
社会人が「私用で休む」ときに迷う理由
多くの社会人が「私用で休む」という言い方に迷うのは、「私用」という言葉があまりに広く、理由をぼかしている印象を与えるためです。
上司やチームに迷惑をかけたくないという思いから、「もっと具体的に伝えたほうがいいのでは」と考えてしまう人も多いでしょう。
しかし、有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社に詳細な理由を伝える義務はありません。
「私用のため」という表現自体が、「プライベートな事情なので詳しくは控えます」という丁寧な断りの意味を持っています。
相手に余計な詮索をさせず、かつ社会人としてのマナーを保つために使われる便利な表現なのです。
※参考:厚生労働省「年次有給休暇の取得促進特設サイト」
- 「私用」はあいまいな言葉で、説明不足と感じられることがある
- 「理由を詳しく言わないと失礼では?」と不安に思う人が多い
- 実際には法的・マナー的に問題のない表現である
「私用」は仕事を休む正当な理由になる?
「私用のため」は正式な休暇理由として認められます。
労働基準法第39条では、有給休暇の取得理由を労働者が申告する義務はないと定められており、会社は原則として拒否できません。
実際に多くの企業では、有給休暇申請書の「理由欄」に「私用のため」と記入することが一般的です。
厚生労働省の調査によると、2025年度の有給休暇取得率は約65.3%と過去最高を更新しており、
プライベートな理由で休むことが社会的にも浸透してきています。
※出典:厚生労働省「令和6年就労条件総合調査の概況」
休む理由を無理に説明する必要はありません。
大切なのは、休むことを「当然の権利」として扱いつつも、職場への配慮を忘れない伝え方をすることです。
「私用で休む」は、仕事と生活のバランスを取るための最も無難で誠実な表現といえるでしょう。
- 労働基準法上、有給取得理由は自由(会社は理由を問えない)
- 「私用」は正当な理由であり、就業規則上も一般的に認められる
- 伝え方を丁寧にすれば、誤解されることもない

社会人として「私用で休む」と言うのは、決して悪いことではありません。むしろ、自分の時間を大切にしながら働く姿勢は、今の時代に合った考え方です。この記事では、迷いや不安を解消しながら、誠実に休みを伝える方法を紹介します。
「私用で休む」とは?仕事の理由として使う意味と使い方の基本
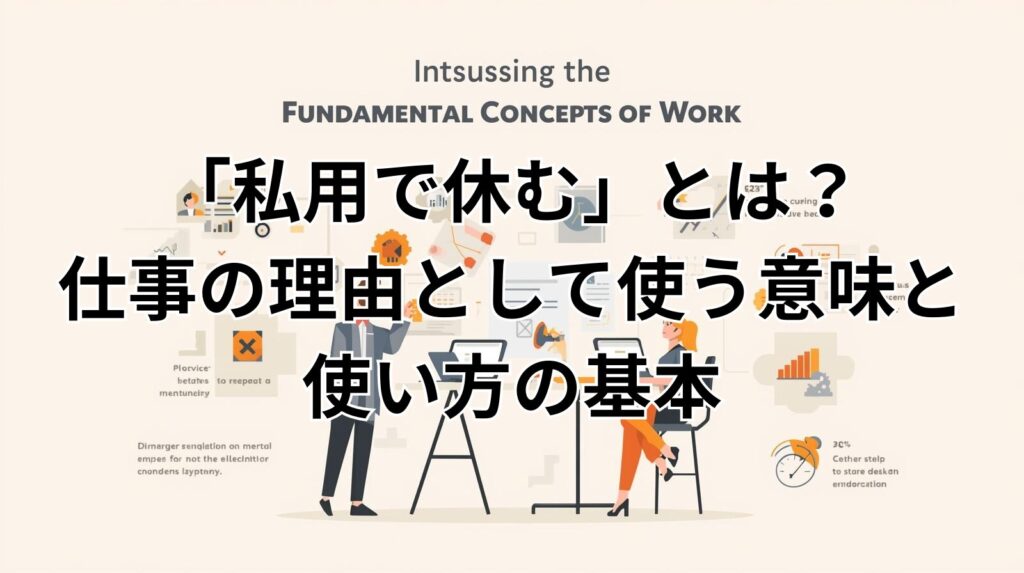
「私用で休む」という表現は、ビジネスの現場で最も一般的な休暇理由のひとつです。
しかし、似た表現に「所用」「私事」などがあり、どれを使うべきか迷う人も多いでしょう。
この章では、それぞれの言葉の意味と正しい使い分け方、そして社内・社外での表現マナーを整理します。
- 「私用」と「所用」「私事」の違い
- ビジネスシーンでの「私用」の正しい使い方
- 「私用」は社内・社外で使い分けが必要
「私用」と「所用」「私事」の違い
「私用」「所用」「私事」は似ていても、使う場面や意味合いに微妙な違いがあります。
- 私用:個人的な用事(プライベート全般)
- 所用:公私を問わず何らかの用件(ビジネス・私生活どちらも可)
- 私事:個人的な事情(退職・家庭など人生的な出来事)
「私用のためお休みをいただきます」は日常的な休暇申請に適しており、
「所用により外出いたします」はビジネスシーンでも使いやすい中立的な言い方です。
一方、「私事で恐縮ですが」は退職や身内の報告など、ややフォーマルな場面で使われます。
このように、「私用」は個人の範囲を示す柔らかい表現で、日常的な有給申請に最も適しています。
- 「私用」=個人的な用事
- 「所用」=公私を問わず何らかの用事
- 「私事」=個人の事情(ややフォーマル)
ビジネスシーンでの「私用」の正しい使い方
「私用のため」は、有給休暇や欠勤連絡の理由として使うのが基本です。
会社に提出する休暇届やメールで、「私用のため休暇を取得します」と書くだけで問題ありません。
ただし、状況によっては一言添えるとより丁寧です。
上司に直接伝える場合には次のように言い換えられます。
「申し訳ありませんが、私用のため〇日にお休みをいただきたいです。」
職場の雰囲気によっては、「家庭の事情で」や「通院のため」など、
相手が納得しやすい表現を選ぶとスムーズなコミュニケーションになります。
※参考:Indeed「家族の都合で休むときの理由はどうしたらいい?「私用のため」「家事都合」の使い分け方」
- 社内では「私用で休みます」でOK
- 社外では「所用」「私事都合」などに言い換えるのが無難
- 具体的すぎる説明は避け、簡潔さを重視する
「私用」は社内・社外で使い分けが必要
「私用」は社内では問題なく使えますが、社外の相手には避けたほうがよい表現です。
たとえば取引先へのメールで「私用のため不在です」と書くと、カジュアルすぎる印象を与える場合があります。
その場合は、次のような表現がより丁寧です。
- 「私事で恐縮ですが、〇日はお休みをいただいております」
- 「所用により不在にしております」
このように、社外では「私事」や「所用」を使うことで、フォーマルさと信頼感を保てます。
一方で、社内連絡や申請書などでは「私用のため」で十分です。
- 社内:詳細不要・上司にだけ簡潔に伝える
- 社外:取引先には「所用のため」など柔らかく伝える
- 相手との関係性によって使い分ける意識が大切

「私用」は「個人的な用事」を指すだけで、決して否定的な意味ではありません。正しい言葉の違いと使い分けを理解すれば、誰に対しても安心して使える言葉になります。まずは「意味を知ること」から始めましょう。
仕事を「私用で休む」は理由になる?実際のケース別に解説
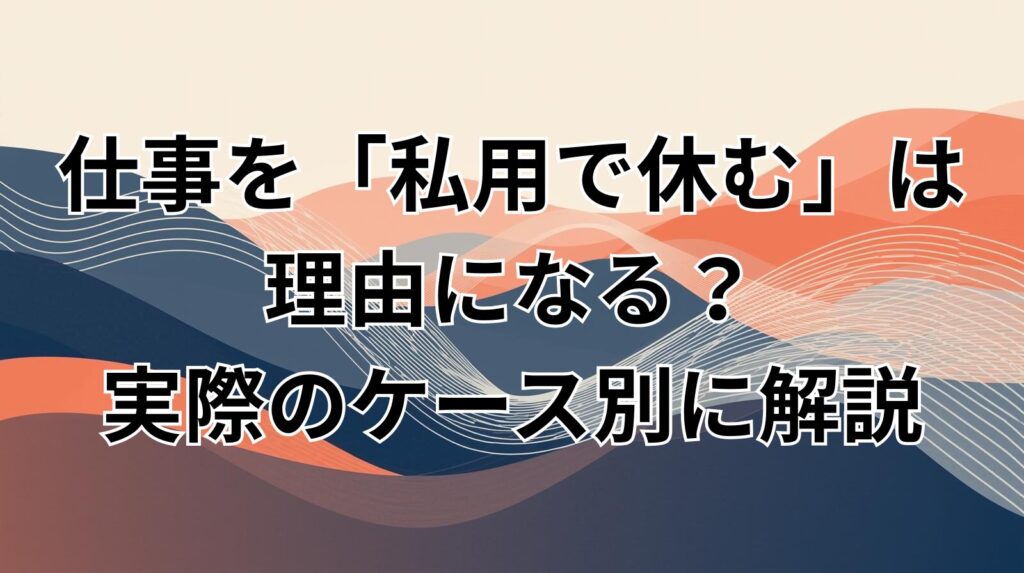
「私用で休む」と言っても、その内容は人によってさまざまです。
この章では、通院や家庭の事情などの正当なケースから、旅行などの私的な用事まで、
どのような場合に「私用」として認められるのかを整理します。
「私用」と伝えることで不誠実に思われないためのコツも紹介します。
- 通院・家庭の事情・冠婚葬祭など正当な私用の例
- 旅行や私的な用事はどう扱われる?
- 「私用=不誠実」と思われないための伝え方
通院・家庭の事情・冠婚葬祭など正当な私用の例
「私用で休む」としてよく挙げられる正当な理由には、以下のようなケースがあります。
- 通院(体調不良や定期健診など)
- 家族の介護や子どもの学校行事
- 結婚式・法事などの冠婚葬祭
- 公的手続き(役所・銀行・免許更新など)
どれも社会生活を送るうえで必要な「個人的な用事」であり、
有給休暇の取得理由として正当に認められます。
特に家族関連の事情や通院は、職場側も理解を示しやすいケースです。
「私用で」と伝えるだけでも十分ですが、親しい上司には「家庭の事情で」などと軽く添えると円滑に進むでしょう。
参考:キャリアパーク「仕事を休む理由は私用でもOK! 角を立てずに伝える連絡4ステップ」
- 通院や家族の看病・介護は「私用」として認められる
- 冠婚葬祭は「慶弔休暇」の対象になるケースもある
- 家族都合も「私用」で問題ない(家事都合など)
旅行や私的な用事はどう扱われる?
一方で、「旅行」や「趣味のイベント参加」など完全な私的理由も、「私用」として問題ありません。
有給休暇は労働者の自由な権利であり、会社はその内容を制限できないからです。
ただし、繁忙期やチームの業務状況によっては、
「なぜ今?」と疑問を持たれることもあるため、事前申請と引き継ぎをしっかり行いましょう。
「私用のため休暇をいただきます」と一言伝えたうえで、仕事への影響を最小限にする工夫が信頼につながります。
欠勤ではなく有給扱いにすることで、正当に休めることを明確にできます。
※出典:厚生労働省「しっかりマスター 有給休暇編」
- 有給休暇の範囲内であれば、旅行も「私用」に該当
- 会社は有給の理由を確認できない(労働法で保護)
- 誠実な申請と事前連絡が信頼関係維持のポイント
「私用=不誠実」と思われないための伝え方
「私用で休みます」とだけ伝えると、場合によっては冷たく感じられることがあります。
特に社内での信頼関係を大切にしたい場合は、一言添える気遣いが大切です。
たとえば、次のような表現が自然です。
「私用のためお休みをいただきます。業務には支障が出ないよう事前に対応いたします。」
このように、相手への配慮を示すことで、たとえ詳細を話さなくても誠実な印象を与えられます。
ポイントは、「理由を隠す」よりも「相手に迷惑をかけない姿勢」を伝えることです。
- 「ご迷惑をおかけします」「ご対応ありがとうございます」など一言添える
- 詳細は言わずとも、誠実な姿勢で伝えることが重要
- 普段から真面目に働くことで「信頼貯金」をつくる

「私用で休む」ことは、法律上もマナー上も問題ありません。大切なのは、伝え方とタイミングです。相手への配慮を忘れずに伝えれば、信頼関係を保ちながら休むことができます。
「私用」を理由に仕事を休む際の、上司や取引先への伝え方【例文付き】
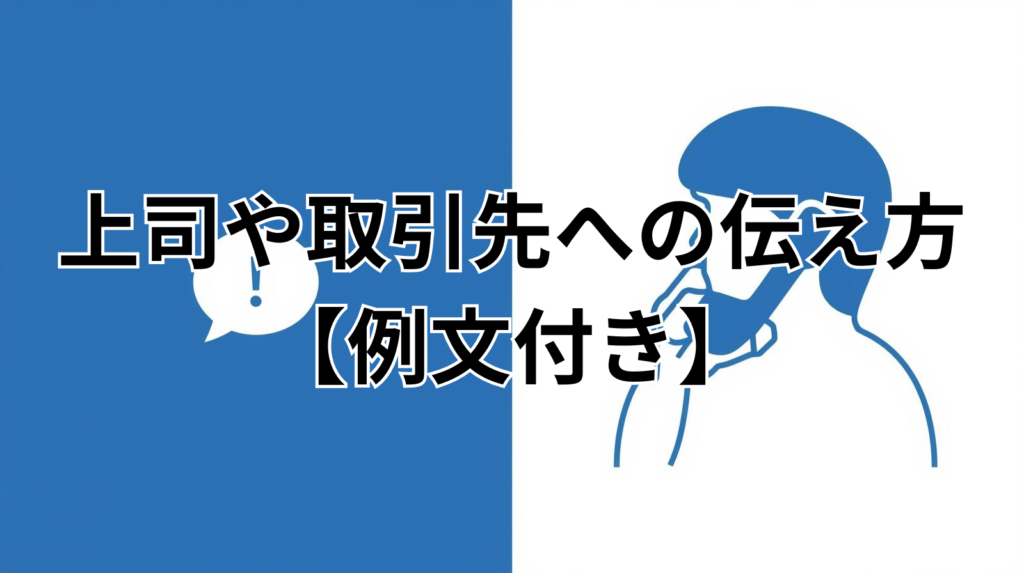
「私用で休む」と伝えるとき、誰に・どのように連絡するかで印象が大きく変わります。
この章では、社内連絡・取引先対応・当日欠勤など、状況ごとに適した伝え方と例文を紹介します。
ビジネスメール・チャット・電話など、どんな手段でも丁寧で誤解のない伝え方を意識しましょう。
- 社内への連絡メール・チャットの例文
- 取引先・顧客への伝え方と注意点
- 当日欠勤・早退の場合の対応方法
社内への連絡メール・チャットの例文
まず、最も基本的なのが上司への社内連絡です。
メールでもチャットでも、「結論→理由→配慮」の順に簡潔にまとめると好印象です。
例文①(前日までに連絡する場合)
件名:私用による休暇取得のご連絡
お疲れ様です。〇〇部の△△です。
私用のため、〇月〇日(〇)に休暇を取得させていただきたく存じます。
業務に支障が出ないよう、引き継ぎは本日中に完了いたします。
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
例文②(チャット連絡の場合)
お疲れさまです。明日、私用のためお休みをいただきます。
本日のうちに担当案件を△△さんに共有済みです。よろしくお願いいたします。
ポイントは「私用で」と簡潔に述べ、相手が確認しやすい形で伝えることです。
- 件名:「本日の欠勤について」「私用による休暇申請」
- 本文は「私用のためお休みをいただきます」で十分
- 緊急時は電話+メールの併用が望ましい
取引先・顧客への伝え方と注意点
取引先など社外の相手には、「私用」よりも「所用」「私事」の方が丁寧な印象を与えます。
また、詳細を伝える必要はなく、代替対応の有無を明示することが信頼につながります。
例文(社外メール)
件名:不在のお知らせ(〇月〇日)
〇〇株式会社 △△様
平素よりお世話になっております。〇〇株式会社の□□です。
私事で恐縮ですが、〇月〇日は所用のため終日不在にしております。
緊急のご用件は、同部署の××(メール:××@company.jp)までご連絡ください。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
「私事で恐縮ですが」と添えると、フォーマルかつ誠実な印象を与えられるでしょう。
- 社外向けでは「所用」「私事都合」で表現を変える
- 「私用で休みます」は避けるのがマナー
- 代理対応者や再連絡日を明確にしておく
当日欠勤・早退の場合の対応方法
急な体調不良や家庭の事情など、当日欠勤の際は早めの連絡が大切です。
特に始業の30分前までに上司へ電話またはチャットで連絡し、その後メールなどで改めて文面を残しておくと確実です。
電話での伝え方(例)
「おはようございます。△△です。体調が優れず、私用のため本日お休みをいただきたいと思います。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。」
メール補足(例)
件名:本日の欠勤について
お疲れさまです。〇〇部の△△です。
本日、私用のためお休みをいただきます。
業務の引き継ぎは□□さんにお願いしております。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
迅速かつ誠実な対応を心がけることで、信頼を損なわずに休暇を取得できます。
- 体調不良・家庭の事情など具体的なカテゴリで伝える
- できるだけ始業前に連絡する
- 引き継ぎ・フォロー対応も一言添えると印象が良い

「私用で休む」と伝えるときは、詳細を語りすぎず、簡潔に・丁寧にがポイントです。定型文を覚えておくだけで、どんなシーンでも落ち着いて対応できます。
「私用」を理由に仕事を休むときのマナーと注意点
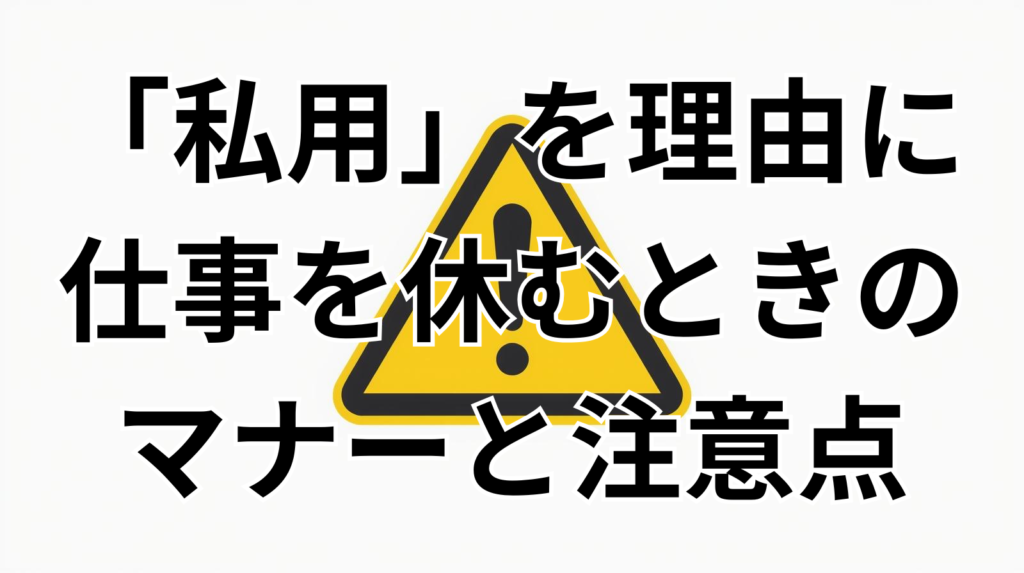
「私用で休む」という言葉自体は問題ありませんが、伝え方やタイミングを誤ると誤解を招くことがあります。
この章では、有給休暇の申請ルールや、詳細を聞かれたときの答え方、
「私用」と「所用」を上手に使い分けて印象を良くするコツを紹介します。
- 有給休暇との関係と申請ルール
- 詳細な理由を聞かれたときの上手な答え方
- 「私用」と「所用」の使い分けで印象を変える
有給休暇との関係と申請ルール
「私用で休む」は、基本的に有給休暇(年次有給休暇)を取得する正当な理由として認められています。
有給休暇は労働者の権利として保障されており、会社は理由によって取得を拒否できません。
※参考:厚生労働省「年次有給休暇制度」
ただし、企業によっては申請期限やフォーマットが定められている場合があります。
前日や当日に申請するのではなく、できる限り1週間以上前に伝えるのが理想です。
また、休暇理由を「私用」とだけ書いても問題ありません。
上司が聞いてきた場合のみ簡単に説明すれば十分です。
- 有給は「私用」で取得可能(理由を説明する義務なし)
- 申請は原則事前に(会社によってはシステム申請)
- 当日申請はやむを得ない場合のみ
詳細な理由を聞かれたときの上手な答え方
「私用」と伝えた際に、上司から「どんな用事?」と聞かれることもあります。
そんなときは、必要以上に具体的に答えないのがポイントです。
以下のように対応すると自然です。
- 「家庭の事情で手続きがありまして。」
- 「個人的な用事のため、当日は外せなくて。」
このように答えれば、相手にも誠実な印象を与えられます。
どうしても詳しく話したくない場合は、
「私用でして、詳細は控えさせてください」と伝えても問題ありません。
有給の理由を開示する義務は法律上ありません。
- 「私的な用事がありまして」とやんわり伝える
- 無理に詳細を話す必要はない
- 圧力的な質問はハラスメントの可能性あり
「私用」と「所用」の使い分けで印象を変える
同じ意味でも、言葉の選び方で印象が変わります。
社内申請では「私用」が自然ですが、社外メールでは「所用」を使うと丁寧に聞こえます。
| シーン | 適した表現 | 印象 |
|---|---|---|
| 社内連絡 | 私用のため | 柔らかく一般的 |
| 社外メール | 所用のため | 丁寧でビジネス向き |
| フォーマル報告 | 私事で恐縮ですが | 改まった印象 |
このように、相手との関係性に応じて言葉を切り替えることで、
不必要な誤解を避けつつ、社会人としての信頼感を保てます。
- 社内:率直に「私用で」
- 社外:丁寧に「所用のため」
- 相手や場面での印象を意識して選ぶ

「私用」という言葉は便利ですが、使い方を間違えると誤解を招くこともあります。社内・社外での印象の違いを意識して、TPOに合わせた使い分けを心がけましょう。
私用を理由に仕事を休むときのトラブル防止と企業側の対応ルール
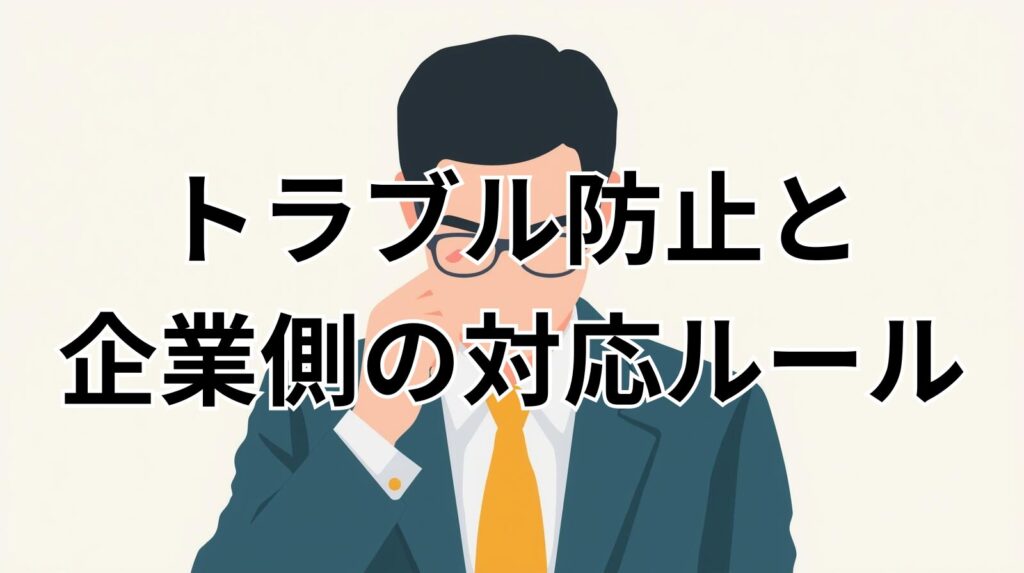
「私用で休む」という表現はシンプルですが、企業側のルールや制度とズレがあると、
トラブルにつながることもあります。
この章では、会社が定める休暇ルールや法的な取り扱い、
そしてハラスメントを防ぐためのポイントを解説します。
- 企業が「私用休暇」に求める基本マナー
- 私用による欠勤で注意すべき法的ポイント
- 社内規定やハラスメント回避のための仕組み
企業が「私用休暇」に求める基本マナー
企業は「私用による休暇」を認める一方で、職場の秩序と業務の円滑性を重視しています。
そのため、最低限守るべきマナーとして、以下の3点が挙げられます。
- 早めの申請と上司への報告
→ 前もって共有することで、業務調整がしやすくなります。 - 業務引き継ぎの明確化
→ 担当者を伝えるなど、チームに迷惑をかけない配慮が大切です。 - 復帰後のフォロー
→ 「ご迷惑をおかけしました」と一言伝えることで印象が良くなります。
特に社内文化によっては、形式よりも「一言の気遣い」を重んじる職場も多いため、
人間関係を円滑に保つ工夫が信頼につながります。
- 事前申請・連絡を徹底すること
- 勤怠記録に正確に記載すること
- 無断欠勤・虚偽申告は信用を失う
私用による欠勤で注意すべき法的ポイント
「私用で休む」場合でも、欠勤と有給休暇の違いを正しく理解しておく必要があります。
- 有給休暇(年休):労働基準法により、取得は労働者の権利。理由は問われない。
- 欠勤(無給):会社の承認を得ずに休む場合。給与控除・評価への影響もあり得る。
企業が「理由を確認する」ことはあっても、
私用という理由をもって有給申請を拒否することは違法です。
※出典:厚生労働省「しっかりマスター 有給休暇編」
また、欠勤日数が多い場合は「勤怠不良」として扱われるリスクもあるため、
継続的に休みが必要な場合は、早めに上司または人事へ相談しましょう。
- 有給は労働者の権利であり、拒否は原則不可
- 不当な理由確認や取り消し要請はNG
- 就業規則に沿った正しい運用が重要
社内規定やハラスメント回避のための仕組み
企業によっては、「私用休暇」「特別休暇」などの制度を整備している場合があります。
こうした制度は、社員のプライベートを尊重しながら、
職場内でのトラブルを防ぐ目的でも設けられているのです。
一方で、「休暇の理由を細かく聞かれる」「私用が理解されにくい」など、
心理的ハラスメント(いわゆるマイクロアグレッション)につながるケースもあります。
そのため、会社は個人情報保護の観点からも、
理由を強制的に開示させないルールを設けることが望ましいとされています。
参考:総務省「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」
従業員側としても、「必要最低限の説明」と「誠実な対応」を意識することで、
無用なトラブルを避け、互いに信頼できる環境を保てるでしょう。
- 企業は休暇制度を明文化する必要がある
- 「私用」への詮索や圧力はパワハラ認定リスク
- 安心して休める文化づくりが企業の信頼につながる

企業側にも、私用休暇をめぐるルールや法的配慮が求められます。従業員・管理者の双方が理解しておくことで、不要なトラブルを防ぎ、安心して働ける環境をつくれます。
仕事の働き方の変化と「私用休暇」の位置づけ
近年、働き方改革やリモートワークの普及により、
「私用で休む」という行為の意味合いが少しずつ変わってきています。
この章では、現代の労働環境における私用休暇の新しい捉え方と、
企業や国のデータをもとにした背景を解説します。
- リモートワーク時代の休暇・中抜けルール
- 有給休暇取得率・労働環境のデータ(厚労省・総務省より)
- 私生活と仕事の両立を支える企業の制度事例
リモートワーク時代の休暇・中抜けルール
リモートワークが一般化したことで、
「私用のために1日休む」から「一時的に離席する(中抜け)」という柔軟な働き方が増加中です。
企業によってルールが異なりますが、一般的には以下のような対応が取られています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 休暇扱い | 半日休暇・時間単位の有給取得制度を活用 |
| 中抜け対応 | 上司にチャットやスケジュールで共有し、業務に支障がないよう調整 |
| 注意点 | 中抜けを繰り返す場合は勤怠管理上の記録が必要 |
厚生労働省の指針でも、「労働時間の柔軟化」が推奨されており、
個人の事情に応じた勤務形態が尊重されつつあるのです。
参考:厚生労働省「テレワークの適切な導入と実施のためのガイドライン」
- 在宅勤務でも「私用中抜け」は就業規則に従う
- 勤務時間中の外出・離席は事前申請が原則
- 業務報告を明確にして信頼関係を保つ
有給休暇取得率・労働環境のデータ(厚労省・総務省より)
日本では依然として有給休暇の取得率が課題とされていますが、
近年は少しずつ改善傾向が見られます。
厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査」によると、
年次有給休暇の取得率は65.3%(前年より3.2ポイント上昇) でした。
総務省の「労働力調査」によれば、非正規雇用を含む働き方の多様化も進み、
「私用休暇」の柔軟な運用が進んでいます。
出典:厚生労働省「令和6年就労条件総合調査の概況」
出典:総務省統計局「労働力調査(基本集計) 2024年(令和6年)平均結果」
こうしたデータは、「私用=わがまま」ではなく、正当な権利の一部だと示しているといえるでしょう。
- 2025年の有給取得率は約62%(前年比+2pt)
- 働き方改革で「休むこと」への理解が進む傾向
- 詳細は厚生労働省「令和6年就労条件総合調査 結果の概況」参照
私生活と仕事の両立を支える企業の制度事例
多くの企業が、社員のプライベートを尊重する取り組みを始めています。
注目されているのは、以下のような制度です。
- 時間単位有給休暇制度:1時間単位で有給を取得できる
- ファミリーサポート休暇:家族の通院・介護などに対応
- メンタルヘルス休暇:心身のリフレッシュを目的とした特別休暇
企業の制度は、社員の「私用」を尊重しながら、
業務への影響を最小限にする仕組みとして導入されています。
政府も企業に対し、柔軟な休暇制度の整備を推奨しており、
「私用で休む」ことが働きやすさの象徴になりつつあるのです。
参考:厚生労働省「多様な働き方の実現応援サイト」
- フレックスタイム・在宅勤務制度の導入が拡大
- 「時間単位有給」など柔軟な休暇取得が可能に
- 企業側も「休みやすい環境」を整える動きが加速

リモートワークや柔軟な働き方が広がる今、「私用」と「仕事」の境界はあいまいになりつつあります。大切なのは、会社との信頼関係を保ちながら、自分の生活も大切にする姿勢です。
「私用」を理由に仕事を休んでも大丈夫

ここまで、「私用で休む」という言葉の正しい使い方や注意点、
そして現代の働き方における新しい位置づけについて解説してきました。
最後に、この記事のポイントを整理し、読者が安心して休めるための実践的な行動をまとめます。
- 「私用」でも胸を張って休んでいい理由
- 上手に伝えて信頼を保つコツ
- 関連記事・出典・参考リンク一覧
「私用」でも胸を張って休んでいい理由
「私用で休む」は、決して後ろめたい行為ではありません。
労働基準法に基づく有給休暇はすべての労働者に認められた権利であり、
理由を問わず、堂々と使ってよい制度です。
企業によっては「家庭の事情」「所用」などの表現を推奨するケースもありますが、
本質的にはどの言葉を使っても問題ありません。
重要なのは、誠実な態度と職場への配慮を忘れないことです。
出典:厚生労働省「年次有給休暇制度」
- 「私用」は正当な休暇理由であり、権利として守られている
- 遠慮せず休むことが、健康と仕事の質の両立につながる
- 無理をせず、安心してリフレッシュすることが大切
上手に伝えて信頼を保つコツ
「私用」という言葉を使うときは、相手との関係性や場面に応じた表現選びが鍵になります。
- 社内 → 「私用のためお休みをいただきます」
- 社外 → 「所用のため失礼いたします」
- フォーマル → 「私事で恐縮ですが」
場面に応じて使い分けることで、
プライベートを守りつつ、社会人としてのマナーも保てます。
また、体調や家庭の事情など、やむを得ない事情の場合は、
「家庭の事情で手続きがありまして」など、相手が納得しやすい伝え方を選びましょう。
- シンプルで丁寧な言葉を使う
- 日頃のコミュニケーションで信頼を積み重ねる
- 「誠実さ」が一番のマナー
関連記事・出典・参考リンク一覧
この記事をさらに深く理解したい方は、以下の公的資料や関連コンテンツも参考にしてください。
仕事も私生活も大切にするために、
「私用」という言葉を正しく使いこなし、自分らしい働き方を実現しましょう。
心の余裕が生まれることで、仕事のパフォーマンスもきっと上がるはずです。

迷ったときは、「信頼」と「誠実さ」を軸に。
それが、“私用で休む”をポジティブに変える一番の方法です。
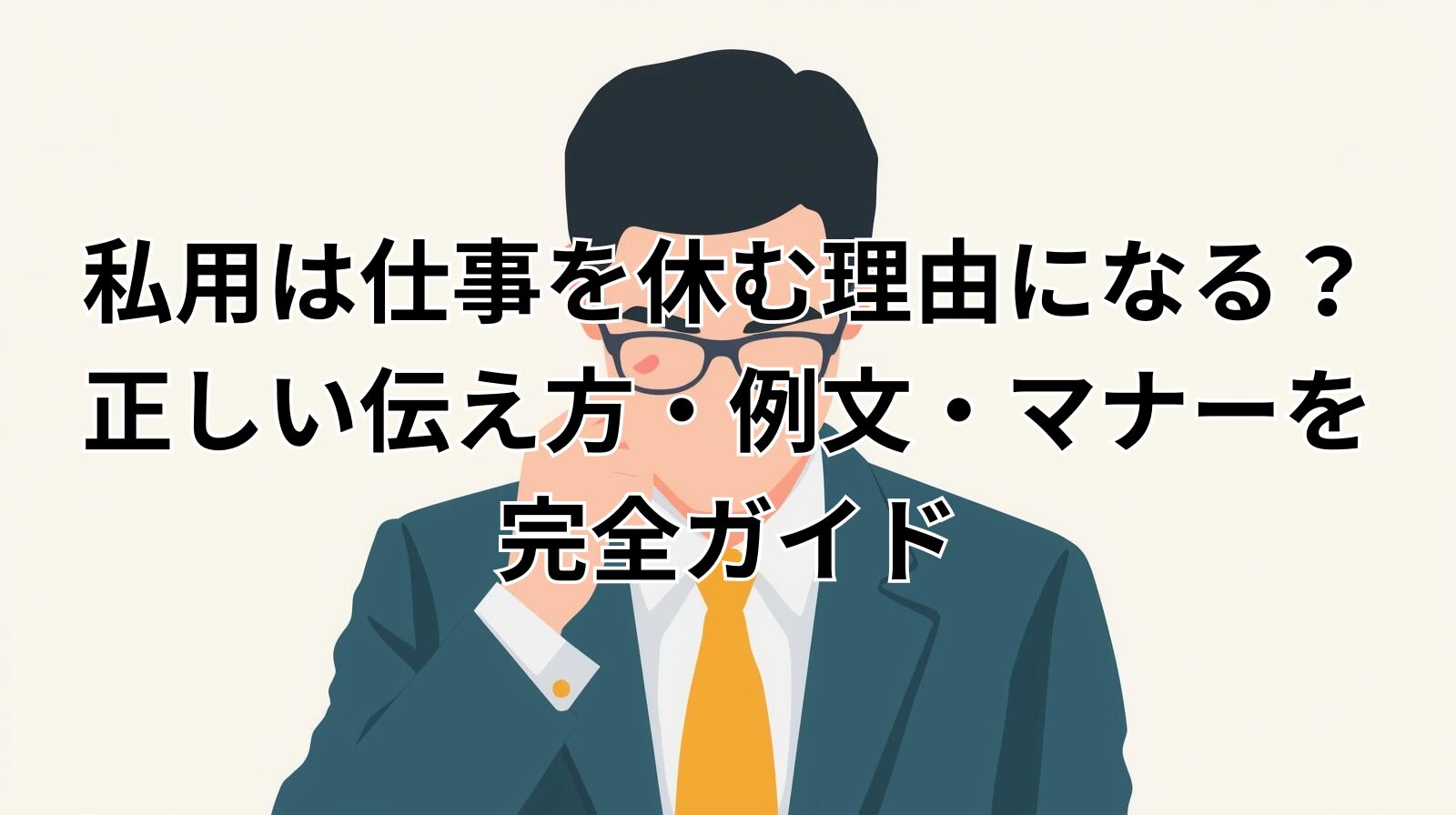


コメント